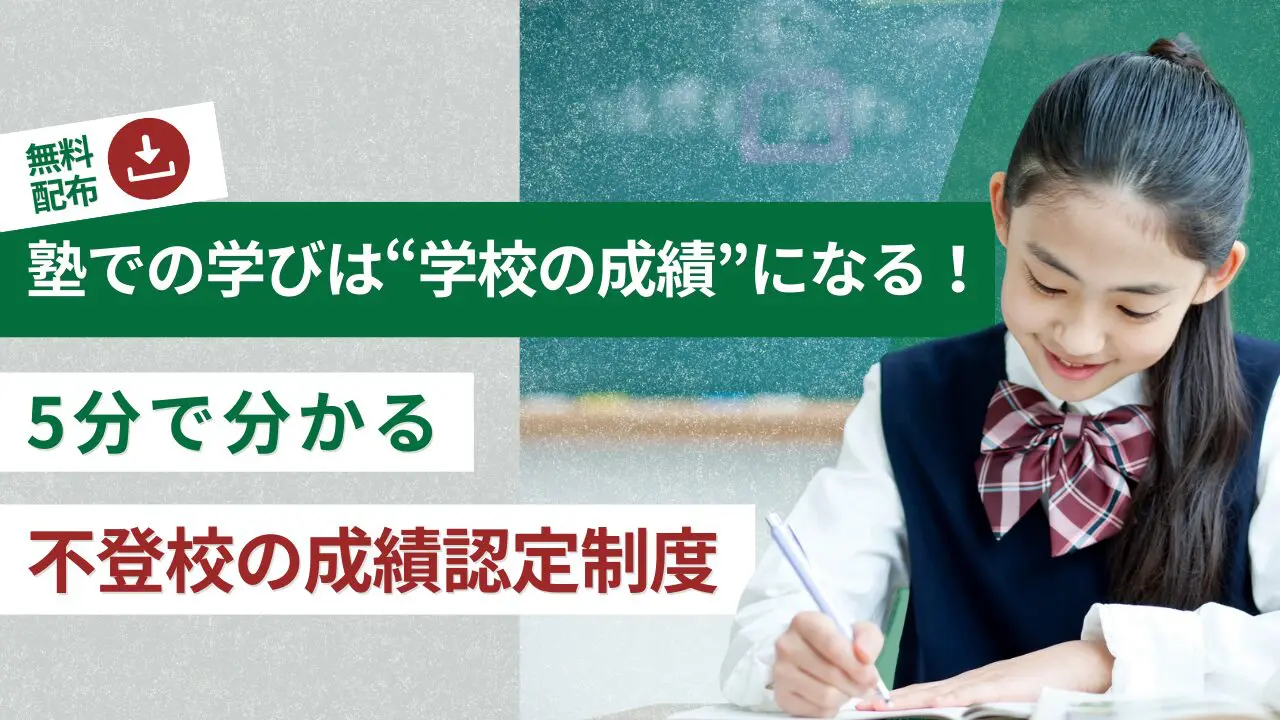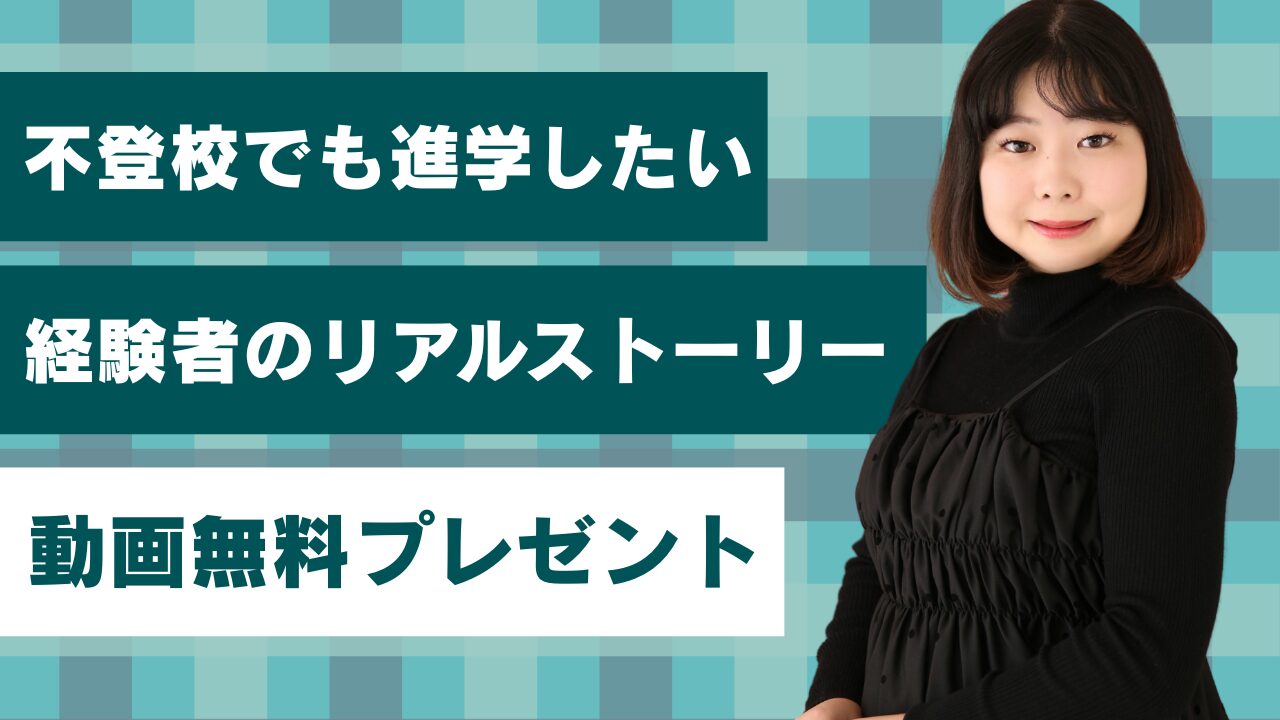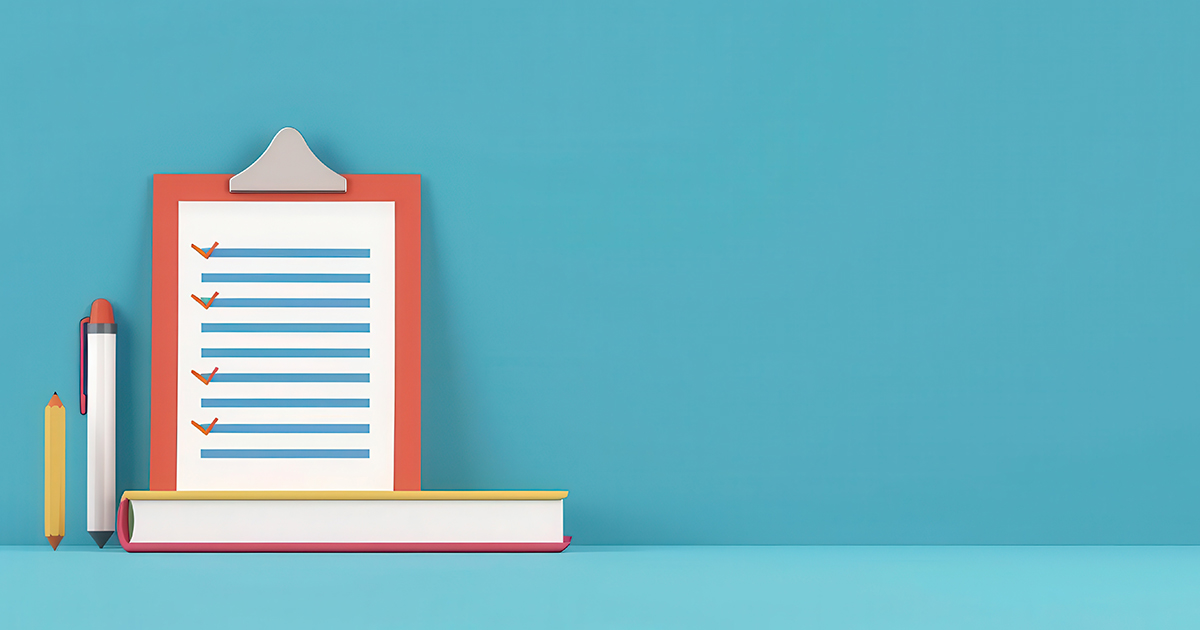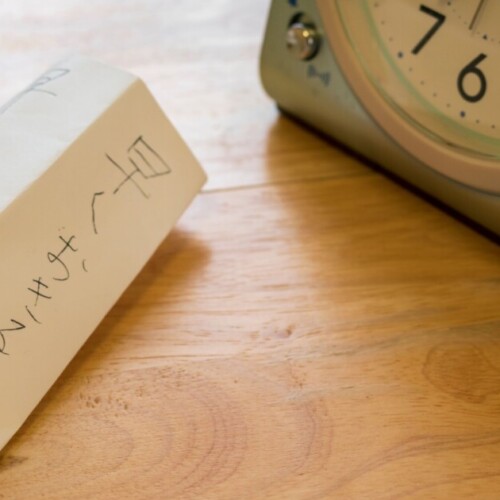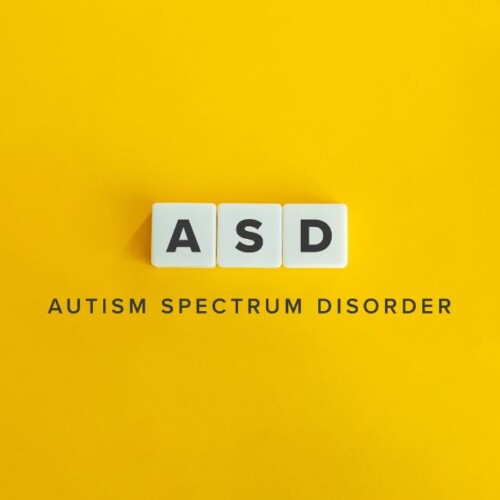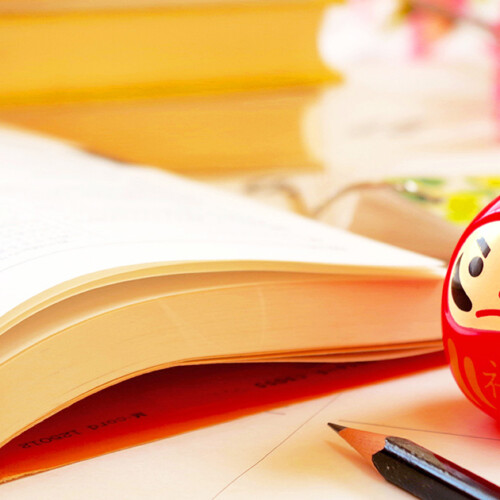【不登校混乱期】不登校ケアに「待つ」勇気を。ネガティブ・ケイパビリティという考え方
「早く昼夜逆転を治したい」。
「早く外出できるようになってほしい」。
「早く進路を決めないと」。
早く、早く、早く……!
日々膨大な情報に触れるなか、私たちは知らず知らずのうちに、「早いこと=よいこと」と思わされがちです。ままならない現状に、ついつい焦ってしまうことも。
しかし、不登校の子どものケアに焦りは禁物です。
【不登校混乱期とは】
不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。
無料プレゼント
あなたの声を聞かせてください
目次
1. ネガティブ・ケイパビリティとは
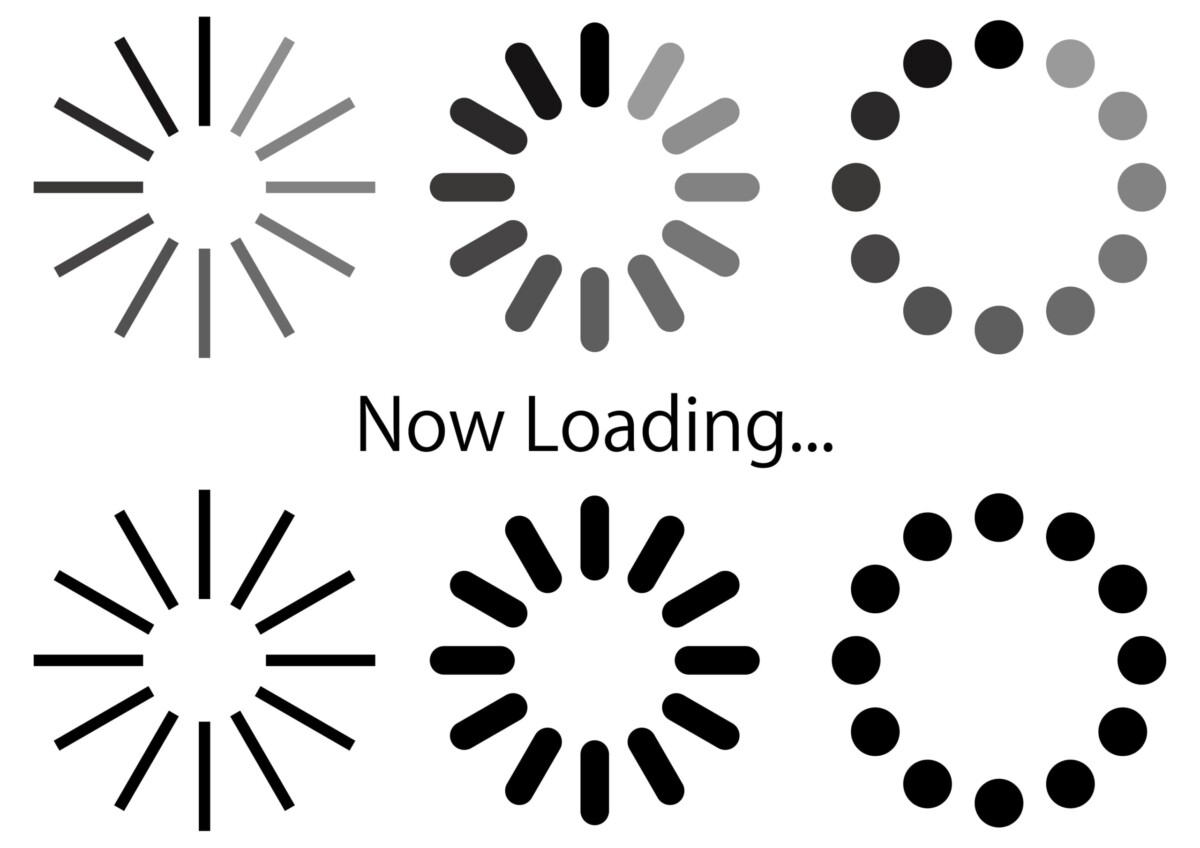 ネガティブ・ケイパビリティとは、19世紀のイギリスの詩人、ジョン・キーツが弟へ宛てた手紙の中で使った言葉です。
ネガティブ・ケイパビリティとは、19世紀のイギリスの詩人、ジョン・キーツが弟へ宛てた手紙の中で使った言葉です。
彼は、優れた文学者には「曖昧さや疑念のなかにあっても、それを受け入れる能力」が備わっていると考え、それを「ネガティブ・ケイパビリティ」と名付けました。
その後、イギリスの精神科医、ウィルフレッド・R・ビオンがこの概念に注目し、心の治療に取り入れました。
ネガティブ・ケイパビリティは、「不確実なものや未解決なものを、不安やイライラを感じることなく、受け入れる能力」とされています。
2. なぜ、不登校ケアにネガティブ・ケイパビリティが必要なの?
 不登校の子どもにとって、保護者の存在は重要です。
不登校の子どもにとって、保護者の存在は重要です。
学校へ行かないことで日常的に接する人が少なくなり、必然的に保護者と過ごす時間の比重が大きくなるからです。
あなたは今、不登校の子どもの不確実な状況に、不安やイライラを感じているかもしれません。
保護者が不安やイライラを感じていると、子どもはそれを敏感に感じとり、子ども自身も不安やイライラを感じます。
その様子を見て保護者が不安やイライラを募らせ、子どもに伝わり……
この悪循環を断ち切るのに役立つのが、ネガティブ・ケイパビリティです。
保護者がネガティブ・ケイパビリティを身につけると、子どもに関する不確実な状況を、そのままに受け入れられるようになります。
不安やイライラを感じることなく、お子さんのペースに合わせてじっくりと待つことができるようになれば、保護者から子どもへ伝わる感情も変わります。
保護者が落ち着いていれば、子どもも落ち着いて安心して過ごすことができるのです。
3. まずは、小さな「心の習慣」からはじめてみよう
 ネガティブ・ケイパビリティを身につけるためには、以下のことを意識してみてください。
ネガティブ・ケイパビリティを身につけるためには、以下のことを意識してみてください。
自分の感情に気づく
まずは、自分の感情に気づくこと。
「今、私は不安を感じているな」。
「イライラしているな」。
自分の感情に気づくことで、知らず知らずのうちに感情に振り回されていることが少なくなります。
【自分の感情に気づくための方法】
■日記やノート
その日の出来事や感じたことを書くことで、自分の感情の流れを把握することができます。
きれいな文章にしなくても構いません。むしろ、飾り気のないむき出しの言葉こそが、偽りのないあなたの気持ちです。
■瞑想やマインドフルネス
呼吸に意識を集中することで、雑念を払い、自分の感情と向き合うことができます。
瞑想は、静かな場所で座って行うイメージがあるかもしれませんが、必ずしもそうである必要はありません。
マインドフルネスとは、「今、ここ」に意識を集中することです。
皿洗いをしながら手の感触や水の温度に意識を集中したり、散歩をしながら足の裏の感覚や風の音に意識を集中したり、歯磨きをしながら歯ブラシの動きや歯磨き粉の味に意識を集中したりと、日常の行動のなかでも、マインドフルネスを実践することができます。
■誰かに気持ちを話す
信頼できる人に話すことで、自分の感情を整理することができます。
頭の中で考えているだけではうまく言葉にならなかったとしても、誰かに話しているうちに自分の感じている気持ちの「名前」が見つかります。
自分の感情を受け入れる
自分の感情に気づいたら、次は、その感情を受け入れること。
たとえ、不安やイライラを感じたとしても、感情にフタをしたり、その感情を抱いたことに罪悪感を抱いたりする必要はありません。
「不安を感じてもいい」。
「イライラしてもいい」。
自分の感情を受け入れることで、感情を否定することなく、そのままに向き合うことができます。
完璧主義を捨てる
「こうあるべき」。
「こうでなければならない」。
完璧主義は、自分を苦しめる原因になります。そして、それが子どもに向けられると、子どももつらい思いをすることになります。
「まあ、いいか」と思うことで、「べき」思考では見つからなかった道が見えてくることもあります。
完璧主義が頭をもたげてきたことに気づいたら、「ああ、自分は今、完璧主義になっているな」と、そのままに受け入れてください。
「完璧主義な自分はダメなんだ」と、自分を否定する必要はないんです。
英語にdefenestrationという表現があります。「窓から何かを投げ捨てる」ことを表す言葉です。保護者世代には少し懐かしい「いらない〇〇を窓から投げ捨てろ」というネットスラングもありますね。
そのイメージで、頭の中で「完璧主義」をポイっと投げ捨ててみてください。あるいは、紙に大きく「完璧主義」と書いて、くしゃっと丸めてゴミ箱に捨ててもいいです(窓からは投げ捨てないでくださいね)。
完璧主義にはこんな冗談みたいな方法で向き合ったほうが、スッキリ気楽になれます。
子どもを一人の人間として尊重する
子どもは、保護者とは別の人格を持った、一人の人間です。
「子どもにこうあってほしい」という願いや期待は、子どもという存在と最初に出会っ瞬間から、ずっと抱き続けてきたことでしょう。
それは、大人が子どもを守り育てるうえで、自然な感情です。
それでも、あなたはあなた、子どもは子どもです。
子どもの個性やペースに目を向け、それを尊重しましょう。
不登校の子どもの悩みや困り感のなかには、保護者にとって理解が難しいこともあるかもしれません。
その「わからなさ」こそが、子どもの個性。
「ここが自分とは違うんだな」と、そのままに受け入れましょう。
4. ガマンや根性論とは関係がない!
 ネガティブ・ケイパビリティは、不安やイライラをただ単に「ガマン」することとは違います。
ネガティブ・ケイパビリティは、不安やイライラをただ単に「ガマン」することとは違います。
「ガマン」は、自分の感情を抑え込むことですが、ネガティブ・ケイパビリティは、自分の感情を認め、受け入れることです。
不安やイライラを抑え込むのではなく、不安やイライラを認め、受け入れる。何もガマンする必要はありません。
また、ネガティブ・ケイパビリティは、根性論とも無関係です。
根性論は「精神力で困難を乗り越えろ」という考え方ですが、ネガティブ・ケイパビリティは精神的な力の有無を問題にしません。困難なことに立ち向かったり、乗り越えたりするという発想も、ネガティブ・ケイパビリティとは無縁です。
風になびく柳の枝のように、しなやかに。
ネガティブ・ケイパビリティは、それくらい柔らかく、やさしく、自然なもの。
だからこそ、強いのです。
5. 信じて、焦らず、じっくりと。
 ネガティブ・ケイパビリティは、一朝一夕に身につくものではありません。
ネガティブ・ケイパビリティは、一朝一夕に身につくものではありません。
「ネガティブ・ケイパビリティを身につけるのにも、ネガティブ・ケイパビリティが必要なの?」
まるで禅問答のようですが、初めは不安やイライラを感じている自分に気づくだけで十分です。
不登校の子どもは、勉強や進路選択においては、ほかの子どもの数歩後ろをあゆんでいるように感じられるかもしれません。
でも、人生の早い時点で、立ち止まる勇気を持ち、自分自身を知るチャンスが訪れたという点では、ほかの子どもよりも先をあゆんでいます。
順番が少し違うだけで、子どもはちゃんと成長しています。
子どもの成長を信じて、焦らず、じっくりと、待つ。
あなた自身の心を削らないことが、不登校の子どもをケアする一番大切な秘訣です。
無料プレゼント
あなたの声を聞かせてください
「不登校オンライン」では、会員向けの記事(有料)をご用意しています。不登校のお子さんをサポートするために知っておきたい情報や、同じ悩みをもつ親御さんの体験談などを掲載しています。お申し込みは下記から(30日間無料)。