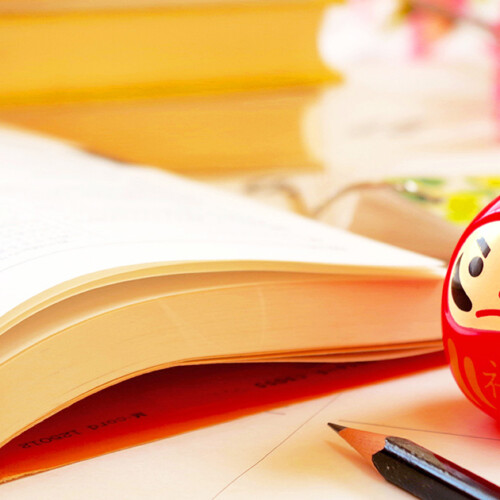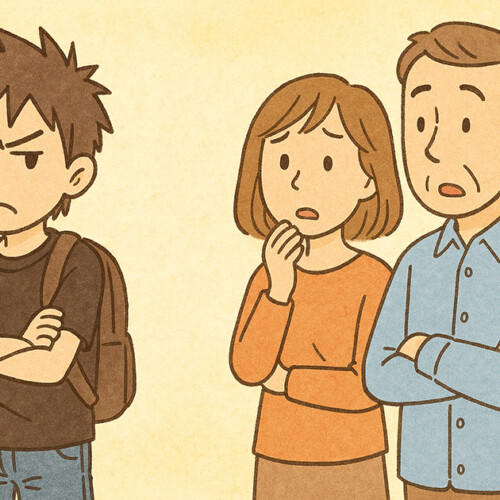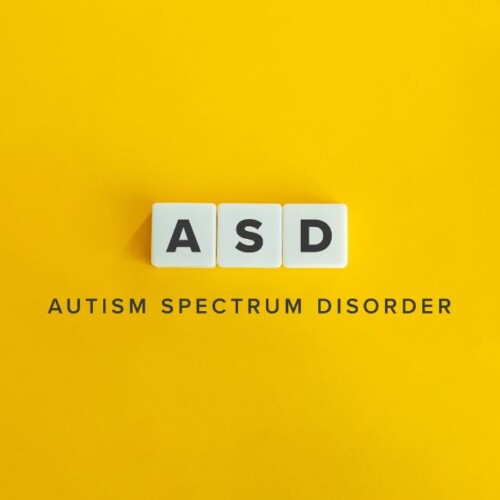【不登校回復期】「勉強したほうがいいかな…」のつぶやきにどう応える?【不登校の知恵袋】
不登校の回復期にあたる時期、子どもがふとこぼす「勉強したほうがいいかな…」というつぶやきは、親にとって嬉しさと不安が入り混じる瞬間です。思わず「そうだね、そろそろ始めよう!」と反応したくなるかもしれませんが、その“反応の仕方”が、子どもの今後に大きく影響することがあります。
本記事では、こうしたつぶやきに対してどのように向き合えばよいのかを、実践的かつ丁寧に整理していきます。
【不登校回復期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「やる気の芽生え」を押しつぶさないために
子どもの「勉強したほうがいいかな…」というつぶやきは、回復のプロセスにおいて非常に繊細な“心の動き”です。
小さな言葉に、大きな意味がある
この時期の子どもは、「できそうな気がするけれど、やっぱり怖い」「何をやればいいかよくわからない」といった不安を抱えています。つぶやきの裏には、期待と自信のなさが混在しており、「動きたいけど失敗したくない」という心の揺れが表れています。
だからこそ、親がこの言葉に飛びつきすぎると、「またすぐ本格的な勉強を始めなきゃいけないのかな」「もう遊べなくなるのかな」と、プレッシャーとして伝わることがあります。大切なのは、子どもの発言の“温度”に合わせることです。
「本当に勉強を始めるタイミング」を待つ心構え
子どもの回復には波があります。昨日は前向きだったのに、今日は一日寝ていた――そんな日々が続くのが不登校回復期の特徴です。
子どもなりのペースに信頼を置く
「やってみたい」と思うことと、「実際にやる」「継続できる」ことは、別の段階です。だからこそ、つぶやきが出たからといって、すぐに教材を用意したり、学習計画を立てたりする必要はありません。
「そっか、そんなふうに思うんだね」と、まずはその感情そのものに寄り添いましょう。無理に次のステップへ誘導するのではなく、「その気持ちが芽生えたこと」を一緒に大切にできる関係性が、子どもの安心につながります。
「勉強」を始める前に確認したい3つの視点
つぶやきが出たとき、すぐに行動に移すのではなく、一呼吸おいて親が意識しておきたい視点があります。
1. 「今の生活」が子どもにとって安定しているか?
心が落ち着かないまま勉強を始めると、それが新たなストレスになる可能性もあります。子どもが今の生活の中で安心できているかどうかを見極めましょう。
たとえば、家族との距離感や食事・睡眠のリズムが安定していることは、回復の土台になります。そこに無理を重ねるのではなく、「日常の安定があるから、勉強もしてみたくなる」という順序を意識しておくことが大切です。
2. 「勉強=学校に戻る準備」としない
つぶやきに対して、「じゃあ、来月から登校できるように勉強しようね」といった言葉は避けましょう。登校再開を目標に据えると、子どもは「やっぱり学校に行かないとダメなのか」と感じてしまうことがあります。
あくまで「勉強は、自分のために、今できることを少しずつやってみるもの」というスタンスを持っていたほうが、子どもは安心して勉強に取り組めます。
3. 「やらなきゃ」に変わる前に、一緒に“意味”を探す
「やったほうがいいかな」という気持ちが、「やらなきゃ」に変わると、勉強は一気につらいものになります。
「なんでそう思ったの?」とさりげなく聞いてみることで、子どもが自分の中にあるモヤモヤを整理できることもあります。将来への不安や同級生とのギャップを感じたこと、あるいは単純に「時間がもったいないかも」という気づきかもしれません。
その動機を親が一緒に肯定していくと、「じゃあ何かやってみようか」という流れが自然に生まれます。
実際に勉強を始めるときの工夫
子どもが「ちょっとやってみたい」と言ったとき、その最初の一歩が大切です。無理なく、気軽に、そして楽しさも交えながら始められる工夫を考えてみましょう。
小さく始める、続けようとしない
最初は「1問だけ」「10分だけ」でも十分です。むしろ「毎日続けよう」と思わせることがプレッシャーになる可能性があります。
たとえば、子どもが好きな教科や得意なジャンルの問題を一緒に見てみたり、勉強系のYouTubeを一緒に見ることも立派な“学びの時間”です。
スタートの伴走は、あくまで「一緒に」
「やるならちゃんとやらないと意味がない」などと言うと、やる気の芽は簡単にしぼみます。
親が一緒に「こんなのもあるんだね」「ちょっと面白いね」と声をかけながら過ごすことで、勉強が“会話のきっかけ”にもなります。
子どものつぶやきが出た“きっかけ”の多様性に目を向ける
「勉強したほうがいいかな…」という言葉は、本人の中に生まれた小さな芽生えですが、その背景には多様なきっかけが存在します。
例えば、
ふとスマートフォンで見た進学情報、
SNSで同年代が塾に通っている投稿、
家族が見ていたニュース番組、
部屋に置かれた参考書など。
直接的な体験でなくても、日常の中にふとした“揺れ”が生じたタイミングで、そのつぶやきが出ることがあります。
つまり、「勉強しようかな」という言葉が出た背景は、偶然や外部からの刺激が大きく影響することも多いのです。
そのため、親は「何があったんだろう」と根掘り葉掘り探るより、「そう思ったんだね」と、その気持ちを丁寧に拾う姿勢が大切です。子どもの変化に気づけること自体が、回復期にある子どもとの大切な関係性の一歩となります。
「勉強しなくても大丈夫」と言える背景にある長期的な視点
回復期にある子どもにとって、学習の再開は「再び失敗するのでは」という不安と表裏一体です。
そんなとき、親が「もし続かなくても大丈夫だよ」と言えることは、子どもにとって大きな安心感になります。
この「大丈夫」は、今だけでなく、もっと長いスパンで見た時に、子どもには回復と成長の可能性があるという信頼に基づいています。
たとえば、中学卒業や高校卒業から数年後に学び直して大学に進んだ人、通信制高校や高卒認定試験を経て再スタートを切った人も数多くいます。
つまり、今この瞬間の学習の有無が、将来の可能性すべてを決めるわけではありません。子どもにとって“いつでもやり直せる”という大人の姿勢や信念が伝わることが、何よりの後押しになります。
ただしこのあたりは、お子さんの性格にもよります。「せっかく勉強しようとしてるのに、なんで続かないことが前提なの!」と反発されることもあります。「具体的な声かけの方法や内容」は、サポート団体なども利用して検討しましょう。
親自身の心を整える——期待と焦りのコントロール
「勉強したほうがいいかな…」という子どものつぶやきに、親が過剰に反応するのは、「ようやくここまで来た」「今逃すとまた元に戻るかも」という期待と焦りが入り混じるからかもしれません。
この“高ぶり”をそのまま子どもに向けると、無意識に圧をかけることにつながります。
そんなときは、親自身も「少しずつでいい」「今の一歩を喜ぼう」と、自分の思考を言葉にして落ち着かせる時間を持つことが効果的です。
日記に書く、
同じような立場の保護者の体験談を読む、
自分が信頼できる第三者に話してみるなど、
自分の心の整理を外に出す手段をもっておくと、子どもに余計な圧をかけずに見守る力が強まります。
「焦ってしまうのは自然」と自覚しつつ、その感情を“昇華”できる親の姿勢が、子どもにとっての安心な土台となっていくのです。
「勉強した方がいいのかな」への親の対応につまづきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ共育塾)が見聞きした、「勉強した方がいいのかな」に対する親の対応につまづきがあったエピソードを紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
1:ちょっとの思いに、親が過剰に反応した
中学2年の陽菜(ひな)さんが、「そろそろ勉強しないとやばいかも」とつぶやいたのは、ある夏の昼下がりでした。