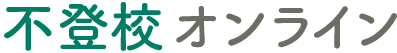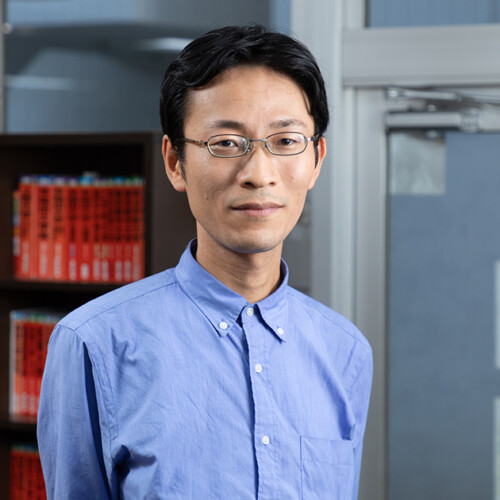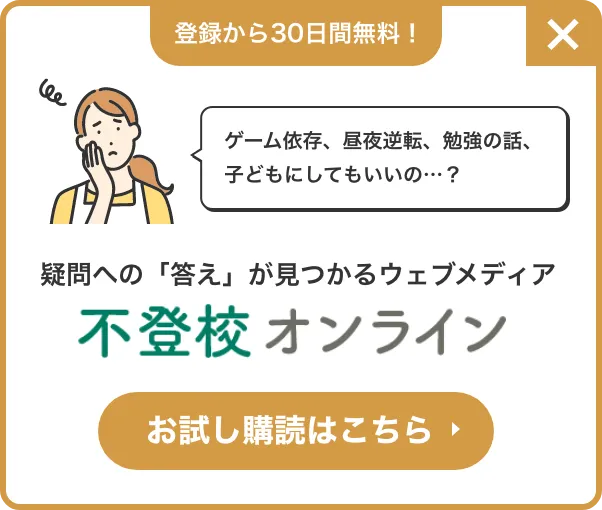「行きたい、でも行けない」苦しんだ中学生が学校へ行けた2つのきっかけ
「朝起きること、制服を着ること、朝ごはんを食べること、家を出ること。それらすべてがとても苦しかったんです」と語るのは、中学1年で不登校をしていた山邊優香さん(23歳)。人と話すのが好きで元気に見られることが多く、友人や先生からは「明るい不登校」と言われていました。ですが、当時はとても苦しく、毎日生きていくのに必死だったといいます。当時の心境と、いま振り返って思うことを聞きました。(聞き手・編集/藤森優香、撮影/矢部朱希子)
* * *
はじめにお伝えしたいのですが、私はこのインタビューによって、いま不登校に悩む人に何かを伝えたいというわけではないんです。さまざまな状況の人がいるなかで、「こうしたほうがいい」という正解はないと思っています。不登校を経験した私が今インタビューを受けている姿を見て、すこしでも何かの希望になればいいな、私の経験を読むことで、何か心にひっかかるものがあればいいなという思いで、インタビューを受けています。
不登校の経緯からお話しますね。中学1年のときに学級委員を務めていたのですが、生徒と担任の先生との対立が多く、ひんぱんに授業の時間が「話し合い」に変わり、その度に学級委員である私が司会をしていました。
学級委員として状況を改善したかったのですが、どうすれば解決するのか、そもそも自分たちはどこに向かえばいいのかよくわからず、話し合いの毎日に疲れていきました。私は生徒と先生、どちらか一方ではなく、双方の味方としてやっていきたかったんです。しかし中学生ということもあり、「先生、なんかイヤだよね」という声にクラスメートがどんどん同調し、結託していくようすが恐ろしかったです。
はじめは、「ちょっとしんどいから1日だけ休もう」と学校を休みました。それが翌日も、1週間、2週間と延びていき、気づいたら数カ月休んでいました。
昼夜逆転の生活に
学校へ行かないと体力を使わないせいか夜早く眠ることができず、毎日明け方に寝て、次の日の昼すぎに起きる、という昼夜逆転の生活になりました。
次第に心身の不調が生じてきました。幻聴が聞こえたり、家のなかにいてもずっと監視されている感覚があり、それが不眠にもつながり、ますます朝起きることができずに学校へ行くのが難しくなりました。
学校ではいじめられていたわけではなく、先生も友人たちもいい人が多かったので、なんとか行きたいという気持ちはあったんです。でも、学校へ行くためにはいくつものハードルを乗り越えなければなりませんでした。
がんばって早起きできたとしても、そこから制服に腕を通すのがとてもしんどかったです。制服を着るということは、その行為の先には「学校へ行くこと」がありますよね。戦場へ行くために軍服に腕を通すような気持ちで、震える手でボタンを留めていました。
制服を着る、髪を整える、朝ごはんを食べる、家のドアノブに手をかける、という行為のひとつひとつがすごくたいへんで、家を出るまでの過程のどこかであきらめてしまう日もたくさんありました。
なんとか家のドアをひねって外へ出て、「もう行くしかない」と泣きながら駅までたどり着いたとしても、電車に乗る前にパニックになり、立てなくなってしまって結局駅まで親に迎えに来てもらう日もありました。中学1年生の6月から学校へ行かなくなり、それから3年生の夏ごろまでの2年間、こんなふうにすごしていました。学校へ行きたい。それなのに体が言うことをきかない。本当につらい毎日でした。

山邊優香さん
親もどうしていいかわからない
両親は無理に学校へ行かせようとはせず、支えてくれました。でも、私とどう接していいか、不登校の娘をどう受け入れればいいのか混乱しているようでした。