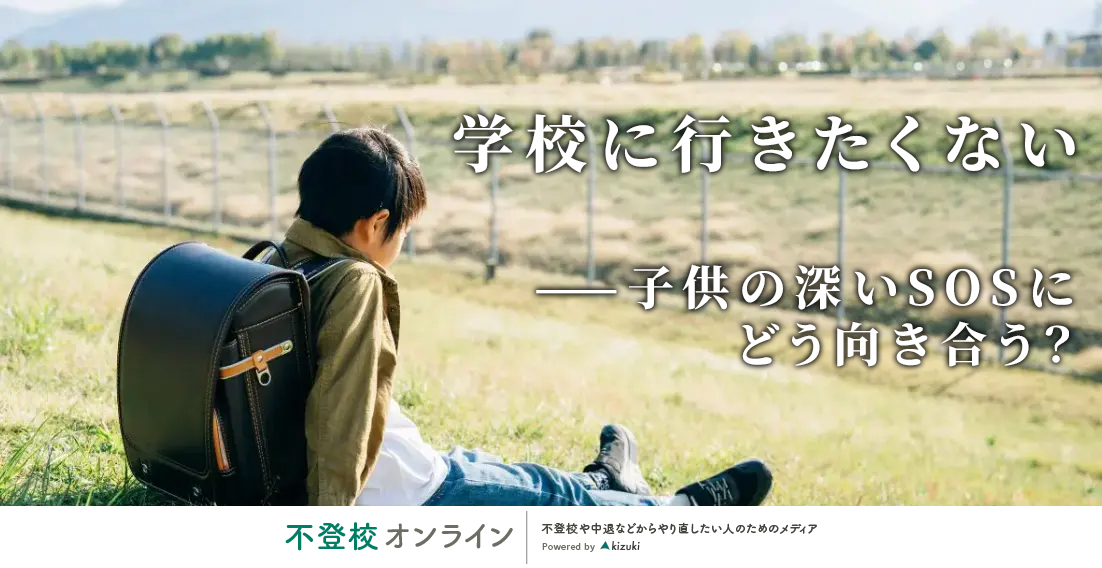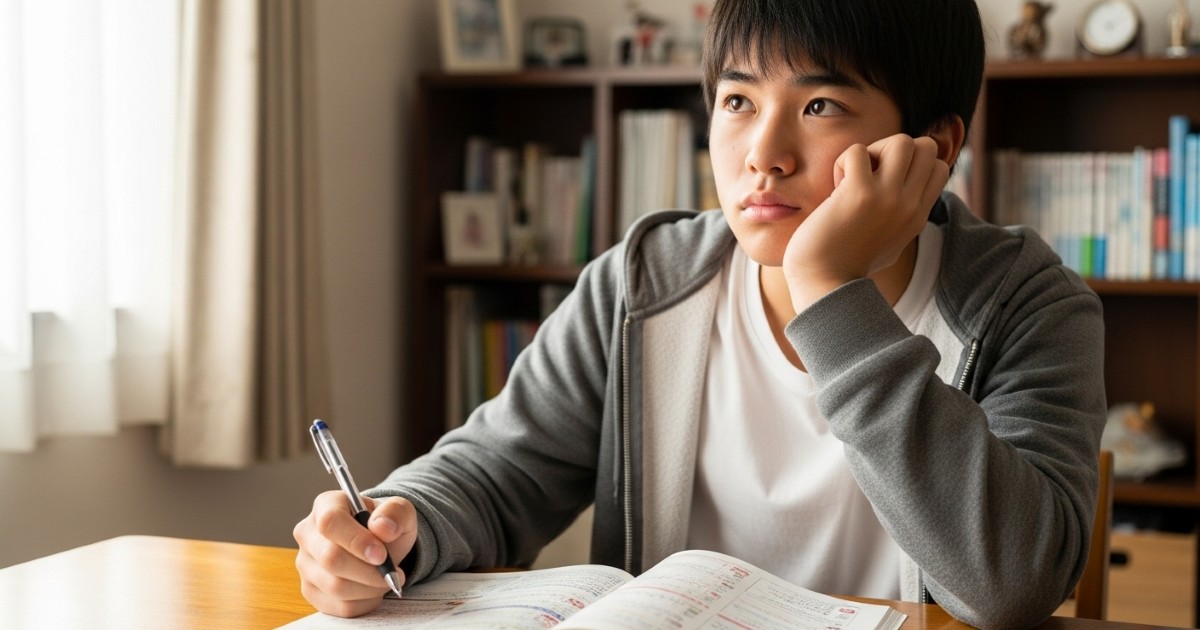【調査報道】子どもの「学校行きたくない」発言アンケート結果(4):やってよかった対応の、詳細を教えてください
ウェブメディア不登校オンラインでは、「子どもの『学校に行きたくない』という声」と「その後の状況」「親の対応」について、リアルなお声をお聞きするアンケートを実施し、102名から回答をいただきました(アンケート結果の総合的な紹介・分析記事はこちら)。
本記事では、その中でも特に「(子どもが『学校に行きたくない』と言った後の、)やってよかった対応の、詳細を教えてください」という設問に寄せられた声を紹介します(複数の声を一つにまとめたものもあります。また、漢字かなづかいや句読点などは、不登校オンライン編集部が編集した部分があります)。
正解のない子育ての中で、今できる最善を探し、親子で希望の光を見つけるための参考にしてください。
1.やってよかった対応の、詳細を教えてください
教育センターに相談した。
スクールカウンセラーに相談した。
子どもの思いを受け止めようとしたこと。
話をよく聞き、何ができそうか探ること。
フリースクールに通ってお友達ができた。
フリースクールなど居場所探し。塾に行かせた。
不登校の知識が入った。配偶者とじっくり話せた。
子どもが楽しめること、一緒に楽しめることを探してやった。
ママ友に打ち明けたときが、いちばん気持ちが落ち着いた。独りではないと思えた。
担任や養護教諭など、学校と夫婦で面談の機会を持ち現状を共有できたことはよかったです。
下痢が続き内科的には問題ないとわかり心療内科を受診。病名と服薬治療で本人が落ちついた。
小学校から中学校まで不登校だったので、校長先生に事情を説明して、フリースクールに通っていた。
中学校のスクールカウンセラーにまず連絡した。そしてカウンセリングルームを近所に探しそこにかかるようにした。
区が主催している不登校の子どもを対象とした居場所を提供してくれているところがあり、そこに通うようになった。
「学校に行っても行かなくても、あなたはあなた。あなたが幸せに楽しく過ごしてほしい」と、常々伝えていました。
泣きながら「行きたくない」と言われ、夫に相談し少し休ませたことで子どもの気持ちが少し落ち着いたような気がした。
先輩ママの子どもが不登校を経験していて、とても勉強されていたので、具体的な考え方を教えてもらえて、とても助かった。
スクールカウンセラーさんと話して、親がやるべき行動を聞けたことで行動指針ができて、これでいいのかな?の迷いが減った。
学校の担任の先生へ、登校催促の刺激となる様な電話や自宅訪問は遠慮いただいたことで、子どもも保護者も非常に気持ちが楽になった。
行かなくていいと伝えたことで、子どもが安心したのがわかった。子どもが話してくれるようになり、状況について話を聞きやすくなった。
校長先生に相談した。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーにつなげてもらえた。学校の管理職に相談すると理解されやすい。
よく寝て休めば一日で回復するくらいに考えていた為、一日くらいは親も余裕の気持ちで休ませていた。もっとじっくり休ませてよかったのかも。
話を聞くことで、子どもの性格傾向を知り、学習への取り組み方を聞いたり学校の様子を聞いたりすることで、何がつらいかを想像することはできた。
以前から精神状態が不安定なことがわかっていたので、休ませるという選択肢しかなかった。無理に行かせてたら、子どもは壊れてしまっていたと思う。
子どもの学校での状況を教えてもらった。担任よりも教頭や学年主任に学校側の対応の話を聞くことで親の気持ちに寄り添ってくれていると感じられた。
田舎なので、専門機関への相談もなかなか難しい。それぞれで対応も違ってくるので、担任やコーディネーターの先生と相談しながらその子に応じた対応を考えてきた。
不登校について、あらかじめネットやYoutubeで勉強していたので、いざ不登校になったとき、すぐに休ませることができた。相談先すぐに相談することができた。
腹痛、吐き気などがおさまらず、身体的に限界な状態だったので、信頼できる小児科の先生の所に早めに連れて行き、体が大変なときは休ませていいことを言ってもらえた。
いろいろ言ってしまったが、説得させようとすることに意味はなかったなと後から思う。何もしないことがよかったかどうかはわからないが、他に何かできたことはなかった。
母親の私のほうから、「学校は無理して体や心を壊してまで行くところじゃないんだよ」と、子どもが「行きたくない」と言い出すだいぶ前から、言いやすい環境を作ったこと。
フリースクールで勉強以外の体験をすることができた(畑で野菜を収穫したり、調理したり、美術館に行ったり、プールに行ったり)。
娘とじっくり向き合ったこと。対話。
市の教育相談の先生に毎月相談しに行っていたこと、不登校の専門のコーチに、不登校のお子さんの関わり方、接し方、様々なことを学んだこと、個別で親自身のカウンセリングを受けたこと。
不登校専門の心理カウンセラーに相談したところ、対応方法のアドバイスや、フリースクールの紹介をしてもらった。また、他の家族や学校にも理解してもらうよう連絡の連携をとってもらった。
2月末から不登校になり、東日本大震災のこと、自分達も被災しライフラインが途絶え苦労したこと、親族が生死の境を彷徨ったこと、生きるということは思い通りにならない苦難もあることを伝えた。
受験塾の先生のアドバイスをもらった。
学校の担任にいじめの実態を報告した。
よく寝かせて休ませた。
推し活などは継続した、美味しい物を食べに行ったりした。
夜寝るときに、息子の学校での不満や不満をとにかく聴いた。中2になった今でも、不安なことがあると話にきてくれる。
市の不登校の相談機関と繋がったおかげで、私の心が少し軽くなった。
この機会にと思い、発達障害の可能性をさぐりたく、児童精神科に行ったこと。その後の道も開けた。
キズキに出会えたことも本当によかった。現在、自由な私立小学校で元気に登校しています。
やってよかったかはわからないが、学校に行かせようとしていると本人も自分もつらくなるので「無理に行かなくてもいい」と言って本人は少し安心できたのかと思った。自分や主人は不安ばかりでまだ安心とは、言えない
ゆっくり休ませて一緒に遊んだりおしゃべりをした。落ち着いてからは旅行に行ったりした。
登校刺激はしない。学校関連のものを目につかないように片づけた(ランドセル・教科書・ドリル・時間割など)。
担任に相談し、家まで迎えに来てもらう案をもらい子どもに話したところ「それなら行けそう」と言っていたので対応してもらった。
賛否ある対応だと思うけど、うちの子にはそれで救われたこともあったと思う。
何がどう困っていて、どんな助けがあれば行けそうなのかを聴きました。
学校にはどんな対応をしてもらえそうなのかを聞きました。
席替えの配慮をしてもらって、行けるようになったことが何回かありました。
休みたいだけ休んでもらい、好きなことをさせてあげて家族で楽しめる趣味を探したり、地方へ出掛けたり、学校のことは少しずつサポートして子どもの気持ちに寄り添いました。
どんな話しも傾聴し、否定せず対応しました。
町内のことばの教室へ相談に行き、私の話を聴いてもらった。担当職員から「お母さん大変だったね。学校へ通うことは少し置いといて、今はゆっくり休ませてみたらどうかな」と言われ肩の荷が降りて安心でき、子どもへも優しい対応ができるようになった。
友人のお子さんも不登校だったことがあり、そのときにいろいろ話を聞いていた経験があったため、無理に学校に行かせるようにしなかったり、親がジタバタしない方がいい、ということの知識があったため、心配はあったものの、比較的冷静に対応できたのではないかと思います。
不登校に関する知識を全く有していなかったため、書籍を中心に不登校に関する情報を収集しました。様々な視点から親としての考え方やHOW TOを得られましたが、その中でも「学校に行かない選択肢もある」「学校に行かなくても大丈夫」と徐々に思えるようになったことは非常に大きかったです。
担任の先生、スクールカウンセラーの先生と親(私)でこまめにコミュニケーションを取るようにした。
その結果、通常授業には参加せず、放課後に担任に会うだけ、もしくは週1回(1コマ)取り出し授業に参加するだけの日を作ってもらい、学校と子ども本人が無理なく繋がっていられる様に対応してもらえることになった。
小学校の頃から発達障害由来と思われる本人の言動に悩まされ、スクールカウンセラーに相談したり、児童精神科にかかったり、自分なりにいろいろ調べたりしていたので、いずれ「学校に行きたくない」と言い出すだろうな…と思っていた。「行きたくない」=本人からのSOS、と捉えていたので、無理に行かせることを考えなかったのは、よかったと思っている。
本人の話を聞くように努めたことは、その後の親子関係にもよい影響を与えたと思います。
五月雨登校や完全な不登校になってからも、本人が自分の気持ちを言語化していろいろと話してくれたため、基本的な信頼関係は崩れなかった気がします。
外部に相談したり支援者を得ることは、親が孤立しないため、また子どもを責めないために、とても大事だと思います。
最初から話をじっくり聞けたわけではなかった。支援センターやその他、知見のある人に相談し、学校は休ませた。子どもが興味を持つ好きなことを探し、行きたいと思える習い事をやらせてみて、学校以外の夢中になれることを応援して一緒に楽しむようにした。またPTA役員をやって、先生方との接点は絶やさないようにし、不登校の親であっても卑屈にならず堂々と保護者会などにも参加するようにした。
大幅な体重減少と無気力が出現したため小児科に相談して内科的な検査をした後に小児精神科に相談し、小児鬱との診断をいただいたので学校にも連絡し、登校させないことを連絡。無理をしない範囲でのんびりと過ごさせるとともに、学習意欲はあったので課題などをいただいたり楽しそうな行事には参加したりサポートをお願いしました。医師に常に相談しながら対応することで家族も本人も楽になれた気がします。
クラス替え時の恒例行事で、正直「またか」との気持ちもありましたが、まずは本人の話を聞くようにしました。その上で「どう思う?」と質問されたら「ママの考えだけど」としてアドバイスする、「世界は広く道はいくらでもあるから大丈夫」と伝え、「どうしても無理なら転学やフリースクールなどもある」と説明。「どうしてもしんどいなら休んでいい」と伝えた上で、実際に登校するか休むかは本人に任せていました。
初めは腹痛が治ったら行くかと思っていましたが、なかなか治らず、受診するのも大変で親子で疲弊してました。五月雨登校でなんとか行ってましたが、5年の夏休み明けからまた行けなくなりました。これは学校に行くのがストレスなんだなとそこで気がついて、「もう行かなくていい、家でゆっくりして、行きたくなったら行こうよ」と言ったときに、「ホッとした」と言われました。もっと早く休ませておけばよかったと思います。家を快適にしてエネルギー溜まったら少しずつ動き出してます。
出社する日の朝になると特に行き渋る様子を見せるようになり、母子分離不安だなと直感しました。近くに住んでいる祖父母からは「親は働いているんだから甘やかしたらいけない、親が休ませるからいけない、一生学校に行けなくなるよ」と強く言われていたので、それも違うなと感じていました。
学校に行きたくない理由を本人に聞いても「わからないけど行けない、仕事に行かないで」と泣くので、職場や学校にとりあえずの連絡を入れてから、玄関で1時間以上気持ちが落ち着くのを待つこともありました。
今日は無理だなというときは欠席させて、「行きたくないけど、行かなくちゃ」と葛藤しているときは、気持ちが切り替わるのを待って、遅刻して登校させていた。
泣いている状態で登校させることは、絶対にしなかった。
小学生のときは長休みに、中学生になってからも休み時間に合わせて登校し、ざわざわした時間に教室に入れるようにしている。
担任と本人の関係はありがたいことにどの先生とも良好だったので、児童玄関まで連れて行けば、担任に引き渡してすっと学校の中に入り、教室で過ごせた。
もともと、感情や困り事を言葉で表すことが課題の子で、さらに、学校は熱がなければ行くべきもの、という本人のこだわりがありました。
しかし、疲労やストレスが溜まると最悪、他害や自傷のリスクのある子とわかっているので、常に、学校での様子を先生に伺い、いつ休んでも当然、というスタンスで見守っていました。
中1の9月は、初めて本人がはっきりとSOSを出したので、迷わず休ませ、一日すると、疲労がとれて、また通うことができました。行事のたびに疲れが溜まるので、そのとき以降「たまには休んだらいいよー」と伝えています。
不登校について知識がなく、まずは担任の先生に相談しましたが特に改善されることなく不登校が続きました。当時ピアノ教室に通っており、民間の児童相談にのってくれる施設を知り、月に2回ほど相談に行くようになりました。その後、自治体の教育研究所を教えてもらいそちらにも相談して、早めにメンタルクリニックの相談予約をとのことで予約をしたり、中学に入る前に教育研究所の方が一緒に中学校に行ってくれて入学してからもし行けなくなった場合の相談室、アプローチルーム等の利用などもできることなどを一緒に聞いてくれました。
不登校について何もわからないまま、マニュアルもない状態で始まることなので親としてとても悩みました。
そんなときにいろいろな助けてくれる場所(民間の相談施設、教育研究所、メンタルクリニック)があったことですくわれました。
最初に入学前に「絶対に学校行きたくない」と言われたときは、元々不登校になる子だとは思ったのでしょうがないかと思いつつ、何も経験しないまま学校行かなくていいよというのは、本人が後で後悔するかもしれないと思ったので少し経験したうえで、不登校になるならやればいいと思ってました。なのでこのときは不登校支援のプロの知人の教員や、校長、担任などに相談しかなり相当手厚いサポートをしてもらったおかげで半年間学校に通うことができて、一般的な運動会と音楽会も一応経験できたのはよかったかなとおもってます。
初めから「学校は絶対に行かないといけないところではない」ということはずっと話していました。
そうはいっても、本人なりに行かなきゃという気持ち、他に行くところもないし、というのがあったので、日々どうするかは学校の予定や学校行かなかった場合に行ける場所などを提示して、どうするかは自分で決めてもらっていました。自分で決めることが大事だと思っていました。
この頃はとても暗くて不安が大きくてつらかったです。
早めに放課後デイやフリースクールにつなげたことで、「こっちのほうがいい」という実感が持てたこと、不登校になったときスムーズにフリースクールに移行できたことはよかったなと思ってます。
回答者ペンネーム(敬称略、本名と思われるものは編集部で変更済み):banboo、Cardamon、hirohiro、JJ、JKの母、mimi、phonkichi、snow、Twinsmama、wamoa、あけりょ、いっとかな、えむママ、おはぎ、お母ちゃん、かぼちゃ、ごくらく、ことり、こむぎ、さくら、さこちん、ささ、じょーちち、しんのすけ、たま、なな、にんにん、のり、のん、ばけりん、はなまる、はぴもぐ、はやめ、ハンバーグ、まぁ、マツア、マミ田マミエ、まる、ミ。、みかん、みんと、ムギ、モナ、もも、りと、りょうこ、るこ、レモン、レモン、ロータス、一休さん、HH、銀の翼、TM、山田太郎、初めての経験で親も戸惑っています、迷える母さん、踊るママ、蓮
2.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント
「やってよかった対応」として、第三者の意見を聞いたり、民間機関に頼ったりしたことをあげてくださった方が多くいらっしゃいました。
客観的に、冷静に事実を受け止めて伴走してくれる第三者の存在は本当に大切です。
10年前、高校生のときに私が不登校を経験したときのお話を共有します。
私の父は救急医療関係の仕事に就いており、人の生死を含む緊急事態に常に向き合ってきた人です。
そのため、とても落ち着いた性格で、あまり動じる様子は26年間一緒に過ごしてほとんど見たことがありません。
そんな父が、私が不登校になったときにはとても動揺していたと後から聞きました。
父曰く、「家族のことになると感情がどうしても動いて冷静さを欠いた行動をとってしまう」ということでした。
そんな父も、私を不登校のお子さんが集まる塾に繋げてからは安心することができたそうです。
家族って、大切であるが故に難しいときもあるんだなあと学んだエピソードです。
本調査の他の記事でもコメントさせていただいたことと重複してしまいますが、大切なことなので何度も言います。
保護者さまも一人で抱え込む必要はございません。
私たちキズキをはじめ、さまざまな相談先があります。
どうか、気軽に頼っていただけたらと思います。
3.関連記事のご紹介
今回のアンケートに関連する記事は、下記からご覧いただけます。
関連記事