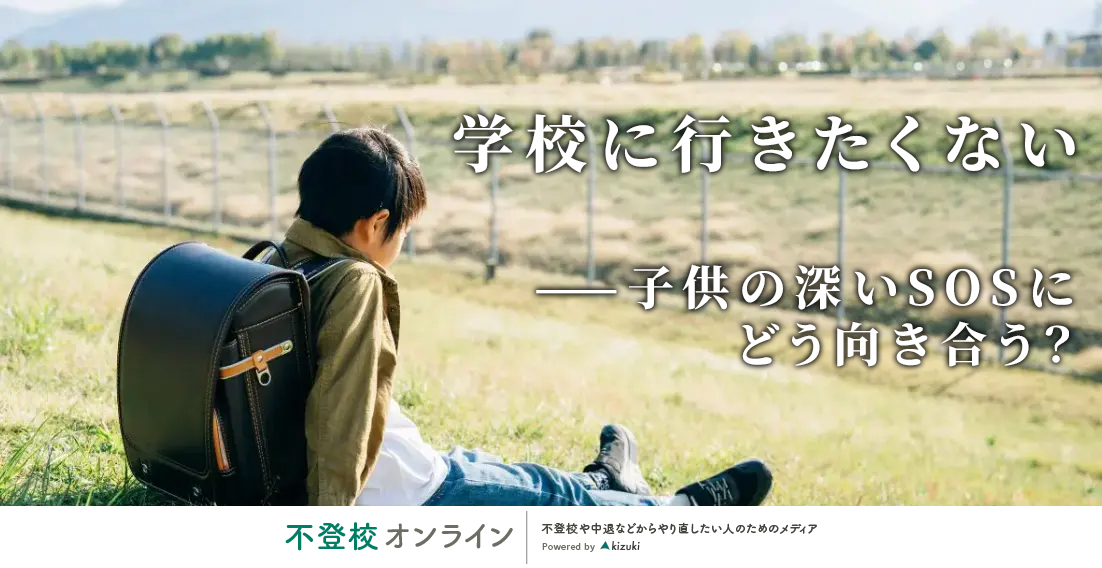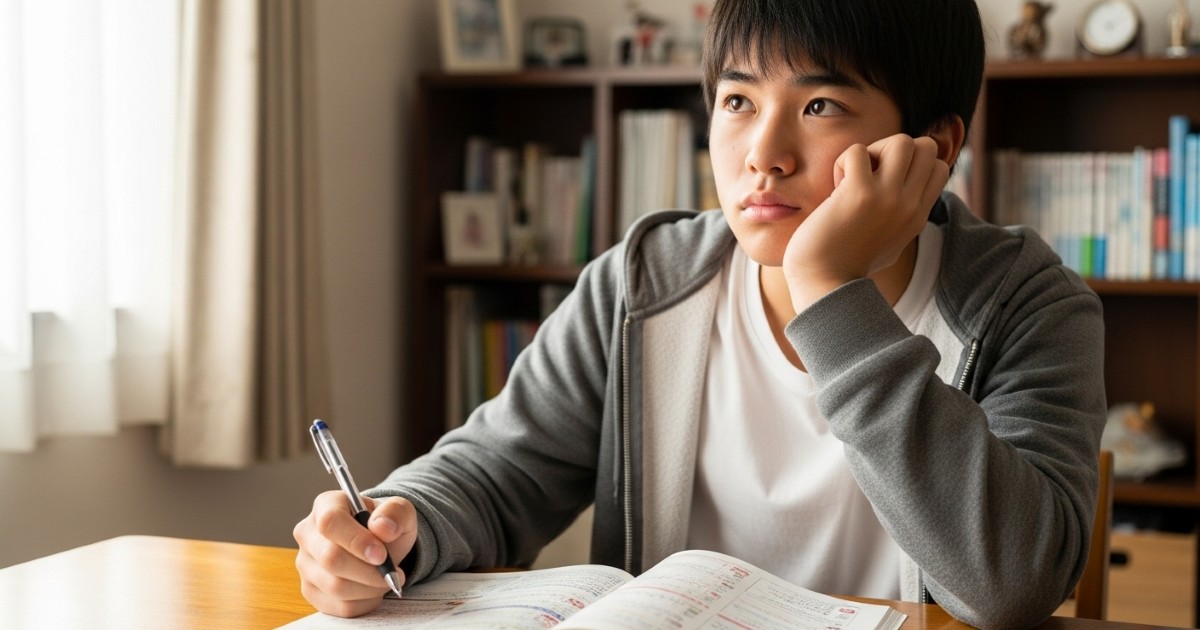
【調査報道】子どもの「学校行きたくない」発言アンケート結果(5):しない方がよかった対応の、詳細を教えてください
ウェブメディア不登校オンラインでは、「子どもの『学校に行きたくない』という声」と「その後の状況」「親の対応」について、リアルなお声をお聞きするアンケートを実施し、102名から回答をいただきました(アンケート結果の総合的な紹介・分析記事はこちら)。
本記事では、その中でも特に「(子どもが「学校に行きたくない」と言った後の、)しない方がよかった対応の、詳細を教えてください」という設問に寄せられた声の一部を紹介します(漢字かなづかいや句読点などは、不登校オンライン編集部が編集した部分があります)。
正解のない子育ての中で、今できる最善を探し、親子で希望の光を見つけるための参考にしてください。
1.しない方がよかった対応の、詳細を教えてください
(学校に相談したが、)学校、担任は何もしてくれなかった。
焦って学校に戻そうとしていたこと。
家庭内でのプリント学習を促したこと。
登校させることを第一に考えてしまった。
部屋から引きずり出したこともあり、頭ごなしに否定した。
無理に登校させようとしてもますます足が重くなるだけでした。
最初は何とかして行かせようとして、責めたり怒鳴ったりしてしまった。
脅すように行くように父親からいうことで関係が悪くなりそうになった。
背中を押すつもりや親の自分の不安を消すために行ったほうがいい、と言ったこと。
不登校の子にやってはいけないと言われていることは、ほぼ全てやったように思う。
祖父母と曽祖母が学校に行くように促していたので、子どもの話を聞いてほしかった。
不安や焦り、不満をぶつけて追い詰めた。子どものことを第一にして考えなかったこと。
期間が空くと行けなくなると思い、無理にでも玄関までなど登校させて追い詰めてしまいました。
なんとか学校に気持ちが向くように話をしたかったが、何も変わらなかった。本当に無力だと感じた。
なんとか行かせようと、付き添い登校を試みた。本人をもっと追い詰めることになってしまったと思う。
行きたくないとはいつも言わず、とにかく起きられず、寝続けていたのに、無理やり起こし続けたこと。
小学校に入学したら登校するのが当たり前との考えしか頭になく、娘の気持ちを一切考えていなかったです。
嫌だ、もう無理と言っているにも関わらず車に乗せて連れて行った。あのときの私は、精神的に未熟だった。
じっくり聞きたかったが答えないので、何度も何度もああなの?こうなの?と聞いたため、親子関係が悪化した。
本人の気持ちを考えずとりあえず学校に行かせようと必死だったが、今考えると可哀想なことをしたと後悔している。
当初は、行かせようと無理に対応していたため、部屋のすみっこで体育座りをしている娘を見て胸が締め付けられた。
行かせなければと思う親とそれを拒否して自分の気持ちを理解してくれないと籠る子ども。この状況が延々と続きました。
サボりかもしれないとか行けばなんとかなると最初は思いました。行ってみたらと言って朝起こしたりしましたが無理でした。
車で学校まで送り、先生と説得しましたが、本人の、行きたくないという気持ちが余計に強固なものとなったと感じています。
妻が自分の両親に相談したこと。暴走して学校に問い合わせしたり、自宅に突然訪問して子どもを問い詰めたりして最悪だった。
適切な対処ができないうちに無理やり登校させても、限界が来る。何よりも子どもの精神の傷が深めてしまったことを後悔している。
休みが続くと行きにくくなると思い、準備も含めて手伝いながら行かせていたときは、毎日落ち着かず本人も自分もつらかったと思う。
配偶者(夫)は、母親(私)の子育てに問題ありと思っており、学校は、登校するように促す。相談機関に通っても、質問ばかりで、改善しない。
自分の仕事が忙しかったこともあり、子どもが休むと自分も休まざるを得ないため、登校を強要するような言い方を繰り返してしまった。
子どもの前で、登校させるか、休ませるかの夫婦喧嘩をしたこと。子どもから「私、生まれてこなければよかったよね」と言われてしまった。
子どもが顔色が真っ白の能面のような状況だったので、明らかにおかしかった。そこまでおかしい状況なのに、登校させるのは、無理だと思った。
こちらが疲れていたりするとうんざりしてしまい、「いつもいつも自分が満足する環境になるとは限らない」など説教めいたことを言ってしまった。
よくないとわかっていても、玄関まで引っ張っていってしまったこと、泣いていても玄関を出てしまったこと。本当に可哀想なことをしたと思っている。
初めは、とにかく登校させて新しい環境に少しずつ慣れさせるしかないと思い、泣く子を連れて行っていた。夫も行きなさいといい、登校を強制していた。
行き渋りの時期は、朝の子どもの状態に毎日振り回されてしまうので、親の方に余裕がなくなるとついつい感情的に子どのを責めたり、脅したりしてしまった。
娘との約束で、1か月に1回だけ休んでいい日をつくった。1日休んだら、それ以降日行きたくない、と言っても「約束したよね」と言って学校に行かせていた。
学校はイジメ隠蔽ばかりで話にならぬ。フリースクールに来たり、不登校の支援センターから我が子を連れ去られ教室につれていかれたことがあり、親の許可なく誘拐。
不登校初期にいろんな選択肢を提示してしまったが、娘は考えられる状態ではなかったと思う。情報は出すタイミングがあると思うので、初めはとにかく休ませた方が無難だと思う。
後から振り返ると、学校の先生やスクールソーシャルワーカーの方は、不登校の対応をほとんど知らなかった。子どもに問題があるという視点での対処だった。登校刺激を提案された。
1時間でも学校に行った方がよいと信じていたので、同伴登校や遅刻早退の送り迎えをしていた。そんなエネルギーを使わせないで始めからゆっくり休むことを受け入れればよかったと思う。
「なぜ行きなくないのか?」の理由を聞くこと。本人もよくわからず、また理由も一つではないため、あまりそこにフォーカスし過ぎると、心を閉ざしてしまう感覚があったので、やめました。
毎日、行き渋る子どもを行かせようとして説得したり、いろいろ話しているうちにイライラして大喧嘩に。毎日同じことの繰り返しでお互いとてもつらかった。今思えば悪いことをしたと思う。
不登校の初期は登校を強要するような場面もありましたが、結果的に登校に繋がることは一切ありませんでした。子どもの視点からすると居心地の悪さしかなく、悪手であったと感じています。
日中の登校はしていないが、担任から「プリントを持って自宅へ訪問に伺います」など連絡が来た際は、放課後等に学校へ一緒に連れて行くことなどあったがそれがよかったかどうかはわからない。
最初本当の理由は知らず、朝や夜に腹痛や頭痛を訴えることが多かったので、サボりや怠けかと思ってしまった。
学校に行ってしまえば何とかなるだろうと車で連れて行ってしまうこともあった。
学校(先生)は少しでも登校できるように保健室登校や1時間だけなど提案していたので、私自身少しでも学校と繋がっていることが本人のためだと思っていたが、嫌なものを無理して行かせる必要はなかった。
私が、息子が学校の時間に家にいることにとても強い不安とストレスを感じてしまい、息子に “ねぇ、なんでいるの?すごいストレスなんだけど!”という酷い言葉を浴びせてしまった。本当に申しわけなく思っている。
高1の担任は毎日どういうところがしんどいか子どもが話してくれることを伝えていたので、いろいろ手厚く配慮してくださったのですが、その様子を学年主任は「サボっているだけのくせに」と不快に思った様で、学年主任の科目は単位を落とされました。
不登校ののち、復学→再度不登校。留年の心配も早々にあったため(本人は留年を望んでいない)、別室での中間テスト受験及び提出課題だけでもこなしていこう、と担任の先生とともに励ましたが却ってプレッシャーがかかり、その後うつ症状が出てしまったこと。
クラスには行っても行かなくてもいいから今日は校門まで行ってみようか、と誘えば足が向かうようになった頃、校門前で校長先生や教頭先生が声をかけてくださるようになり…。
行くか行かないかは本人に任せましたが「行かなくちゃ」のプレッシャーにかなり苦しんでいました。
無理に登校させることはNG対応だと言われても、不登校初期は復帰してほしい気持ちや原因を対処すれば復帰できるという思いは多くの保護者が持っていると思う。無理に登校させることがよくないと実感として気付かなければ「見守りましょう」と初期に言われても親は受け入れられずつらいです。
我が家の場合、配偶者は最後まで「学校へ通う」以外の選択肢は考えられなかったので、話し合いになりませんでした。また、学校の教員に相談しても、有効な解決策は得られませんでした。子どもから見れば「ブラック」な学校へ相談に行ったところで、子ども一人のために学校が変わるはずがなかったのです。
本人は話をしようとしなかった。何となく理由はわかっていたが、見守ればよかった。
死にたいくらい本人は行きたくなかった。
「学校は命をかけてまで行くところではない」という言葉にもっと早く出会っていればよかった。学校に行けなくても大丈夫。その後、うちの子は大学から持ち直して今は就職して正社員として働いている。
家庭学習を学校の時間割通りに取り入れてみたが、お互いだんだん疲れてきて、関係が悪化しそうだったのでやめた。
教育委員会系の相談窓口に時間を作って言ったが、さんざんヒアリングした後で何も有益な情報ももらえず、最後に「お母さんゲームは絶対だめですよ」と時代錯誤なことを言われて、がっかりした。元校長のおじいさんおばあさん、古い学校側の人に話しても不登校は解決(何をもって解決かわからない)しないと思った。
一旦休ませましたが先生が本人から詳細を聞きたいと2日目の放課後、学校に向かいました。
放課後でしたが学校に向かう道中、足取りも重くしんどいと言ってとてもつらそうでした。
私も初めての経験でどのように対処するのが正解かわからず、担任がこどもにどうしたいか尋ね、自分の口から嫌だったことを伝えるほうが効き目があるよと無理なら先生が伝えると言われ、こどもは効き目があるということで自分の口から伝えると話しました。学年主任や管理職を交えておらず、担任のみへの相談だったため後々、担任の対応に不満が募る結果になりました。
回答者ペンネーム(敬称略、本名と思われるものは編集部で変更済み):banboo、HH、hirohiro、JJ、JKの母、miku、mimi、mog、obaco、phonkichi、ri_co_pe、snow、TM、Twinsmama、wamoa、アカママ、あけりょ、ありそん、いっとかな、うさかご、うつぼ、えむママ、おはぎ、お母ちゃん、ごくらく、こむぎ、さくら、さこちん、ささ、じょーちち、だし、ちこまめ、のり、はぴもぐ、はやめ、ハンバーグ、まぁ、マツア、マミ田マミエ、まる、みかん、ムギ、モナ、もも、りと、りょうこ、るこ、レモン、ロータス、華、銀の翼、山田太郎、初めての経験で親も戸惑っています、迷える母さん
2.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント
「まずは見守ることが大切」「無理しないことが大切」——
不登校支援ではよく耳にする言葉ですし、実際にとても重要な考え方です。
けれど保護者さまとしては、「本当にこのまま、何もしなくていいの?」「放っておいても大丈夫なの?」と不安になる方も多いのではないでしょうか。
最終的に目指すのは、お子さんが長期的に自立し、自分の人生を歩んでいけるようになること。
つまり、どこかのタイミングで「成長」や「再スタート」が必要になるのも事実です。
そのためには、”辛すぎ”でもなく、”ラクすぎ”でもない、“ちょうどよい中間ゾーン”を一緒に探っていくことが大切です。
今回のアンケートでは「無理に〇〇させなければよかった」と声を寄せてくださった方が多くいらっしゃいました。
きっと、「ちょっと“辛すぎる方向”に寄せてしまったかも」という思いがあったのだと拝察します。
この“ちょうどよい中間ゾーン”を見つけるのは簡単ではありません。
うまくいかなかった経験もひとつのデータとなって次のサポートにつながります。
そのため、どんな後悔も無駄ではないことを、コメントとしてお伝えできればと思います。
3.関連記事のご紹介
今回のアンケートに関連する記事は、下記からご覧いただけます。
関連記事