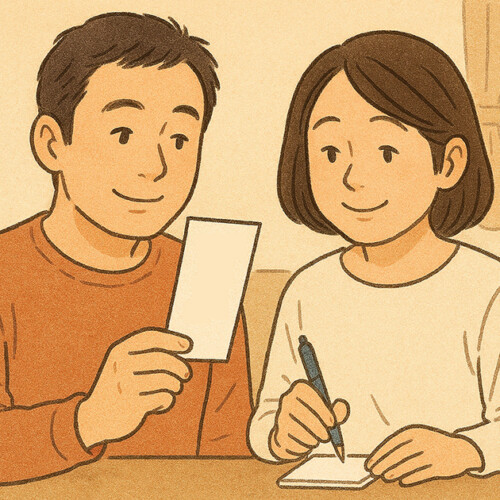自民党総裁選、候補者の不登校対策は?高市早苗氏・小泉進次郎氏の回答を紹介!【独自アンケート】
2025年10月4日に投開票が行われる自由民主党総裁選。投票資格は自民党所属の国会議員と自民党員などにかぎられますが、総裁が「次の首相」になるため、私たちの生活に非常に重要な選挙だと言えます。ですが、総裁選の報道と言えば「誰が選挙に強いのか」「どの野党と組むのか」といった政局に集中しがち。でも、私たちが本当に問いたいのは、いま自分が直面している課題、つまり不登校の現状を誰がどう変えてくれるか、ということでしょう。
そこで今回、キズキ共育塾、好きでつながるコミュニティBranch、そして私(石井しこう)の三者が協働しあって総裁選候補5名に不登校政策に関するアンケートを実施しました。回答いただいたのは小泉進次郎氏と高市早苗氏の2名、残る3名(小林鷹之氏、林芳正氏、茂木敏充氏)は「検討中」で未回答でした。未回答も重要な判断材料になると思い、未回答の方も含め、ありのままをみなさんにお伝えします。
さて、総裁選の有力候補とみられる小泉進次郎氏と高市早苗氏の回答は、共通点もありながら「差」も見られる回答となりました。なるべくわかりやすく共通点とちがいをお伝えしたいと思います。
目次
共通点――前提認識と方向性は重なる
両者の回答を比べて共通していたのは「不登校への認識」と「支援の方向性」でした。不登校は多様な要因が重なり起こるという認識と、学校内外の学び場や相談先を広げて子どもを確実に支援へつなげていくという方向性は一致していました。その具体的な支援先として両者が挙げたのは、校内外の教育支援センターや学びの多様化学校(旧不登校特例校)などでした。
不登校は個人の責任で支援しないというのではなく、「不登校への支援拡充を」というのが前提であると考えていいのです。
相違点①――見えた違いは最優先施策の「起点」
一方で相違として言えるのは「起点」でした。小泉氏が不登校施策として最優先で取り組むべきは「多様な学びの場の拡充」だと指摘。多様な選択肢を速く・広く整えることで、より多くの子どもの実態を早く変えたい狙いがうかがえました。小泉氏は「選択肢」を起点に考えたようです。
対する高市氏が不登校の最優先施策として挙げたのは「個々のニーズに応じた受け皿の整備」です。高市氏は回答で何度も「個々のニーズ」というキーワードを使用し、個々の実態に即した支援を広げていく考えを示しました。
両者の方向性は同じであるものの、ちがいを強いて挙げればスピードや広がりを意識する小泉氏と、支援の厚みを意識する高市氏でちがいがみられる結果となりました。
相違点②――親の離職・就労をどう支えるか
不登校は子どもだけの問題でなく、保護者にも大きな負担がかかります。子どもの不登校をきっかけに保護者が退職・休職・大幅な勤務調整を迫られる現象は「不登校離職」とも呼ばれ、5人に1人が不登校離職を余儀なくされたという調査もあります(不登校の保護者5人に1人が離職、学校から情報もらえず困惑)。
こうした不登校離職にはどのように対応するのでしょうか。
小泉氏は、実態調査を前提にデイサービスや学習・居場所サービスなど、家庭への直接的な支援と優先順位づけを検討する考えを示しました。一方で高市氏は雇用主側の対応が鍵だと主張。フレックス勤務やテレワークなど企業の柔軟な就労を促すため、企業を財政的にバックアップする方策を示しました。
両者ともに課題解決の意欲は示されましたが、家庭支援(小泉氏)と企業支援(高市氏)という入口に差が見られました。
通信制の「小中学校」をどう考えるか
今回は「通信制の小中学校」についても見解を求めています。なぜ「通信制の小中学校」なのか、すこしだけ説明させてください。現在中学校と高校では不登校の割合は大きく異なります(中学の不登校率6.71%/高校の不登校率2.4%)。単純比較はできませんが、背景として挙げられるのが通信制高校の存在です。年間6日の登校から週5日の登校まで登校頻度を選択できる通信制高校も多く、その柔軟さによって中学時代に不登校でも、高校に入ってからは通える生徒も多くいるのです。
通信制高校によって不登校が大きく減る現状を踏まえて「通信制の小中学校を開設するべきでは」という専門家もいます。
通信制の整備について両者に伺ったところ、高市氏は「対面での交流を通じて、全人格的な教育を行うこと」が義務教育段階では求められるとし、「通信制はなじまない」と回答しました。一方の小泉氏も「社会的な議論が必要」と慎重な姿勢を見せ、通信制以外の選択肢拡大によって現状を前に進める考えでした。
ややちがいは見えたものの、通信制小中学校には消極的な姿勢は一致したようです。
起点と親支援の入口にちがい
両者の回答をあらためて見返すと共通点は明確でした。前提となる不登校への認識と支援の方向性です。これらは政府や自民党が示してきた不登校対策とも重なるので、当然と言えば当然でしょう。一方で、特色として両者のちがいがみられたのは、最優先課題に向かう「起点」。小泉氏は「多様な学び」をキーワードに、選択肢そのものを広く速く整えることで、より多くの子どもの実態を早く変えるアプローチを意識していました。高市氏は「個々のニーズ」を基点に、受け皿と支援の厚みを高める発想を強調しています。どちらが不登校の現実に有効なのか。読者のみなさんはどう考えられますか。
最後に両氏の回答全文を掲載します。最後までどうぞ、読み進めていただければ幸いです。
回答本文(到着順)
高市早苗氏の回答

高市早苗氏(高市早苗事務所提供)
①不登校施策における最優先施策は?
不登校施策における最優先で実行する施策はなんでしょうか? 200文字程度以内でお答えください。
不登校の前触れとなる小さなサインを把握して早期発見・対処する、学校の風土を「見える化」して改善に繋げるなど、多様な対策を講じる必要があると思うが、強いて言えば、不登校の原因が多様であることを踏まえると、個々のニーズに応じた受け皿を整備することが大事だと思います。
②最優先で行った不登校施策、 1年後に測定できる指標は?
上記で回答した施策について1年後に測定できる指標をお答えください。(例:最優先課題は居場所の整備、各自治体に1件の設置を目指すなど)。200文字程度以内でお答えください。
個々のニーズに応じた受け皿としては、校内教育支援センターや、学びの多様化学校の設置が考えられます。これらの設置数や、これらの施設が実際に対象とした 児童の 不登校児童に対するカバー率が指標となるものと考えます。
③不登校離職への対策は?
子どもの不登校により保護者が離職や休職を余儀なくされるケースも少なくありません。不本意な離職などを減らすため、国として対策を講じるお考えはありますか。ある場合、どのような方策が想定されるか、200文字程度でお答えください。
不登校児童の保護者には、フレキシブルな勤務時間を設定したり、テレワークを許容するなど、雇用主側の対応が極めて重要です。したがって、こうした取り組みをする企業を財政的にバックアップするなどの対策が必要だと思います。
④通信制の小中学校の制度創設は?
中学生と高校生の不登校の割合は大きく異なっており(中学生6.71%/高校生2.4%)、単純比較はできませんが、背景には多様な学び方ができる通信制高校の存在が大きいと指摘されています。不登校や病気など多様な子どもたちのニーズに応えるため、通信制の小中学校を設立できるよう、国が制度や環境を整備する必要があるとお考えでしょうか。それとも、通信制という仕組みは小中学校にはそぐわないとお考えでしょうか。いずれかの立場を明記し、その理由を200字程度でお答えください。
義務教育である通信制の小中学校については、教師との対面での授業・ 指導、クラスメイトなどとの対面での交流を通じて、全人格的な教育を行うことが重要だと思います。したがって、通信制は馴染まないと考えますが、他方で、その分、 上述の個々のニーズに応じた受け皿作りが重要だと思います。
小泉進次郎氏の回答

小泉進次郎氏(小泉進次郎事務所提供)
①不登校施策における最優先施策は?
不登校施策における最優先で実行する施策はなんでしょうか?200文字程度以内でお答えください。
多様な学びの場の拡充を最優先で実行すべき。具体的には、政府の施策である「不登校対策COCOLOプラン」に含まれる、「学びの多様化学校(不登校特例校)」の設置、校内教育支援センターの拡充、教育支援センターの機能強化等により、不登校になっても学びが途切れないような施策を最優先で実行することが必要と考えます。
②最優先で行った不登校施策、 1年後に測定できる指標は?
上記で回答した施策について1年後に測定できる指標をお答えください。(例:最優先課題は居場所の整備、各自治体に1件の設置を目指すなど)。200文字程度以内でお答えください。
例えば、学びの多様化学校の設置数、校内教育支援センターの設置数・設置率、校外教育支援センターの設置数、校外教育支援センターで支援を受けた児童・生徒数など。
③不登校離職への対策は
子どもの不登校により保護者が離職や休職を余儀なくされるケースも少なくありません。不本意な離職などを減らすため、国として対策を講じるお考えはありますか。ある場合、どのような方策が想定されるか、200文字程度でお答えください。
不登校の小中学生は合計約35万人程度であり、子どもの不登校により離職や休職を余儀なくされている保護者をその5分の1から4分の1とすれば、10万人弱と推計されます。まずはその実態調査を行い、柔軟な有給休暇や企業内の相談体制の整備、学校外の学習支援拠点の拡充、有償でのデイサービスや学習・居場所サービスへの補助など、どのような施策が適当か、その優先順位等を検討することが考えられるのではないか。
④通信制の小中学校の制度創設は?
中学生と高校生の不登校の割合は大きく異なっており(中学生6.71%/高校生2.4%)、単純比較はできませんが、背景には多様な学び方ができる通信制高校の存在が大きいと指摘されています。不登校や病気など多様な子どもたちのニーズに応えるため、通信制の小中学校を設立できるよう、国が制度や環境を整備する必要があるとお考えでしょうか。それとも、通信制という仕組みは小中学校にはそぐわないとお考えでしょうか。いずれかの立場を明記し、その理由を200字程度でお答えください。
義務教育は多くの他者と学んだり、遊んだりする実体験を通して社会の一員としての基礎をはぐくむことを重視しており、高校のような通信制による学びが適切かどうかの社会的な議論が必要です。まず行うべきは、不登校の小中学生に対してメタバースを活用した授業や教育支援センターからの訪問支援などのサポートなどにより学校以外の場所であっても専門家のサポートのもとしっかりと学べる環境を整えることで、これらの成果を踏まえて多様な学びの在り方の実現を図ることが大事なのではないか。
「検討中」とし未回答の3名
小林鷹之氏、林芳正氏、茂木敏充氏
アンケート調査実施団体
- 石井しこう(不登校ジャーナリスト)
- 好きでつながるコミュニティBranch
- キズキ共育塾
クラウドファンディングを実施中
アンケートを実施した3団体は、クラウドファンディング「【子どもの命を守る】学校休んだほうがいいよチェックリスト継続のための運営資金支援」を実施中です。ぜひ寄付のご検討をいただけますと幸いです。