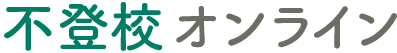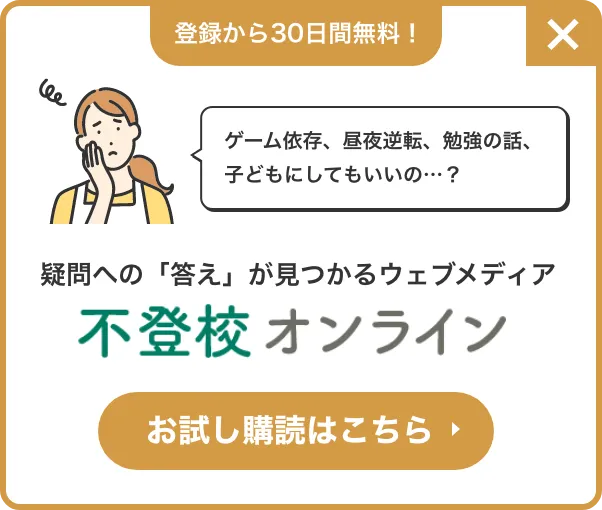「母のつくった弁当を駅のトイレで食べていた」不登校経験者が通学途中で経験した心のなかの戦い【全文公開】
通学途中、駅のトイレで母のつくった弁当を食べていた――。バスに乗って駅に向かい、学校へ行く道中の心の葛藤について、古川寛太さんが語ってくれました。
* * *
冬の通学路が苦痛だった理由。まず、バスの発車時刻が決められていること。1限開始に間に合うためには毎日定刻のバスに乗らなければならない。今日は行けるのかどうかを葛藤している早朝に、明確なリミットを外部から定められていることが、当時とてもストレスだった。これが自転車で行くともうすこし融通が利く。「授業開始時刻」に加え「発車時刻」という自分で動かすことのできない数字の発生に、俺の頭はあっという間にキャパオーバーしていた。いまでこそ、そんなことでつまずいていたのかと驚くが、やはりあのころは明らかに容量が小さくなっていた。かんたんにパンクしてしまうほど、もろかったのだ。
二重に発生する決断
もうひとつ、この通学路のいやな点は、途中で駅を経由することである。これは「学校へ行く」という決断が二重に発生することを意味する。自転車で通う際、学校へ向かうためのこの「決断」は、家を出るか否かで成されていた。意を決して家を出てしまえば、すくなくとも学校の前まではなんとか気持ちを保てる。そこから校内に入れるかでまたひと悶着あるのだが今回は省く。これがバス登校に変わるとどうか。仮に家を出ることができても、バスが到着した駅から学校へ向かうまでで、もう一度同じ決断をしなくてはならないのである。これが本当に厄介で、学校や同世代の人間という恐怖の対象が近づいてきたことで、俺は駅で再び立ち止まってしまうことがよくあった。苦い薬を2回に分けて飲むようなものだ。3年間、駅構内で1日をすごした日が何十日もある。奥のほうにある人気のない多目的トイレで、母親のつくったお弁当を食べていた。
何かのまちがいで学校へ行けてしまった日は、終業と同時にクラスの誰よりも早く校内を出た。逆に放課後に呼び出しをされた日には、クラスの誰よりも遅く校内にいた。そしていつだって家まで徒歩で帰っていた。定期券はあったが、それを使って早く家に帰ろうとは思えなかった。考えなければならないことがたくさんある。解決しなければならないことがたくさんある。気温は0度を下回り、しんしんと雪が降る夕闇のなかをゆっくり踏みしめていなければ、俺はやっていられなかった。もうすぐ進級ができなくなる、卒業ができなくなる。今積もっている雪が溶けるころには、取り返しのつかないことになる。そうして、1時間半かけ自宅に着くと1日が終わった。また何も進まないまま、雪溶け水で靴下が濡れる。冬は嫌いだ。(つづく)
(初出:不登校新聞622号(2024年3月15日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)
記事一覧