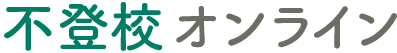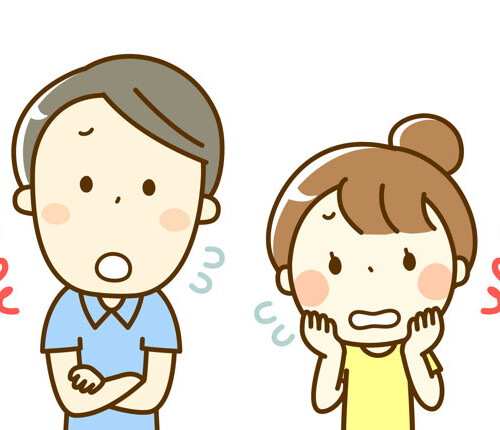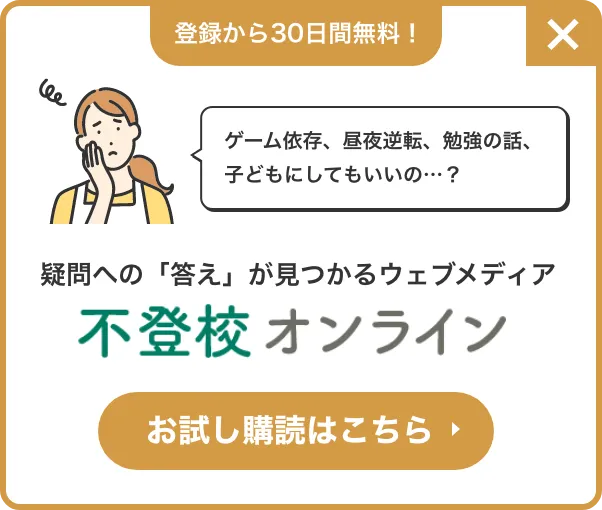親も教師もカン違いしています。子どもが学校を休み始めたら「もう限界」なんです【全文公開】
長いこと不登校の活動を続けていると、ありがたいもので、講演の依頼をいただくことがあります。
最近はとくに、学習指導要領改訂によって不登校対応も指摘されたことから、学校の校内研修などでお話する機会もあります。
学校が不登校理解を図ることのうれしさを感じながらも、「不登校」という言葉のインパクトが強く、どうしても、そこに思いが集中してしまうことに対して違和感を覚えていました。
そこで今回は、「子どものわかり方」ならぬ「不登校のわかり方」を書いてみたいと思います。
不登校について、文科省は「何らかの心理的、情緒的、身体的あるいは社会的要因・背景により、登校しないあるいはしたくともできない状況にあるために年間30日以上欠席した者のうち、病気や経済的な理由による者を除いたもの」と定義づけています。
身体症状が出る
これは、毎日毎日休む子どもや保護者の思いの積み重ねであり、休むまでには過程や背景がある、ということだと思います。
また、欠席数は「30日以上」と規定されていますが、29日目の欠席と30日目の欠席の間に断絶はありません。
それは、5月1日から新しい年号になっても、4月30日とさほど変わらない生活が待っているのと同じことです。
そんなのあたり前だと思われるかもしれませんが、「不登校」というテーマ設定になると、不思議なくらい30日に焦点が集まってしまうことが多いのです。
たとえば、病気などのあきらかな理由がなく、数日間休んだ子がいたら、保護者や先生方は、その子のようすの変化に気づくはずです。
教育委員会などが作成した資料を見ても、「不登校の前兆」として身体症状を上げています。身体症状とは「朝起きられない」「頭痛など体調不良」「理由もなく突然泣いてしまう」など。
休み始めがチャンス?
こうした身体症状を伴っていたとしても、休み始めたときは、まさか不登校になるとは周囲も本人も思えません。
こんなとき先生方は「成長のチャンス」だと捉えるケースが多いようです。つまりなんからの心理的な負担はあるけれども「これを乗り越えたら成長できる」と。
教員からその旨を教えられると、「そういうものなのか」と保護者も思うはずです。そこで教員と保護者がいっしょになって登校を促すと、じつは決定的な不信を生む種になることが少なくありません。
というのも、子どもはつらいことをできるだけ隠そうとします。それでも、身体症状が出るということは、負荷に耐えきることが困難になり、SOSを出さざるを得ない状態になっています。
休み始めたということは「不登校の初期段階」を越えて、すでに十分乗り切ろうとがんばった結果である、ということです。
「教育機会確保法」における「休養の必要性」の意義はここにあるように思います。休む必要があるのです。
どうしても学校では「学校復帰の早期対応」が求められます。でも、「誰にでも起こりうる」ことなら、そんな対応策が本当に子どものためになるのか、そもそも「問題行動」ではないのだから、もう少し慎重になってもよいのではないかと思います。
一方、不登校の未然防止もよく言われますが、それはいかに休ませないようにするのかではなく、いかにうまく休みを確保できるかということではないかと思います。
そのためには、子どもの周囲にいる人が、日々どのような関係を築いてきたのかがとても大事になります。
また、それが出会いというひとつの教育であり、その関わりやつながりが子どもにとって大切な学びになりうると思うのです。(庄司証)

(しょうじ・あかし)80年生まれ。「函館圏フリースクール すまいる」代表。不登校・高認・進学支援にとり組んでいる。元大学非常勤講師。
【連載】すまいる式 子どものわかり方記事一覧