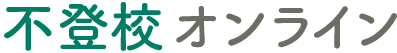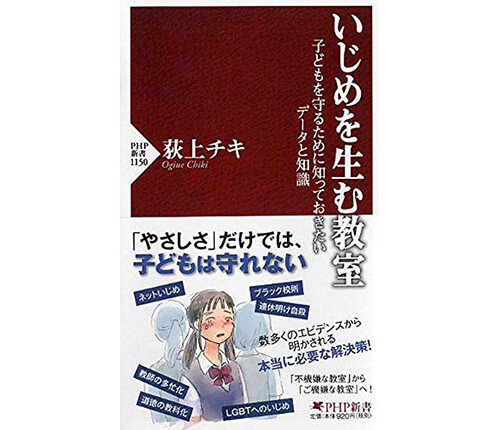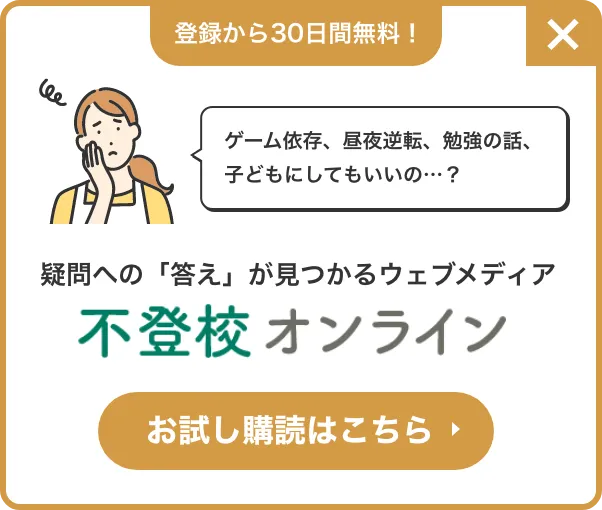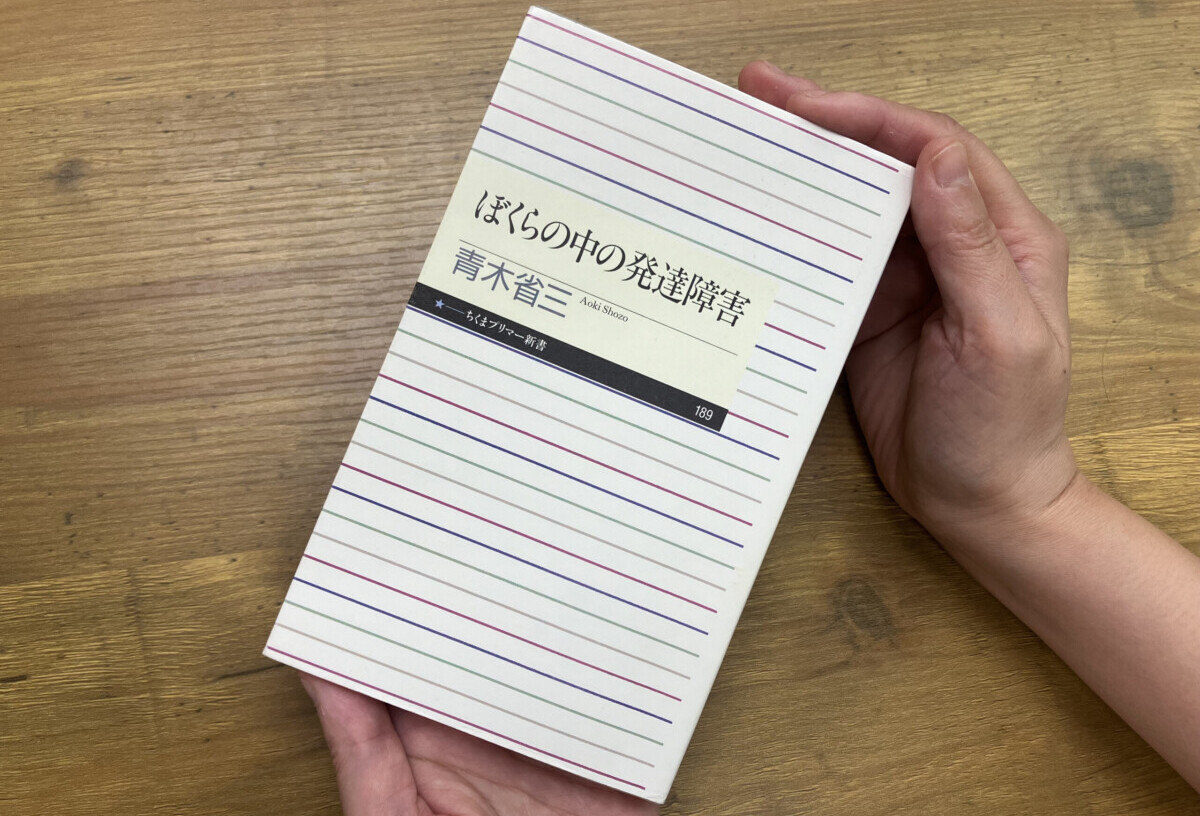
「発達障害」がわからない……そんなときは、「特性」ではなく◯◯を見て!
いくら調べてもイマイチよくわからない……。発達障害の「わかりにくさ」もまた、発達障害をめぐる困りごとのひとつ。『ぼくらの中の発達障害』(青木省三・著、ちくまプリマー新書、2012年)は、親御さんだけでなく、中学生以上の発達障害当事者にもおすすめの一冊です。「特性」とは別のアプローチで発達障害をとらえてみると、相手の「心」が見えてきます。(評者=内田青子)
内田青子(うちだ・あおこ)
1982年生まれ。上智大学文学部卒。大学卒業後、百貨店勤務などいくつかの仕事を経た後、2018年から発達障害・不登校・中退経験者などのための個別指導塾・キズキ共育塾で講師として国語(現代文・古文・漢文)と小論文を指導し、主任講師となる。並行して、聖徳大学通信教育部心理学科を卒業。現在、公認心理師の資格取得を目指して、発達障害や不登校支援についてさらに勉強中。
どれだけ発達障害のことを調べてもわが子のことを理解できない。
そう思われている親御さんは多いのではないだろうか。
また、どんなに発達障害の本を読んでも生きづらさがなくならない。
そう悩む発達障害当事者の方も少なくないと思う。
発達障害について調べてもなかなか困り感がなくならないという人は、発達障害の特性という観点から少し離れた本を読んでみるといいのかもしれない。
『ぼくらの中の発達障害』は、青年期精神医学を専門とする精神科医・青木省三氏が、発達障害に関わる教師、保護者、そして発達障害の当事者に向けて書いた書籍である。
「どんな精神症状も、誰もの心にある」と題された序章冒頭のこの見出しから始まるこの本は、発達障害の人を定型発達の人と同じひとりの人間として見つめる視点から書かれている。
“こだわり””パニック””ぎこちなさ””衝動性”を、医療の対象として解説するだけではなく、「なぜ、彼・彼女は、こだわりやパニックという行動をとるのだろう?」と、ひとりの人間の心の動きとして紐解いていく。
発達障害の人も、人を求めている
たとえば、「広汎性発達障害(※)の人は一人が好きで孤独を好む。一人でいても平気だ」という解説を見かけることがある。(※診断名は、書籍発行時(2012年)の名称です。以下同じ)
しかし、ある中学生の女の子は、「一人がいいです」ときっぱりと言いながら、家にいる時は学園ドラマを観ていた。少女は、友だちの中に入りたい気持ちを学園ドラマを観ることで慰めていたのだ。
別の子は、一つの曲をくり返し聴いていた。それは発達障害の“こだわり”の特性のように、周りには見えていた。しかし、進級して友だちができた時から、彼女は友だちが聴くほかの曲も聴くようになった。一緒に曲を聴く友だちができて、彼女の一つの曲へのこだわりは消えた。
広汎性発達障害の人が言う「一人がいい」は、「人といて孤独でいるよりは一人がいい」という意味である。
多くの発達障害の人は、人を求めていると青木氏は語る。
青木氏はそのほかにも、発達障害の人のこだわり、ウラオモテのなさ、パニック、奇行などの事例を挙げ、特性の向こうに見える彼らの心を探っていく。
それらを読んでいくと、「これって、どんな人でも感じることじゃないか?」ということに思い当たる。
興味のない話題について行けず疎外感を抱いたり、せっかく立てた予定を邪魔されて腹が立ったりということは、定型発達の人にも少なからず経験があるのではないだろうか。
発達障害の特性の向こうにあるのは、普遍的な「人の心」だ。
“特性”という言葉に囚われすぎず、発達障害の人がどのような気持ちで、何を考えて生きているのかに目を向けることの大切さを、青木氏は語っている。
「外から目線」で見えるのは、その人「心」ではない
発達障害の診断がついた途端に、周りが当事者の気持ちに目を向けなくなってしまうということが往々にしてある。
今までその人のことを応援し、理解しようとしてきた人(教師や保護者)の態度に、変化が生じるのだ。
青木氏は、それを「外から目線」と呼んで警鐘を鳴らす。
極端な例ではあるが、今までその子の気持ちに寄り添って試行錯誤していた教師が、発達障害の診断名が付いた途端に、「教師や学校にできることは何かと考える態度から、医療機関の指示を受けてから対応するといった態度に変わってしまう」ということがある。
家庭でも、我が子の気持ちを汲み取ろうと寄り添っていた両親が、発達障害かもしれないと言われた途端に、医師やカウンセラーの意見を通してわが子を見るようになることも多いだろう。
発達障害かもしれないと思った時から、教師や親の目が、彼の苦しみを考えるものから、発達障害の特徴を見つける目に変わってしまう。彼の「心」を見なくなる。
これはとても残念なことであると、青木氏は言う。
その人の心を見ないということは、その人との関わりを実質的にやめてしまうということでもある。
周りが関わることを実質的にやめてしまうと、当事者はそれを敏感に察知して、見捨てられたような気持ちになるだろう。
関わりを断ってしまう「外から目線」は、発達障害の人の社会性の芽を摘んでしまう。
もちろん、客観的に発達障害の症候を観察することが必要ないというわけではない。
主観的に気持ちを理解しようとする態度と、客観的に症候を観察する態度のバランスがとれていることが重要なのだ。
発達障害の人は、海外に留学した日本人のようなもの
本書では、青木氏からの発達障害の当事者に向けたメッセージと、困り感に対する具体的な対処法も紹介されている。
その中でもとくに印象深いエピソードを、最後に紹介したいと思う。
発達障害の人は、人とうまくやれなかった経験から、「人から嫌われている」「馬鹿にされている」と思い込むことが多い。
青木氏は、自身のイギリス留学時のエピソードを挙げて、「嫌われている」「馬鹿にされている」は思い込みかもしれないよ、と発達障害当事者に語りかける。
青木氏は、イギリス留学時代、言葉や文化の違いから周りとうまくやれず、発達障害の人と同じように、周りに嫌われているような、馬鹿にされているような感覚に陥っていた。
ある時、青木氏は指導教官の家に夕食に招かれた。
すでに疎外感に苛まれていた彼は、指導教官を不親切な人だと思いこんでいた。
指導教官の家は郊外の田舎にあり、交通の便が悪い場所だった。夕食後、指導教官は青木氏を駅まで車で送り、あっさりと帰ってしまった。
時刻は終電の時間になっている。
誰もいない暗い駅で電車を待ちながら、「外国人を田舎の駅に一人残して帰るなんて、冷たいんじゃないか」と青木氏は思った。
ところが、数日後に会った時、指導教官は思いがけないことを青木氏に言った。
「この前の晩は、終電に乗れてよかったね。僕は君が無事に電車に乗るかどうかを丘の上からずっと見ていたんだよ。電車が来るまで一緒に待つのは、イギリスでは子ども扱いをしていることになって失礼に当たるんだ。もし電車が来なければ、家に泊めなきゃいけないからね。心配で遠くから見ていたんだ」
心配というものの「文化」が違う。
その時、青木氏はそのように感じたそうだ。
発達障害の人は、イギリスに留学した日本人のようなものだ。
イギリス人と日本人で文化が違うように、発達障害の人と定型発達の人とでは文化が違う。
「心配する」「慰める」「励ます」「思いやる」……。
文化が違えば、やり方が違う。
「嫌われている」「馬鹿にされている」と感じる発達障害の人は、相手は違う文化の、自分が知らないやり方で心配してくれているのかもしれないと、時に立ち止まって考えてみる必要があると青木氏は言う。
自分が思いもしなかった、相手の思いやりや、気持ちの奥深さが見えてくるかもしれない。
自分が思っていたほど、相手は自分を嫌っていなかったことに気づけるようになるだろう。
【ご紹介書籍】
青木省三『ぼくらの中の発達障害』(ちくまプリマー新書、2012年)