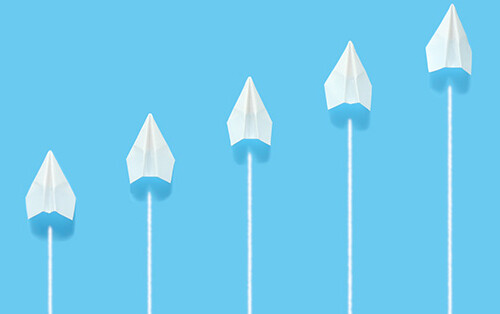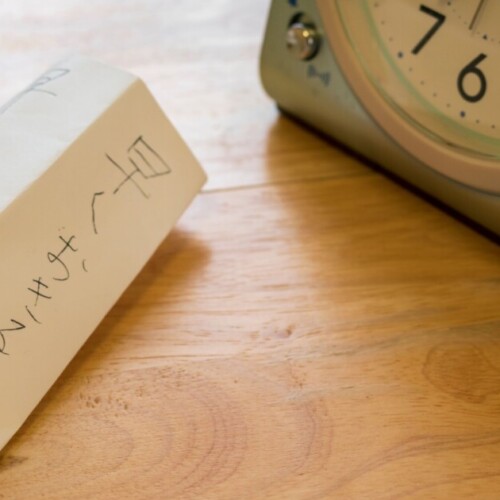放デイ職員に聞きました! 不登校親子の悩みトップ3とその対策
発達障害やその可能性のある子どもの中には、不登校で放課後等デイサービスに通う子どももいます。
発達障害の子どもが不登校になる原因はさまざまですが、いずれの困りごとにも対応法があり、サポートする人や制度があります。
目次
放課後等デイサービスとは

放課後等デイサービス(放デイ)とは、児童福祉法に基づく障害者福祉サービスです。
通所施設であり、発達に遅れなどがあって医師から発達障害と診断された場合、または意見書などでサポートが必要と認められた場合に、保育士、教員資格、心理士などの資格を持った職員から、専門療育を受けることができます。
障害者福祉サービスとありますが、厚生労働省が作成した資料にも「継続的に学校に通学できない児童(不登校児童)への支援の充実」と定められている通り、不登校児童へのサポートも行っています。
また、不登校児童が通う放課後等デイサービスは、学校と連携を図って支援をする必要があります。
そのため、学校と連携会議を開き児童の困り感などについて話し合ったのち、療育内容を決めて支援を行います。
利用している児童の多くは、放課後に放課後等デイサービスを利用をしますが、午前中から営業している事業所であれば、朝から通うこともできます。
施設によってサービス内容は若干異なりますが、主に学習支援、SST(ソーシャルスキルトレーニング)、自立支援などを受けられるほか、児童の特性を理解した上でサービスが受けられるため、居場所や心の拠り所にもなり得ます。
放課後等デイサービスに通うためには、各自治体が発行している受給者証(障害児通所受給者証)が必要です。通所を希望する場合は、行政の窓口(役所の社会福祉課など)へ相談しましょう。
「発達障害があって、不登校」の子どもの「お悩みトップ3」と対応法
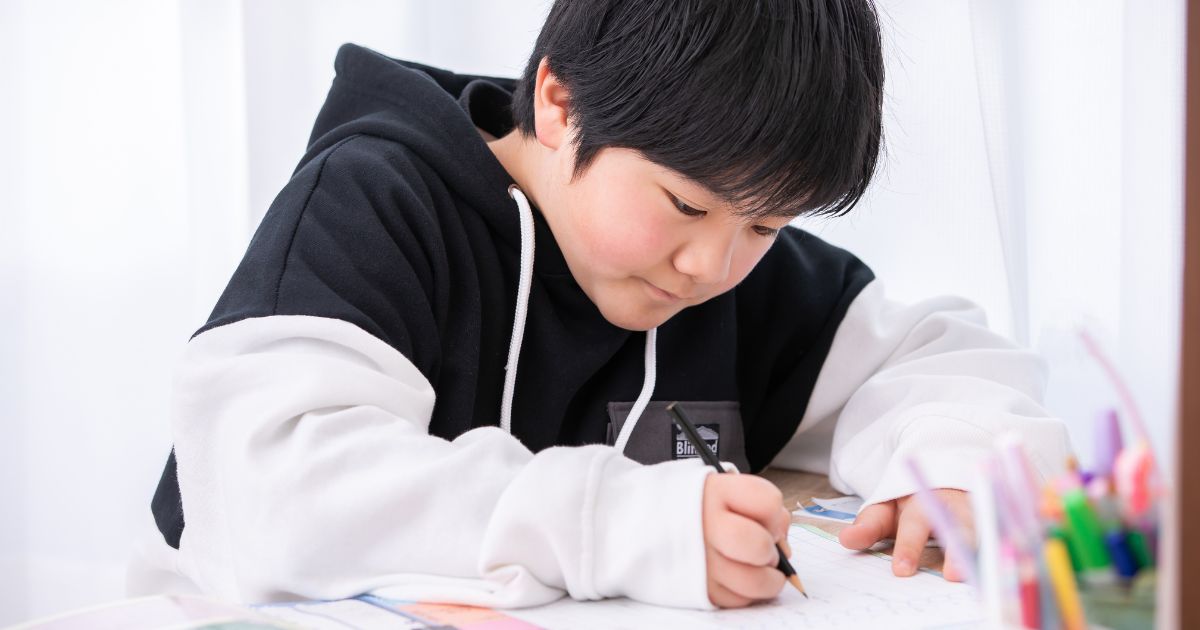
1. 人間関係の悩み
ASD(自閉症スペクトラム障害)の子どもは、その特性にコミュニケーションの苦手さや、こだわりの強さなどがあります。
コミュニケーション面では、相手の気持ちを察することが苦手であったり、比喩や冗談などがわからず言葉をそのままの意味で受け取る、思ったことを言ってしまう、暗黙の了解などの社会的なルールの理解が苦手、といった特徴があります。
相手の状況を推しはかったり、気持ちを理解したりするのが苦手なことから、意図せず相手を傷つけてトラブルになることもあります。
こだわりの強さからは、マイルールを発動して身勝手な行動を取ったり、時間を守ることが苦手なために約束を守れないといったことがあります。
また、ASDの子どもは見た目では障害があることが分かりにくいため、周りからは「ちょっと変わった子」と捉えられがちです。そのため、友人とのトラブルやクラスでの孤立にが起こりやすいのです。
人間関係に困り感がある子どもへの対応法
ASDなどで相手の気持ちが理解できない子どもに対しては、SST(ソーシャルスキルトレーニング)や、療育現場での集団活動の経験を積むという方法があります。
SSTでは発達や年齢に応じて、個別療育やグループレッスンなど、さまざまな療育を行います。
SSTの例
①会話や行動
- 相槌の打ち方や話を聞く時の態度について学ぶ。
- 場面カードなどを用いて、TPOに応じた適切な行動を学ぶ。
②気持ちの表現、理解
- 自分の気持ちをコントロールし、適切に表現する方法を学ぶ。
- 自己理解・他者理解を深め、人間関係構築のためのスキルを養う。
③振り返り
- 自分の行動のよかった点・気をつける点などを考える。
- フィードバックをしてもらうことで、次からの行動に繋がる支援を受ける。
2. 学習の遅れによる悩み
LD(学習障害)の子どもは、聞く、読む、書く、話す、計算する、推論するといった特定の分野に苦手さがあります。
就学後その苦手さは顕著となり、授業が分からないからおもしろくない、ついていけない、勉強や宿題が苦痛といったストレスから、不登校になるケースがあります。
子どもの学習の遅れを心配するがゆえに、大人は知らず知らずのうちに、子どもにプレッシャーをかけていることも少なくありません。
プレッシャーによる息苦しさや、自己肯定感の低下なども、不登校につながることがあります。
学習の遅れがある子どもへの対応法
学習に遅れがある子どもは、努力が足りていないわけではありません。
しかし周りからのプレッシャーで、自己肯定感や自尊心が下がっていることが多くあります。
叱責したり、詰め込んで学習に取り組ませたりするのは逆効果です。学習に対する苦手意識がかえって深まるので、避けましょう。
子どもが楽しみながら興味を持って学習に取り組めるように工夫し、少しでも取り組めたときには、たくさん褒めることで自信に繋げることが大切です。
学習の工夫の例
①読み書きの練習
- 子どもの好きな絵本を使う。
- 好きなキャラクターの名前で文字を書く練習をする。
②教材の選択
- 子どもが興味を持つようであれば、知育アプリやタブレット学習などで、勉強へのハードルを下げる。
③学校との相談
- 子どもの発達に合った宿題を用意してもらう。
3. 環境への対応の難しさによる悩み
発達障害やその可能性のある子どもの中には、音や光などの感覚刺激への弱さから不登校になる子どももいます。
また、「学校まで行ったけど教室に入れない」「教室の人の多さがしんどい」「運動会の練習など、行事によるスケジュール変更に対応ができない」など、環境の変化についていけないことが不登校につながることもあります。
環境への対応の難しさがある子どもへの対応法
子どもがどのようなしんどさを感じているのかをよく確認し、環境を調整しましょう。
環境調整の例
①人の多さがしんどい、心がざわざわする
- 教室や別室(校長室や保険室など)にカームダウンスペースなど、安心できる場所を用意してもらう。
②スケジュール変更に対応できない
- イラストや文字などの視覚支援を取り入れ、事前にスケジュールを伝える。
- 放課後デイサービスでは、学校以上に合理的配慮を意識していることが多いです。
- 自分に合った環境がある場所に通うことで、子どもは「安心できる場所があるんだ」と感じることができます。
「発達障害があって、不登校」の子どもの保護者の「お悩みトップ3」と対応法

1. 学習が遅れる
子どもの発達や学習に遅れがあると、ほかの子どもよりも努力が必要だと思う保護者もいるかもしれません。
そんななかで子どもが不登校になると、「より差が開いてしまうのでは」と不安になります。不登校で勉強に取り組む時間が減って「勉強の習慣が変わってしまうのでは」「いつか学校に戻ってもついていけないのでは」と思うこともあります。
学習が遅れることへの対応法
不登校で学習が遅れることが不安な場合は、フリースクールや放課後等デイサービスに通うという選択肢があります。
いずれも学習支援を行っています。個別サポートがあるため、学校のような集団指導ではなく、個々に合わせた学習のフォローを受けられます。
施設ごとに特徴や強みがあるので、子どもに合った場所を見つけてください。社会や学校での不安の軽減が早まることも期待できます。
2. 家族も振り回される
子どもが学校に行かない場合、本人だけでなく家族にも影響が出るケースがあります。
きょうだいがいる場合は、不登校の子どもに影響を受けてほかのきょうだいも不登校になることを心配する保護者もいます。
年上の子どもが不登校になって自尊心が傷ついたり、年下の子どもがきょうだいの不登校をよく思わないなど、きょうだい間の関係が悪化することもあります。
また、保護者の仕事にも影響が出ることから、とくにシングルペアレントの家庭では経済的な問題につながるケースがあることも報道されてます。
家族が振り回されないための対応法
こちらも、放課後等デイサービスの活用で、課題をある程度解消できます。
決まった時間や曜日での利用を目標にすることで、生活リズムの悪化を防ぐことにもつながります。安定した生活リズムで日常を送れるようになると、家族への負担が軽減されます。
きょうだいにも「学校とは違う場所でがんばっている」と説明できるため、きょうだい間の関係悪化を防ぐことも期待できます。
放課後等デイサービスは、経済的にフリースクールの利用が難しい家庭でも利用しやすいしくみが整えられています。利用料金の9割を国や自治体が負担し、さらに前年度の年間世帯所得によって、利用者負担額の上限が決められています。
3. 親子関係の悪化
仕事への影響や、子どもの将来への心配から保護者はつい子どものプレッシャーになる言葉をかけることがあります。子どもも、「甘えられる対象」である保護者に対してキツく当たることがあります。
また、「相手の気持ちの理解が苦手」という特性のある子どもは、保護者が苦労していてもそのことに気づかないケースもあります。
こうしたことが続き、親子関係が悪化することもあるのです。
親子関係の悪化に対する対応法
発達障害のある子どもも、ほかの子どもよりは成長スピードがゆっくりです。
「いつ勉強するようになるんだろう」「いつ私の苦労に気づいてくれるんだろう」と、焦ることもあるでしょう。しかし、 必ず成長はしています。
「先日、私のためにご飯を作ってくれたんです。仕事で疲れているでしょって言ってくれて。そんなこと今までなかったので驚きました」
放課後デイサービス利用中のある保護者の言葉です。
子どもの発達特性を理解し、ほかの子どもと比べずに、子どものペースを信じることが、親子関係を悪化させないための秘訣です。
困ったときは、専門家やサービスを活用して!

相談支援員や放課後等デイサービス職員に話を聞いてもらうだけでも、心は軽くなります。具体的なアドバイスをもらえることもありますので、積極的に周囲に協力を求めましょう 。
放課後等デイサービスなどを利用することで、一人で考えていたときにはわからなかった方法を知ることができます。専門家同士が連携し、カンファレンスなどを開くことで新しい解決法が見出される可能性もあります。
こうしたサービスを活用することは、何も悪いことではありません。むしろ積極的に上手に利用して、子どもや家族の生きやすさにつながる道を探っていってください。
お子さんも、保護者のみなさんも「次の一歩」へ!
「不登校オンライン」では、会員向けの記事(有料)をご用意しています。不登校のお子さんをサポートするために知っておきたい情報や、同じ悩みをもつ親御さんの体験談などを掲載しています。お申し込みは下記から(30日間無料)。