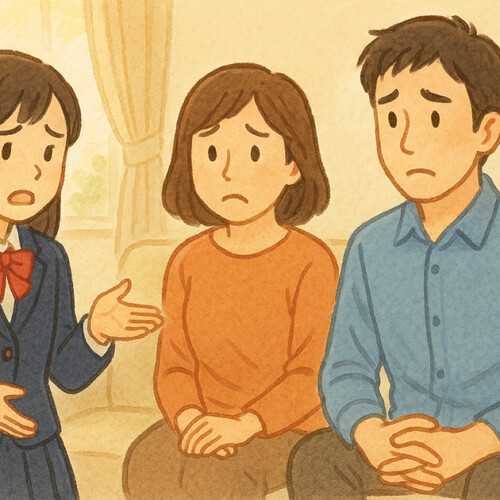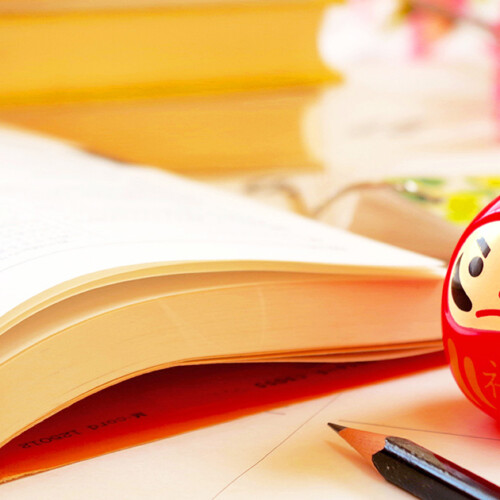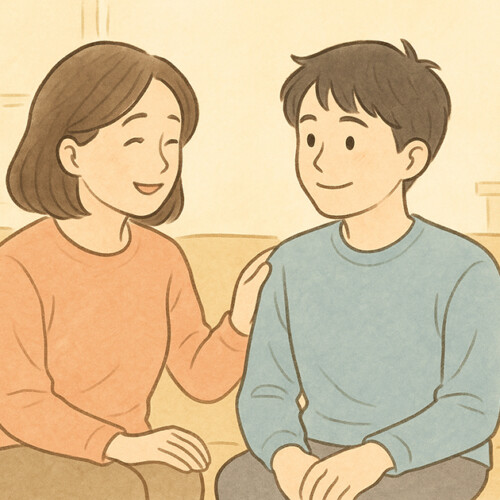【不登校前兆期】「暑くて疲れた…」と言い出したら?夏の体調不良と心のSOSの見分け方【不登校の知恵袋】
夏になると、子どもが「暑くて疲れた…」「だるい…」と訴える場面が増えてきます。
夏は、気温や湿度の影響のために体が不調になりがちです。
しかし、実は「学校に行きたくない気持ち」が体の不調として現れているサインであることも(そしてもちろん、両方が関係することもありますし、両方が関係ないこともあります)。
何が原因であったとしても、子どもたちは心身の違和感をうまく言葉にできないことが少なくありません。
本記事では、子どもの体の不調の原因を、「夏の疲れ(夏バテ)」と「学校に行きたくない気持ち(心のSOS)」の2つの観点で着目。その見極め方や接し方を、具体的に解説します。
※本記事でお伝えする内容は、あくまでも参考です。心身の不調については、迷わずに医療機関を利用しましょう。
【不登校前兆期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。前兆期とは、「何らかの要因で、心理的な安定度が崩れていき、学校を本格的に休み始めるまでの期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校前兆期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
体と心の不調を見極める5つのポイント
子どもの不調が「夏の疲れ」なのか、「心のSOS」なのかを判断するのは難しいものです。ここでは、両者の違いを見極めるための視点を紹介します。
1. 不調のタイミングを観察する
夏バテの場合
- 炎天下での外出後や、寝不足の翌日など、生活リズムや環境によって疲労感が強まることが多い。
心のSOSの場合
- 月曜日の朝、登校の準備時間など「学校に関係する時間帯」に集中して不調を訴える傾向がある。
2. 症状の一貫性・改善傾向を見る
夏バテの場合
- 水分補給や休息で回復傾向が見られる。
心のSOSの場合
- 十分に寝ても疲れが取れない、同じ症状が何日も続く、病院の検査でも「身体的な原因」が見つからないことが多い。
3. 好きなことに対する反応を見る
夏バテの場合
- 体調に波があっても、好きなこと(遊び、動画視聴など)には反応する。
心のSOSの場合
- 好きなことへの関心そのものが薄れ、意欲が出ない、反応が乏しい。
4. 食事や睡眠に現れる変化を見る
夏バテの場合
- 冷たいものや軽食は食べられる、クーラーをつけると眠れるなど、環境次第で改善する。
心のSOSの場合
- 好きな食べ物でも拒否、就寝前に不安が強くなる、朝起きられないなど、根本的なエネルギー不足が疑われる。
5. 会話や態度の変化を感じ取る
夏バテの場合
- 体調が回復すれば自然と会話も戻る。
心のSOSの場合
- 「別に」「どうでもいい」などのそっけない返答や、家族との接触を避ける傾向が出てくる。
保護者がとるべき接し方:言葉と態度で安心を伝える
子どもが「疲れた」「だるい」と言ってきたとき、まずはその言葉をそのまま受け止めてください。たとえ原因がはっきりしなくても、子どもにとっては「本当にしんどい」のです。
否定しない、評価しない
「気のせいじゃない?」「そんなの甘えだよ」と言うと、子どもはもう何も言えなくなります。「そうか、疲れてるんだね」「無理しなくていいよ」といった肯定的な受け止めが大切です。
登校を前提にしない声かけ
「明日は行けそう?」「そろそろ頑張らなきゃね」といった言葉は、悪気がなくてもプレッシャーになります。
登校再開は、必ずしも目指すべきことではありません。「今日は家でゆっくりしよう」「まずは体を休めよう」と声をかけるようにしましょう。
家庭でできる具体的なサポート
体も心も疲れやすい夏。子どもが少しでも安心できるような家庭環境づくりを意識しましょう。
快適な室温と湿度を保つ
寝苦しさやだるさの原因となる室温・湿度は、エアコンや除湿機などで調整し、体に負担がかからないようにします。子ども自身が快適と感じる温度にできる自由も尊重しましょう。
規則的な食事・水分補給をサポートする
「食べなさい」ではなく、「何なら食べられそう?」と問いかけることで、子どもが自分から選べる感覚が持てます。冷たいフルーツやゼリーなど、楽に口にできるものを常備しておくと安心です。
「何もしない時間」を許す
エネルギーが枯渇しているとき、子どもは何をする気にもなれません。そんなときは、「今日はゴロゴロしてていいよ」と伝え、何も求めない空気を家庭に作っておくことが回復への土台になります。
必要に応じて相談を──医療や支援機関の活用も視野に
子どもの不調については、積極的に専門家のサポートを利用しましょう。相談は「早すぎる」と思うより、「早くしてよかった」と思えるケースがほとんどです。
小児科・内科
- 体の不調を確認する第一歩として
スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー
- 学校を介した支援の窓口
フリースクールや支援機関
- 学校以外の学びや居場所づくりとして
児童精神科・心理相談機関
- 心の専門的ケアが必要な場合に
関連記事
不登校前兆期の「夏の体調不良」について、親の対応につまづきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ)が見聞きした、不登校の前兆期のお子さんの「夏の体調不良」への親の対応で、つまづきがあったエピソードを紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
「暑さに疲れてるだけ」と励ました結果、子どもは心を閉ざした
中学1年生のリクくんは、7月に入ってから「暑い」「だるい」と言って、登校を渋る日が増えていました。
母親は「夏バテか成長期のせいかな」と軽く考えており、栄養ドリンクを買ってきたり、早寝を促したりと、体調管理に注力していました。
ある日、リクくんが「学校に行きたくない」とつぶやいたとき、母親は「暑さに疲れてるだけでしょ、夏休みまでもう少しだし頑張ろう」と励まします。それ以来、リクくんは気持ちを口にしなくなりました。