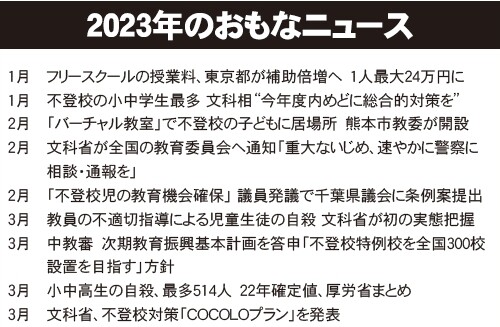【不登校進行期】「始業式、出る?出ない?」の問いが重くならない工夫【不登校の知恵袋】
2学期の始業式が近づくと、「式に出る・出ない」という判断を迫られる場面が生まれます。子どもにとってそれが、心理的な負担となることが少なくありません。
1学期までに子どもが学校を休みがちになっていても、始業式はひとつの「区切り」として意識されやすいものです。
むしろ、休みがちだったからこそ、「2学期は、行った方がいいのかな」「みんなとどんな顔で会えばいいんだろう」などの悩みが生じる子も多くいます。
学校を休みがちな子どもにとって、始業式の当日は、先生や友達との再会、いつもと違う教室の雰囲気、周囲の視線など、登校に際しての「全部入り」のハードルが詰まっています。
大切なことは、始業式に出るか出ないかを、子ども自身が決めること。その選択に関連して、子どもの安心を守る関わり方や、この時期にできる工夫を解説します。
【不登校進行期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。進行期とは、不登校が始まり、心理的な落ち込みが激しくなり、やがてその状態が固定化されるまでの期間のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校進行期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「出る・出ない」が親の期待にならないようにする
子どもが自分で選択できるようにするには、親の言葉が「期待」に聞こえないように配慮することが大切です。
子どもは「問いの裏」に敏感です
「始業式、出る?出ない?」という何気ない問いでも、子どもにとっては“出るのがいいこと”という前提が感じられることがあります。
親としてはただ確認したつもりでも、子どもは「本当は出てほしいんでしょ」と受け取ることがあるのです。
これは、学校に行っていないことで日頃から自信を失いがちな子どもにとっては自然な反応です。「親の期待に応えられない自分」をまた確認するような痛みも伴います。
「出てくれたらうれしいな」は誰のため?
親の言葉に「出てくれたらうれしいな」が混ざるとき、それが本心であっても、子どもは「親のために行くかどうかを決める」ような感覚に陥ることがあります。
大切なのは、子ども自身が「行ってみよう」「行かない」と決断できるかどうか。
親の気持ちが先行すると、それに応えることが目的になって、本来の“自分の感覚”がわからなくなるリスクがあります。
子どもが「自分で決めた」と感じられる関わり方とは
始業式への出欠をどうするか――この選択を子ども自身が納得して決められるよう、親の姿勢にも工夫が求められます。
決定の主導権を子どもに委ねる
「行ってもいいし、行かなくてもいいよ。どうしたいか決めていいよ」
このように選択の余白を示し、決定の主導権を子どもに戻す声かけが効果的です。
親の側が結果にどちらもOKというスタンスでいると、子どもは「どちらを選んでも責められない」という安心を持つことができます。
たとえば、次のように、あらかじめプレッシャーを取り除く言葉を添えておくと効果的です。
- 「当日になって決めてもいいよ」
- 「行くかどうかは朝の気分で決めてもいいからね」
- 「お母さんはどっちでも大丈夫だよ」
ただしその上で、子どもから「投げやりな対応をされているな」「自分のことはどうでもいいんだな」と思われないよう、真摯に伝えるようにしましょう。また、「相談したいならしてね」といった声掛けなどもアリです。
行けたらよし、行けなくてもよし
親の本音としては「行ってくれたら安心」「少しでも顔を出せたらよかった」と思うこともあるかもしれません。それ自体は自然な感情です。
ただ、子どもがその気持ちを背負うと、「できなかった自分」をまた責める材料になりがちです。
そうならないよう、「行けたらラッキー」「行けなくても全然大丈夫」というメッセージを、親自身がまず納得しておくことが大切です。
行かない選択にも意味がある
始業式に行かないという判断は、「失敗」ではなく、子どもが自分を守るために必要な行動であることも多くあります。
今の心身の状態では、教室に戻ることが負担になりすぎる場合もあるのです。
この選択を尊重することで、子どもは「理解されている」「自分の気持ちを大事にしていい」と感じることができ、その後の親子関係や心理的安定につながります。
始業式=通過点と捉えて、親も構えすぎない
親が構えすぎず、気負わずに始業式を見守る姿勢が、子どもにも安心感を与えます。以下、具体的にお伝えします。
登校の再開と結びつけすぎない
「始業式に出席できたら、2学期はそのまま登校できるかも」
そんなふうに捉えると、始業式が“試金石”のような重たい存在になります。
しかし、登校再開には波があります。たとえこの日に出られたとしても、翌日にはまた休むこともあります。逆に、出られなかったとしても、その後に心身のエネルギーが回復することもあります。
一日一日の選択に一喜一憂せず、「今はこの判断を大事にしよう」と思えることが、長い目で見たときの支えになります。
親の安心のために子どもを使わない
始業式に出てくれたら、親としても安心。もちろんそれは自然な思いです。
ただ、「親の自分が安心したいから子どもに出てほしい」と思ったり、子どもに伝えたりすると、“親のための登校”になります。
大事なのは、親としても、自分自身の不安や期待をきちんと整理すること。
たとえば、「どうして自分は出てほしいと思ってるのか?」「行かないと、何が不安なのか?」を振り返ってみることで、子どもにプレッシャーをかけずにすみます。
「出る・出ない」よりも、親子の関係が残るように
「始業式に出るかでないか」。この問いの先に残るのは、出欠の記録よりも、親子のやりとりや信頼関係です。
始業式に出席したかどうかは、長い目で見れば一つの出来事に過ぎません。それよりも、この選択の場面で「親が自分をどう受け止めてくれたか」という記憶は、子どもの中に長く残ります。
- 「どんな選択でも受け入れてくれた」
- 「自分の気持ちを尊重してくれた」
- 「一緒に考えてくれた」
そうした経験の積み重ねが、結果として子どもの自己肯定感や安心感に結びつきます。
逆に、「行かなかったことでがっかりされた」「自分のせいで親が不機嫌になった」といった記憶は、心にしこりとして残り、親子関係に影を落とすこともあります。
だからこそ、「始業式に行くかどうか」そのものよりも、「どんなやりとりが交わされたか」「親がどう構えたか」に目を向けることが大切です。
「始業式は、ただの一日。その日の選択がどうであっても、親子の関係は続いていきます。大切なのは、今このときに、子どもにとって安心できる土台を築くことです。
始業式への出欠に関連して、親の対応につまづきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ)が見聞きした、不登校の子どもの始業式への出欠に関連して、親の対応につまづきがあった事例(エピソード・ストーリー)を紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
「登校をがんばれる自信」を手にしてほしかった
中学2年の悠人くんは、4月から五月雨登校を続けてきました。8月の半ば、母は「2学期になったら、せめて始業式には出て」と頼みました。