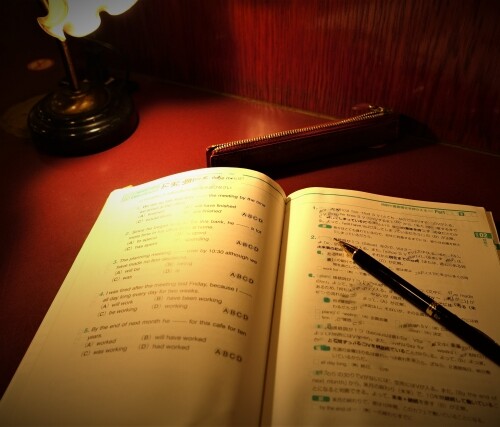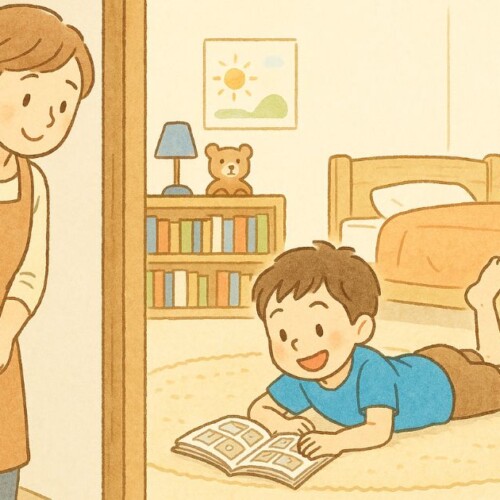【不登校前兆期】2学期の「行きたくない…」が出始めたときに親ができること【不登校の知恵袋】
2学期の生活が本格化した10月。子どもから「学校に行きたくない」という言葉が出始めると、親としては大きな不安を覚えるものです。ここでは、登校を無理に促すのではなく、安心感を与え、エネルギーを回復させる関わり方について具体的に整理します。
【不登校前兆期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。前兆期とは、「何らかの要因で、心理的な安定度が崩れていき、学校を本格的に休み始めるまでの期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校前兆期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
子どもの「行きたくない」を受けとめる第一歩
2学期に「行きたくない」という言葉が出ても、子どもは「必ずそのまま不登校になる」わけではありません。しかし、心の疲れや負担のサインであることは確かです
「休んでいいよ」と伝える
この時期に大切なのは、学校を休むことを否定せず、安心して休める選択肢を提示することです。「(今日は)休んでいいよ」と言われることで、子どもは元気を取り戻し、また自己肯定感を保ちやすくなります。
身体の不調が現れることも
「お腹が痛い」「頭が痛い」などの訴えが増えたときは、ストレスのサインかもしれません。身体的な診察では「異常なし」と診断されることもあります。その場合は、子ども向けのメンタルクリニックも検討しましょう。
子どもの気持ちを打ち消さない
子どもが「学校に行きたくない」と言ったとき、「そんなこと言わないで」「頑張りなさい」と打ち消すのは避けたいところです。まずは「そう思うんだね」と受けとめることが、安心感につながります。
理由を聞き出そうと焦らない
学校に行きたくない理由を知りたくても、子どもは「言いたくない」と思うこともあります。自分でも理由がわからないことも、またわかっていてもうまく言語化できないこともあります。理由を無理に聞かず、「話したくなったらでいいよ」と伝える姿勢が大切です。
登校を促す声かけは控える
子どもが「行きたくない」と言ったとき、登校を促す言葉は逆効果になることが多いです。そうではない言葉に言い換えて伝えましょう。
NGワードと代替表現
-
- NG:「早く学校に行きなさい」 → 代替:「今日は家でゆっくり休もう」
- NG:「明日から頑張ろうね」 → 代替:「明日のことは明日考えよう」
- NG:「学校に行かないと将来困るよ」 → 代替:「どんなときも、私は味方だよ」
日常生活の小さな変化を整える
「学校に行きたくない」という気持ちが出始めたときには、生活リズムや環境の小さな工夫が大きな支えになります。
家の中で安心できる時間を増やす
子どもが家庭で安心できる時間を意識的に持つことが、心の回復を助けます。テレビを一緒に観る、雑談するなど、小さな習慣が支えになります。
好きなことに没頭できる時間を与える
ゲームや読書、絵を描くことなど、子どもが「楽しい」と感じることを取り入れることも大切です。「学校に行っていないのに、ゲームなんて」とは思わないようにしましょう。楽しめる時間は、心のエネルギーを回復させる力になります。
イベントや行事シーズンの対応〜参加しなくていいという選択肢も〜
秋は運動会や文化祭など、学校行事が続く時期です。学校外でも、秋祭りといったイベントも行われます。子どもにとっては、楽しみである一方、負担や不安の要因になることもあります。
行事に出られなくても、お子さんが全否定されるわけではありません。参加したいかしたくないかを確認しながら、「無理に出なくてもいい」と伝えることで、気持ちが楽になります。これは「イベントの当日」だけではなく、準備・練習についても同じです。
学校や外部機関との連携
子どもの状態を家庭だけで抱え込まず、学校や支援先と情報を共有することも重要です。
担任への報告・連絡・相談
子どもが「行きたくない」と言い始めた段階で、担任の先生に状況を伝えましょう。理解のある担任であれば、「これからどうするか」といった話がスムーズに進みます。
担任に理解がない場合は、学年主任の先生などにも相談しつつ、学校外の選択肢も積極的に探しましょう(担任に理解がある場合も、学校外の選択肢は積極的に探してOKです)。
学校以外の選択肢も意識する
地域のフリースペースや相談機関など、学校以外の居場所や支援先を知っておくことは、親自身の安心にもつながります。また、不登校に理解のある塾や家庭教師などもあります。
関連記事
親の「不安のコントロール」も大切
子どもが「行きたくない」と言い出したとき、親の心が揺れるのは自然なことです。その不安をコントロールするようにしましょう。そのためには、情報の収集と、相談先の確保が効果的です。
「学校に行きたくない子ども」に関する本やウェブメディアはたくさんあります。それらから情報・知識を得るようにしましょう。
そして、お子さんのことを、親だけで抱え込む必要はありません。信頼できる友人、支援機関、学校外の相談窓口に状況や気持ちを話すようにしましょう。
ともに、安心できるだけではなく、具体的な「できること」も見つかっていきます。
関連記事
親子で過ごす「安心の時間」を重ねる
結局のところ、子どもの「行きたくない」気持ちに親がどう向き合うかは、日々の小さな積み重ねにかかっています。
子どもの安心感を最優先にする
登校再開を目指すよりも、子どもが「安心して過ごせる」ことを第一に考えましょう。安心できる環境で、子どものエネルギーは少しずつ回復していきます。
焦らずに見守る姿勢
親が先を急がず、まずは「今できていること」に目を向けることで、子どもの回復力を支えられます。小さな変化に気づき、認めることが大切です。
不登校前兆期で、2学期に「学校行きたくない」と言い始めた子どもへの対応につまづきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ共育塾)が見聞きした、2学期に「学校行きたくない」と言い始めた子どもへの親の対応に、つまづきがあった事例を紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
1.「明日も頑張ろうね」の約束が重荷になっていった
中学校1年生のゆうさんは、2学期の3週目、夕方になると「明日、行きたくない…」と言うようになりました。親は励ますつもりで「大丈夫だよ。明日もまた頑張ろうね」と繰り返します。寝る前には「明日、学校行けるよね。約束ね」と確認しました。