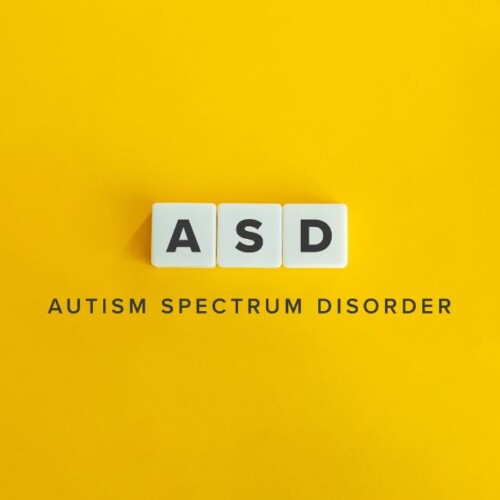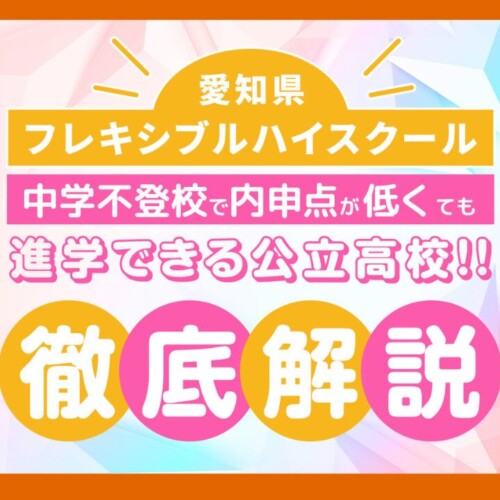【不登校混乱期】「高卒後の進路の話、まだ早い?」——焦りがすれ違いを生むとき【不登校の知恵袋】
高校生の子どもが不登校になってしばらく経ち、日常が落ち着かないまま時間が過ぎていく——。
親としては、「高校を出たあと、どうなるのだろう」「そもそも、高校を卒業できるのだろうか」という不安が常に頭にあるでしょう。
しかし、焦って将来の話を持ち出すと、子どもの心をさらに閉ざすことがあります。この記事では、「高卒後の進路の話をいつ、どう扱うか」を中心に、不登校混乱期の子どもへの寄り添い方を考えます。
【不登校混乱期とは】
不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校混乱期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「焦り」は“愛情があるからこそ”
不登校混乱期の親にとって、「焦り」は避けられない感情です。「このままで社会に出られるのだろうか」「同級生との差が広がっていく」と思うほど、心がざわつくのは当然のこと。
その焦りは、子どもの将来を想う深い愛情があるからこそのものです。
問題は、愛情よりも焦りが先行するとき。「なんとかしなければ」という思いが、結果的に子どもへのプレッシャーとなり、時期尚早な進路の話を生みやすくします。
子どもはまだ心理的な回復の途中にあり、将来を問われると「いまの自分を否定された」と感じて心を閉ざすこともあります。
焦りを抑え込む必要はありません。「焦っているのは、子を想うがゆえ」と受け止めて、その気づきを“話を急がないためのブレーキ”に変えることが大切です。
「まだ早い」かどうかを判断するための目安
不登校混乱期のお子さんにとって、最優先は心理的な休養です。進路の話を持ち出すべきかどうか迷ったときは、「話せる余力があるか」を基準にしましょう。お子さんの状態と、進路の話の適切性の例を紹介します。