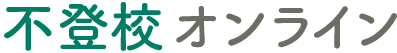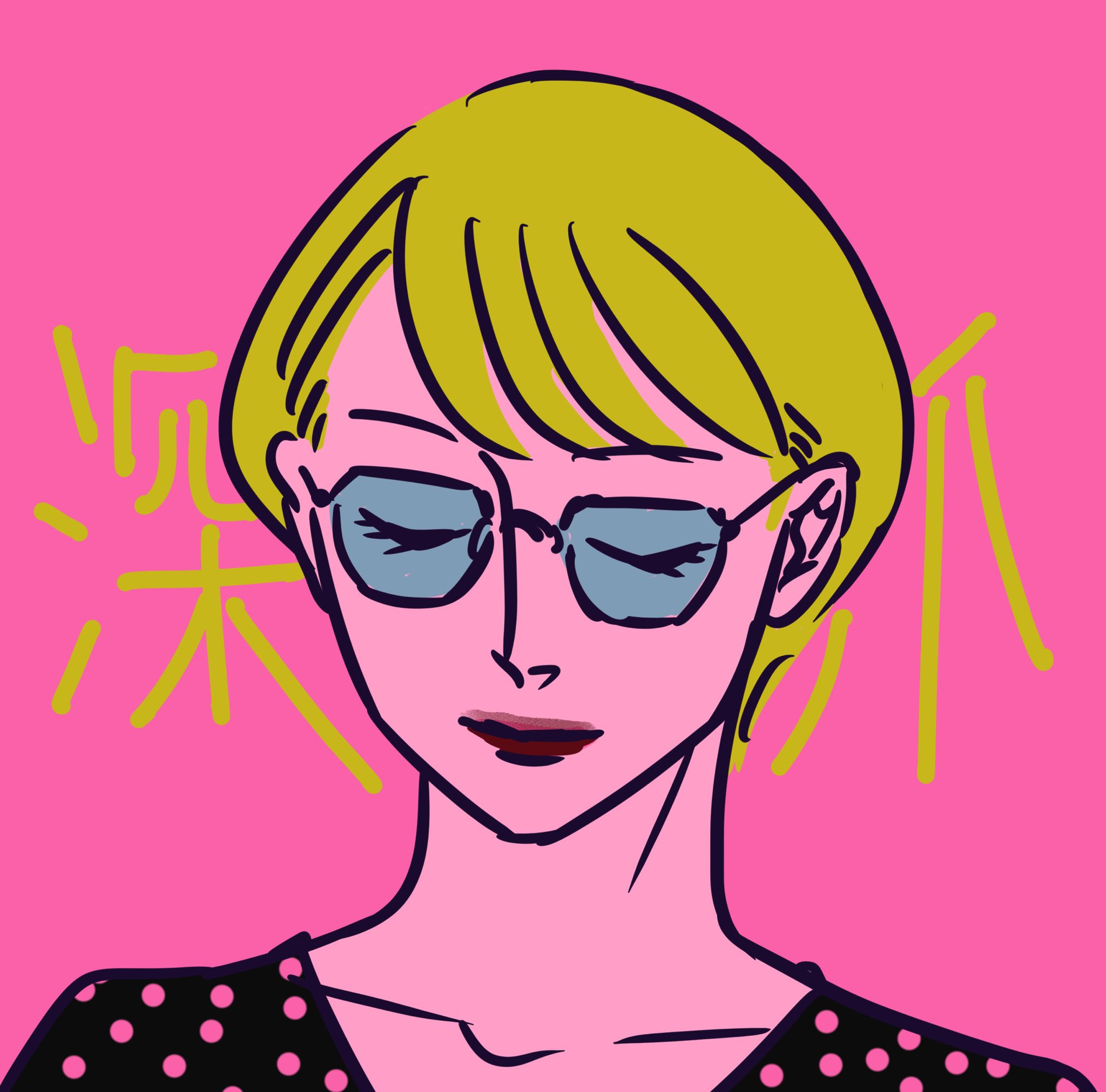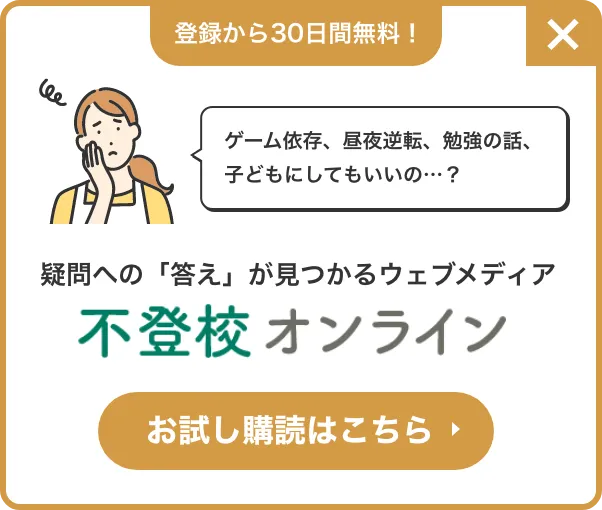コラムニスト・深爪さんが語る「息子の不登校」。不安で涙があふれた日々と、あのとき本当にほしかった言葉
コラムニストの深爪さんは、日々の気持ちや家族へのまなざしを丁寧にすくい上げる文章で、多くの読者の心を支え続けてきました。
そんな深爪さんにも、息子さんの不登校と向き合い、毎日が揺れ続けた時期がありました。
今回、不登校オンラインでは深爪さんに「不登校の子どもと向き合う中で感じたこと」をテーマに寄稿をいただきました。
学校に行けないわが子を前に、どう支えればよいのか分からなくなる――。
あの頃の深爪さんが抱えた不安や自責の念、その中で見えてきた“親として守りたいもの”。
その言葉は、今まさに苦しさの中にいる保護者の方に、静かに寄り添うはずです。
目次
「このまま社会から脱落してしまうのでは…」涙があふれた日々と、胸の奥に広がった恐怖
息子が学校に行けなくなった当初(小学校5年生でした)、もっとも強かったのは「このまま社会から脱落してしまうのではないか」という漠然とした恐怖でした。
朝、楽しそうに登校する近所の子どもたちを目にするだけで涙があふれ、夏休みや冬休みなど長期休暇に入るとほっとする自分に気づくほど追い詰められていました。
息子も小さいながら将来に不安を感じるのか、夜になるとたびたび「明日はがんばって学校に行ってみる」と宣言するようになりました。しかし、朝になると体調が悪くなりランドセルを背負ったまま玄関でうずくまってしまう。
私には「なんでいつもこうなっちゃうんだろう…」と涙をこぼす息子の背中をさすることしかできませんでした。
何度も何度も繰り返されるその光景に「このまま学校にも行けず、社会にも出られず、一生部屋にこもってしまうかもしれない」と最悪の未来を想像して絶望的な気持ちになることもありました。
いつからか息子から笑顔が消えました。大好きなゲームもすることもなくなり、一日中布団にくるまっているような日々が続くようになりました。
どんどん元気がなくなっていく息子の姿を見ているうちに「学校に行かないこと」そのものへの不安よりも「息子の心が折れてしまったらどうしよう」という危惧が胸の奥で膨らんでいきました。
親として守りたいものが何なのかがはっきりと見えてきた時期でもありました。
顔も名前も知らない、不登校経験者の保護者の“リアルな声”に救われた
当時ほしかったのは「解決策を与えてくれる人」ではなく「気持ちを支えてくれる人」でした。身近にはその役割を果たしてくれる人はなかなか見つかりませんでした。