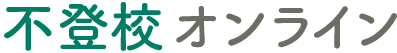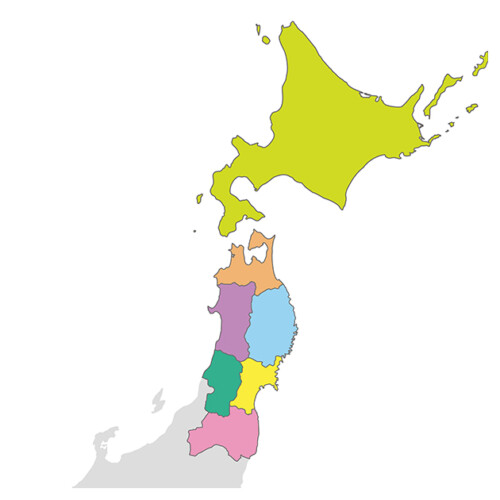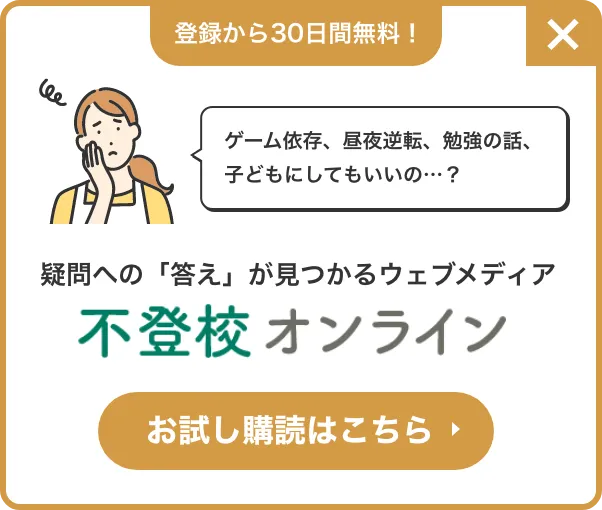あなたの知らない、学校の不登校支援の実情とは?【第1回:小学校の副校長先生に聞く】
不登校について、公立の小・中・高等学校の先生に、キズキがインタビューを行いました。キズキは、不登校・ひきこもり・中退などの挫折を経験した方々のための個別指導塾・キズキ共育塾の運営などを行っています。
今回のインタビューは、主に不登校のお子さんを持つ保護者の方が、学校の不登校支援の取組の利点や限界を理解し、必要に応じて様々な手段を利用できるようになることを目指しています。
学校内外の支援を活用し、不登校からの「次のステップ」を歩むきっかけとなれば幸いです。
また、学校教員として働くことを視野に入れている方も、実務的な視点から学校運営の様子を覗くことができますので、ぜひご一読ください。
全3回でお届けします。
第1回となる今回は、「あなたの知らない、学校の不登校支援の実情とは?~小学校の副校長先生に聞く~」です。
東京都内の公立小学校の副校長先生である、小林明彦先生(仮名/50代)にお話をお聞きしました。
インタビュアー:キズキ 亀山裕樹
目次
不登校の児童は増えている
亀山:ご自身が小学生のころ(1970年代)、周りに不登校の方はいらっしゃいましたか。
小林:当時は「不登校」ではなく「登校拒否」と言っていました。
言い方はともかく、今の自分が認識している「不登校の子どもたち」と同じような子がクラスにいたかというと、記憶にないんです。
今は不登校の児童に対して目も向くし、気持ちも向きます。
ですが小学生のころは、仲のいい友達以外のクラスメイトにはそんなに関心がありませんでした。
で、ずっと来てない子がいたっていう記憶が、僕自身にはないんですね。
「いたのかもしれないですけど、認識はない」というのが正直なところです。
亀山:教員になったときはいかがですか?
小林:僕が教員になりたてのころは、不登校の児童は今ほどには人数が多くなかったですね。
学年に1人か2人くらいで、今よりも珍しかったんです。
だから、不登校の児童は、いるクラスもあればいないクラスもあるって感じだったんです。
亀山:昔は、不登校という「選択肢」自体があまり認識されていなかったから、数が少なかったのでしょうか?
小林:学校に足が向かない児童は、ゼロではないんですけども、絶対数として今より少なかったと思いますね。
今はクラスに1人とかいて、学校に行かないという選択も昔よりは珍しくなくなってきましたね。 【編注:小中学校の不登校児童数は、年々増加傾向。1995年度は81,591人、2005年度は122,287人、2015年度は125,991人となっている(文部科学省. 2017.「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」)】
亀山:不登校の人数が次第に増えていく中で、不登校の児童を特に意識するようになったのはいつですか。
小林:実際に不登校の児童を初めて受け持ってからは、ガラリと認識が変わりました。最初に赴任した学校の、2回目の担任だったかな。
不登校児童への家庭訪問前はビクビクしていたが、話してみたら普通の子だった
亀山:具体的にはどのように変わりましたか。
小林:担任になるまでは不登校の児童と接する場面は圧倒的に少なかったわけで、最初はどう接していいかもわからなかったんです。
不登校の児童の方から学校に来ることがまずないので、彼らが何を考えているかとか、どういう感覚で毎日過ごしているかっていうのが、想像でしかなくて。
そんな状況ですが、児童が学校に来ない以上、自分から児童のところに行って話をする必要があります。
最低でも週に1回、自分から家庭訪問に行くようにはしていました。
現在はなかなか難しいのですが、当時はそういう家庭訪問は普通にできました。
最初に家庭訪問するまでは「どんなふうに接したらいいんだろうか」と思っていましたし、言葉は悪いですけど、はれ物に触るような感じでビクビクしていましたね。
だけども、実際に訪ねて、お部屋に上がると、その児童がどんなことに興味を持っているかがちょっとわかる。
興味があることを話題にしていくと、会話が弾むというほどではないですけど、話もできます。
実際に話してみれば、不登校の児童も「学校に来ない」という部分以外はごくごく普通の小学生と変わらないんだなと実感しました。
不登校の「好転」には、登校日数以外のものもある
亀山:不登校の児童の「指導」経験における成功や失敗についてご教示いただけますか。
小林:何をもって成功・失敗とするか、次第ですね。
単純に登校日数が増えて、学校に足を運ぶようになったことを「成功」とするのか。
もちろん、登校して学校で楽しく過ごせるようになれば、わかりやすい意味での「成功」ですね。
ただ、それ以外は果たして「失敗」なのだろうかと、僕自身はとても疑問に思います。
前述の児童の例で言えば、彼は僕が家庭訪問して関わっていく中で、積極的に学校に足を運ぶようになりはしなかったので、ある意味では「失敗」です。
ただ、それまで彼は部屋の中で過ごしていて、自分が考えていることや興味のあることをキャッチボールする相手がいなかったんですよ。
そこに僕が行って、好きなことを「ああでもない、こうでもない」と言いながら、キャッチボールができるようになってきた。
そういう、独りで家にいるときはできなかったことができるようになったのであれば、学校の出席日数には反映されなくても、その子にとって、何かしら自分の存在を確かめることができるようになって、ある意味では「成功」です。
「こういうものが好きで、こういうものが嫌いだ」って相手に投げかけて、「ああそうかそうか」って僕も返していく中で、自分という人間を客観的に判断していけるようになります。
そんなことも、登校日数とはまた別に、大事なものなのだと僕は思います。
亀山:登校日数に反映されなくても、子どもがコミュニケーションできるようになったのはいいことですね。
保護者としても、無理に出席日数にこだわりすぎずに、子どもの変化をじっと見守る時間も必要かもしれませんね。
亀山:学校の先生としては、やっぱり、登校日数などの「数字」で不登校か否かを判定することになりますか。
小林:そうですね。例えば、年間30日以上欠席している子には、ある書類をつくらなきゃいけないんです。
じゃあ「29日だったら問題ないのか」って話ですけど、ある程度はどこかで線を引かなきゃいけないので、その目安は必要なのかもしれません。
でも、そういう数字で表されるもの以外のいろんな要素もあります。
僕個人としては、不登校というものに対する考え方を、教員自身もその子の立場になって、もっと考えていかなきゃいけないと思います。
公立小学校の教員は「公務員」なので、行政の施策などに則って動かなければいけません。
ですけれども、行政としての視点「だけ」では不十分だと思います。
目の前の子どもにとって、学校という関わりがどの程度必要なのか。
学校以外のものはどの程度求められているのか。
教員である自分には何ができるのか。
そういったことを見極めることは、子どもと直に接する教員として必要な考え方かな、と僕個人として思います。
学校の先生は、もっと多様な考え方を持っていい
亀山:教員に必要な考え方とは、例えばどういうことでしょうか。
小林:例えば、あるお母さんがオルタナティブ教育【編注:伝統的な「学校での教育」以外の教育】について非常に勉強されていて、「自分の子どもは学校外で、オルタナティブ教育で勉強を進めたい」っていう相談を受けたことがあります。
そのお母さんは、「学校なんて意味がない」と思っているわけではなく、むしろ学校には「授業だけでなく、いろんな社会性を養う場」の役割があると、学校の存在をポジティブに認めていました。
その上で、「通学ではなく、オルタナティブ教育がいい」という考えなんですね。
そういう親御さんやお子さんを受け持ったときに、ただただ「学校に来るのか来ないのか」とか一般論をもとに考えるよりも、自分で対応をアレンジして考えることが大事。とにかく自分の頭で考えることが大事だと思うんです。
亀山:従来のやり方にとらわれすぎず、柔軟な考え方を持つことも大事ですね。
小林:はい。学校文化には日本独自のところがあるんです。それにとらわれすぎる必要はないと思いますよ。
日本の学校では、「教科指導+α」として、教科教育だけではなくて「全人格的な教育」を行うという意識がずっと続いているんです。
言い換えれば、「教えること」を全部ひっくるめて、「勉強も教えましょう、身体も鍛えましょう、道徳教育もやりましょう、何かあったらいつでも学校に来てください、ここで全て教えますから」という教育をしているわけです。
しかしこれは、逆に言うと「学校に通わないと、ちゃんとした人間に育たない」という考えにもなるんです。
だから、「全てのことを教わることができる『学校という場所』に足が向かないっていうのは、人としていかがなものか」っていう認識が日本には広がっているんだと思います。
だけど僕はね、それは諸外国から見たらかなり珍しいと思いますよ。
海外では、教科教育は教科のスペシャリストが教えて、生活指導的な面ではカウンセラーやケースワーカーがいる、という完全な分業体制も珍しくありません。
だから、「これまでの日本的な公教育」以外にもやり方はあるはずです。
ただ、近年の日本には、いろんな価値観が入ってきていく中で、学校へ足が向かないっていうことに対しても、理解が進んできていますね。
いろんな考え方、多様性があるってことはすごく豊かなことだと思います。
そして、「不登校」と一概にまとめて呼ばれてしまうお子さんに対して、おしなべて同じような対応をすることが全てだとは思いません。
「不登校の子どもたちに公教育として何ができるのか」っていうことを考えていくことが大事ですよね。
もちろん、どんな考え方にもやり方にも、どうしても限界はあります。
ですけど、少なくとも理解とか認識の部分では、もっと自由度をもっていいかな、とは思いますね。
ちょっと質問から離れてしまいましたけど、僕が今日一番お話ししたかったのはそこなんです。
学校外の支援を受けてうまくいったケースはあるが、学校外の支援を紹介するのは難しい
亀山:ありがとうございます。公教育の枠組みの中だけで不登校の子どものニーズに合わせるのは難しいこともあると思います。
例えばキズキのような、学校外だったり民間だったりの支援組織と連携されることはありますか。
小林:一例として、不登校から引きこもりになった、ある児童がいました。
その児童は学校には来ないままだったんですが、次第に民間の塾に通うようになりました。
その子は、その塾では勉強だけでなく、年上の人といろんな話もしていました。
で、その塾も、その子の塾での様子を学校に逐一知らせてくれるんです。
その子が外に出て行って、興味のあることを広げていったというのは、すごくいいことだと思います。
引きこもることが「絶対的に悪いこと」だとは思わないけれども、少なくとも、学校とも家とも別のところに行って、いろんなことと関わるようになったのはいいと思いますね。
学校外の支援を利用するのも、1つの方法だと思います。
ただし、学校の教員が「こういう民間団体があるんですけど、どうですかね」って言うと、そんなつもりはなくても、「学校・行政の責任転嫁・責任放棄」にもなりえます。
ですから、学校外の支援の紹介は積極的にはしていないのが現状です。
なので、学校外の施設については、親御さんが「この子をどうにかできないか」と思っていろいろ探していく中で、自分で見つけて、利用しています。
また、学校外の支援に詳しくない教員も、一定数いると思います。
積極的に紹介しないにしても、「外部の支援団体がある」っていうことを知識として持って、理解しているというのは、全然違うと思うんですよ。
前述の児童と別に、「学校にはほとんど来れないけど、塾には通っていた」児童がいました。
その児童は、卒業式に向けて、毎日ちょっとずつ、1時間、2時間と来れるようになりました。
残念ながら卒業式本番には来れなかったけれども、卒業式の終わった日の午後に、クラスの子とその子が集まって、2回目の卒業式を自分たちで行ったんです。
その子は、学校に来れない間でも、日常的に起きて電車に乗って、いろんな人と会って関わるということを続けていたわけです。
そういう「生活の基になるもの」が学校とは別にあったので、卒業式までに学校の登校に慣れて、その延長として、特別な1人だけのための午後の卒業式ができた。
その塾がなかったら、そこまでできたかどうかわからないですね。
繰り返しになりますけども、教員が積極的に学校外の支援・教育機関を選択肢として保護者の方に示すのは、現実的になかなか現実的に難しいところがあります。
ただ、知識や理解があるというだけで全然違うと思いますね。
不登校支援コーディネーターの登場で、学校も不登校への理解を深めつつある
亀山:学校外の支援の場に通うことでうまくいったケースもあるということですね。では学校としては、不登校の方を支援するためのどのような制度を整えていますか。
小林:東京都が不登校支援のモデル事業をやっていて、うちはそのモデル校だったので、「不登校支援コーディネーター」がいます。
不登校支援コーディネーターとは、不登校支援に特化して業務を行う教員のことです。
コーディネーターの役割は、うちの学校の例では、
・担任のフォローに回る
・養護の先生の事務的な負担を軽減するために事務の補助員を雇う
・家庭支援センターや教育センターや専門員や児童相談所の人とのケース会議のコーディネート
などがあります。
今のところ、うちの学校では、「コーディネーターのおかげで不登校の児童が登校を再開した」という意味での成功はありません。
ですが、コーディネーターが研修などで得た知識や経験を担任や保護者など学校全体に共有できたことは成功です。
具体的には、前述の、オルタナティブ教育を検討していた親御さんも最初はかなり態度が固かったんです。
「学校の必要性はわかっていますが、うちの子は学校で自信を失っています。だから通学はさせたくありません」という趣旨のことを強い口調でおっしゃっていたんです。
ここでもしコーディネーターの知見がなかったら、学校側は「学校の価値とは」「学校に来る意味とは」みたいな「説得」をしていたかもしれず、そうなると「学校」対「保護者」という、児童本人を置き去りにした状況にもなりかねません。
ですがコーディネーターと担任と僕とで話し合っていく中で、「まず、お子さんの特性についてお母さんから学校側に教えてもらいましょう」ということになりました。
その子を理解しよう、というところから始めたんですね。
お母さんは自分のお子さんだから、育て方でいろいろ苦労しながら知識を得る。
それを我々が理解しようとしている姿勢を示せたわけです。
そうしたら親御さんの態度がとても変わりましたね。
「幅広く相手の側に立って理解しながら、物事を進めていく」というスタンスになれたことはコーディネーターの役割が大きいですね。
亀山:なるほど。コーディネーターはどういった形で知識・経験を共有しているんですか。
小林:特別支援の学年委員会という仕組みがあるんです。
コーディネーターのほかに養護教諭、特別支援教育のメンバー、学年の先生が集まって、悩みを共有する会ですね。
会を通して、解決策を皆で考えたりとかカウンセラーさんにつないだりとかします。
テーマは不登校のほか、生活指導や発達障害など、幅広いですね。
その中で、不登校の子どももどうしたらいいかな、と考えて、各学級の情報がまず学年で共有されるわけです。
その後コーディネーターが全6学年の特別支援の学年委員会に出る。
そうすると、学年ごとのいろんな支援経験が教員全体に共有されるんですね。すごくいい仕組みだと思います。
実は、小学校は学級中心の体制なので、なかなか学級間で情報が共有されないんです。
先生たちは皆プライドがあるから、普段は「困り事」「悩み事」を同僚や上司に言わないことも多いんです。
そういう意味では、特別支援の学年委員会は、「いやー、実はこんなことがあるんです」と腹を割って話す貴重な機会でもあるんですよ。
担任の先生だけでなく、カウンセラーや養護教諭に相談してもいい
亀山:コーディネーターなどの仕組みができたことで、不登校に対して、学校の先生も理解が深まりつつあるんですね。
では、保護者の方がどういう形で相談したら、学校としても受け入れやすいですか。
小林:保護者の方も決して一様ではありません。
「うちの子は学校に行かなくて本当に困るんです」っていう方もいれば、「学校だけが学ぶ場所じゃないでしょ」っていう方もいる。
保護者の方が相談をしたい内容がそれぞれ異なるので、一概に相談しやすい形、というのは思いつきません。
担任の先生に伝えづらい場合は、学校のカウンセラーや養護教諭などに相談してみてもいいと思います。
出席日数・クラス替えなどについて、学校は配慮できる
亀山:保護者から不登校に関する相談があったときに、どのような措置を取っていますか。例えば、卒業の出席日数条件を緩和したり、クラス替えの際に特定の子と同じクラスにしたり、など。
小林:学校ごとに管理職の判断によるところもありますが、うちの場合は、出席日数に関しては、外部の(学校が認めた)不登校支援機関に行った日は全て全日出席としてカウントしています。
あとは、ちょっとでも学校に顔を見せてくれたら、全日出席したことにしています。
だから、何時間以上学校にいたら出席でそれ以下は遅刻早退扱い、みたいなことはしていないです。
それから、特に小学生は自分で環境を変えるのが難しくて、友人関係の影響が大きいので、友人関係で学校から足が遠のくような場合はクラス替えに対する配慮もしています。
関係する児童とクラスを一緒にしたり、離したりということです。
クラス替えができない時期には、班が一緒にならないようにするなど配慮もしています。
どんな子どもも自己肯定感を持ってほしい
亀山:もし学校の不登校支援制度に課題があれば、教えてください。個人的なもので結構です。
小林:最初の話に戻るんですが、そもそも「学校に来るということが善で、学校に来ないという選択が悪なのか」というところが、学校が不登校を考えていく上で大きな課題だと思います。
学校の教員、ましてや管理職が「学校に来なくていい」とは言わないんですけど、でも「学校が全て」かと言うと、そうではないと思う。
不登校の時期に必要な「最大公約数的な措置」は学校で取り揃えています。
でも、それは決して、全ての不登校児童をカバーできる「措置」ではありません。
そして、本当に個人的な考えなんですが、「措置」ではなく、本当に全ての子にカバーしなければいけないものは何かと考えたときに、それは「自分の存在を自分で肯定的に認めてあげられる力」、「自己肯定感を持てる力」を与えることだと思うんです。
子どもに
「自分は大事な存在なんだ」
「自分はいろんな可能性を秘めているんだ」
ということを自覚できるようにすることが、教育の1つの目的なんだと思うんです。
科目の勉強は、義務教育を終えてからでも、働きながらでも、働き終えてからでも、いつでもできるんですよ。
でも、多感な時期に必要なことというのは、「自分の存在を自分で肯定的に認められる」ってことだと思います。
そういう意味で言うと、学校が教科教育や部活動や特別活動を提供している目的も、最終的にはそこに行きつくはずです。
でも、それって必ずしも学校でないと得られないものではないですよね。
もし課題があるとしたら、一人ひとりの教員が、「児童が自己肯定感を身につけるための役割を担っている」という自負を持つと同時に、「果たして学校の支援だけが全てなんだろうか」っていう問いかけを内側に持つことでしょうか。
何も考えずに、「やっぱあいつ学校に来ないからダメだなー」とか思いこむのは、ちょっと違うと思いますね。
ゆっくり大きく、幸せになってほしい
亀山:今現在、不登校の方や引きこもりがちの方へ、何かメッセージがあればお願いします。
小林:現在僕が勤めている学校には、特別支援学級もありますし、難聴の児童のための通級学校もあるんです。
いわゆる「普通のクラス」のほかにもそういうクラスがあって、いろんな子どもたちが一緒に生活しています。
大人は、教員は、子どもをいろんなふうにカテゴライズしていくけれども、「この子の幸せのために本当に大事なことは何なのかな」と常々考えています。
児童としても、「はい、この教育が、どの子どもにも絶対に必要なものです!」と言われても、納得できないですよね。
ある子どもにとって本当に必要なものは、その子どもが自分で見つけなくてはいけません。
ですが、そのためには、判断力や意欲などを学ぶ必要があります。
逆に言うと、大人は、子どもたちに判断力や意欲などを教える必要がある、ということです。
では、子どもたちが「学びたい」と考える熱源になるようなものが何なのかな、って考えたら、それは自己肯定感だと思うんです。
学校で自己肯定感を得られるわかりやすい例としては、
「学級委員になって、すごいね」
「テストで100点とって、すごいね」
「部活の部長になって、すごいね」
などがあります。
ですが、「部活のメンバーは、部長以外はダメな人間か」というと、もちろんそんなことはないですよね。
いろんな場面で、いろんなふうに、自分のことを肯定してほしいと思います。
ゆっくり育つものは、大きく育つ。木もそうですよね。
「明日学校行けなかったらどうしよう」と悩むのはわかりますが、義務教育はたったの9年間で、その後の人生のほうがよっぽど長いんです。
決して慌てることはないですよ。
20歳になる前の人間の過ごし方で、人生は決まりません。
ゆっくりでいいから、その分大きくなる。そういうふうに考えてもらえたらいいな、と思います。
亀山:ありがとうございます。
副校長先生の立場から、学校教育という枠組みにおける不登校支援体制の在り方と課題を中心に、個人的な思いも含めて語っていただきました。
さて、後編のタイトルは、「あなたの知らない、学校の不登校支援の実情とは?~中学校の不登校支援コーディネーターに聞く~」です。
不登校のお子さんや保護者が学校で受けられるサポートや、学校としての不登校支援に対する考え方などについてお伝えします。