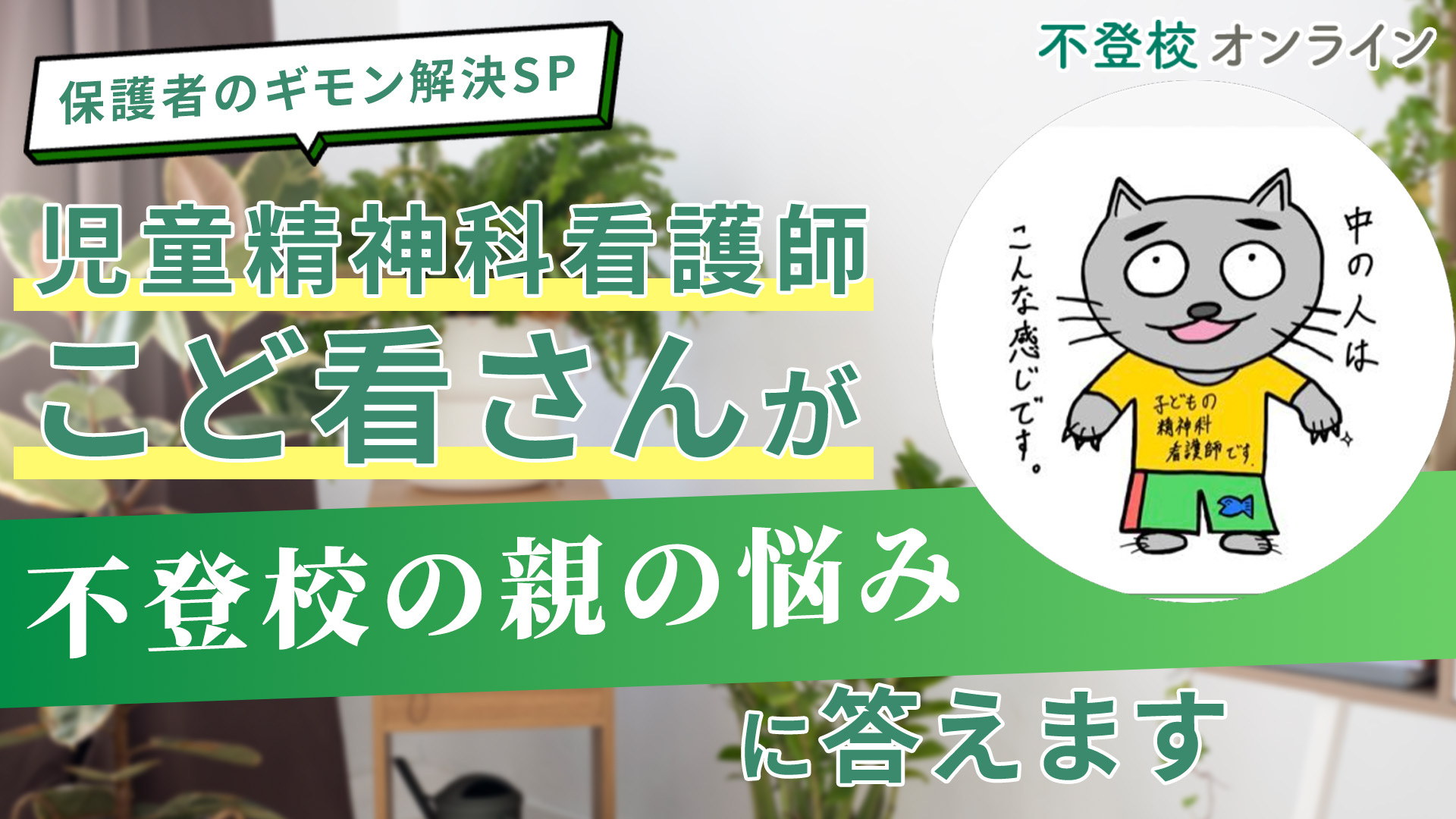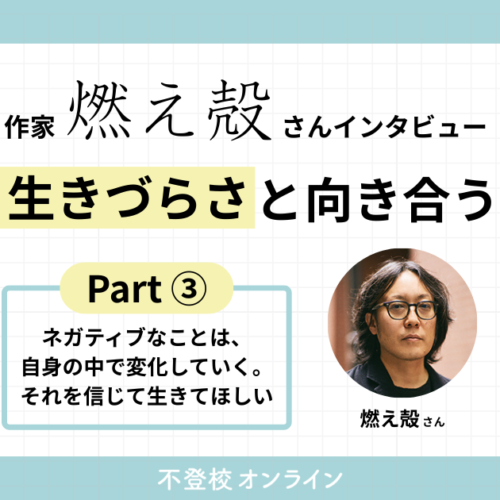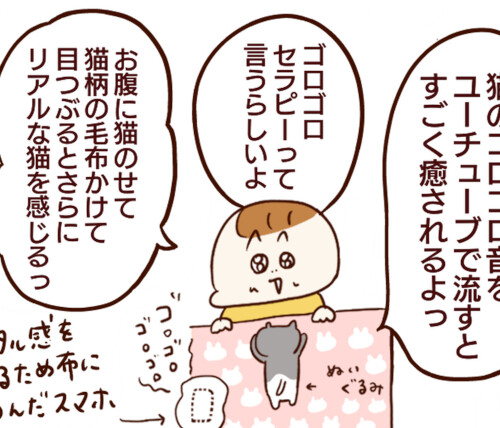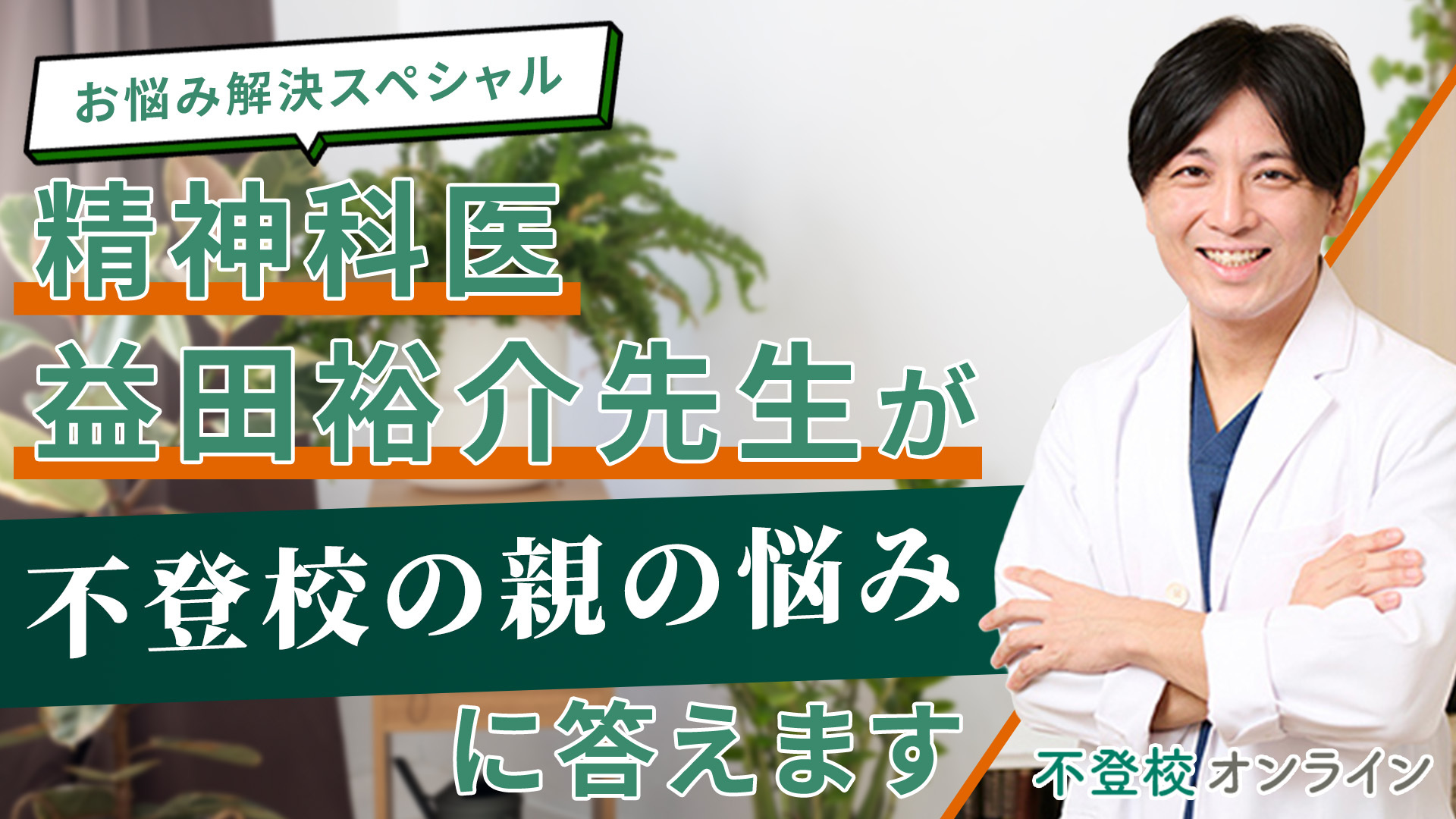
精神科医・益田裕介先生が“不登校の親の悩み”に答えます(2)〜ASD傾向のある子どもに、どのように接したらいい?〜
2025年9月26日(金)、「学校休んだほうがいいよチェックリスト(※)」を運営する3団体が、精神科医・益田裕介先生をお招きして、無料のオンライン講演会を実施いたしました。
テーマは「不登校のプロと精神科医益田先生が答える、不登校のお悩み解決スペシャル」。
オンライン講演会での、不登校のお子さんがいる親御さんからお寄せいただいた質問へのご回答を、全3回に分けてご紹介します(一部の表現は、不登校オンライン編集部が編集を行っております)。
※学校休んだほうがいいよチェックリストとは
子どもが「学校休みたい」「学校行きたくない」と言っているけど、休ませていいのかな?と心配になっている保護者の方に向けたチェックリストです。簡単な質問に答えるだけで、精神科医からの回答結果が届きます。運営は、不登校ジャーナリスト・石井しこう、好きでつながる居場所「Branch」、不登校の子のための完全個別指導塾「キズキ共育塾」の3団体が行っています。
目次
質問4:ASD傾向のある子どもに、どのように接したらいい?
小3の息子は、今年の4月に不登校となったことをきっかけに児童精神科を受診し、ASDの傾向があると診断されました。
親として以前から発達障害的な特性があるかもしれないと感じていたものの、特性が目立たず、これまで受診に繋がらないままでした。感覚過敏やこだわりの強さ、社会的なやり取りの苦手さなど、家庭ではASDの特徴がみられる一方で、知的な遅れがなく、周囲の大人からは、普通の子、真面目な子と思われているように感じます。
今後、本人が少しずつ自分の特性を理解し、得意、不得意を受け入れながら自分らしい方法で社会に適応していってほしいと考えています。このようないわゆるグレーゾーンの子に対して、どのようなタイミング、アプローチで理解を促していけば良いか?そして、親や家庭でどのような関わり方を意識すれば良いか?アドバイスをいただけたら嬉しいです。
伊藤:
まず自己理解っていうことに対して、お子さんにどのように促していくと良いか、コツはございますか?
益田:
小学校3年生だから、自己理解という段階ではまだないのでは、という気はしますね。
そもそも思春期以前には、「自分」というものはあるんですけど、「自己とは何か?」「他者を意識した自分の得意、不得意が分かるような自分の自己・自我」という概念は、あまりないんです。
どちらかと言うと、「万能感があるような自我」であったほうが健康的です。小学校3年生くらいだったら「俺は将来プロ野球選手になるんだ」って言っていて、でも野球の練習は行っていないみたいな子とかいても、それが障害って感じしないじゃないですか。そんなの普通じゃないですか。
だから、自己理解っていうのとはちょっと違うんじゃないかなっていうのが、まずありますね。ただ、「ダメなことはダメ」とか、そういうことをちゃんと教えていく段階ではあります。
かと言って、感覚過敏やできないものとかもあるので、さじ加減を見ながら社会のルールを教えていく段階なのかなという気はしますね。
伊藤:
そうすると一番大切なのは、自己効力感みたいなものを育てることでしょうか。
益田:
そうですね。思春期に突入しておらず、複雑なことはまだ分からないので、どちらかと言うと、愛情たっぷり育てることのほうが大事かなと思います。
愛情をたっぷりやって、本人の万能感を意識しつつ。「こいつ、怠けているからちょっと懲らしめてやろう」とかいうのは、あまり上手くいかないので、万能感はちゃんと持たせつつ。
感覚過敏があるから嫌かもしれないけど、ボディタッチもして。ボディタッチは大事です。
あとは、1に傾聴、2に傾聴、3、4がなくて、5に傾聴ですね。
不登校になった理由も聞かないとですね。何が嫌なんでしょうね?
発達障害的な問題だけで本当に行かないのか?
発達障害が重いからなのか?
それとも学校の「空気」なのか?
たまたまなのか?
家の環境が悪くて、親の喧嘩を見ているから行けなくなったのか?
とか、いろいろ考えていくのがいいかなと思います。
児童精神科医の見立ても大事ですよね。「発達障害傾向があるから、これは学校キツイよね」ということもあるでしょうし、「学習障害や協調運動障害があって、これはキツイよね」というパターンかもしれないし、そうじゃないかもしれないし。いろいろ聞いてみるのがいいんじゃないかなと思いますね。
質問5:学校やバスで吐き気。人に会いたくないので病院にも行けない
伊藤:
高2のお子さんの保護者様です。
学校に行くと吐き気があり、帰りのバスでも気持ちが悪くなり吐いてから学校に行くことができなくなって6月から休んでいます。
車に乗っても家から離れた場所に行くと、手汗、動悸、吐き気が出ます。家の近所の場所なら散歩には行けている。そして、帰るとなると症状が治り元気になります。昼夜逆転もあります。
そして、今は人に会いたくないらしく病院にも行きたがらないです。この状況は見守るしかないのでしょうか?あれこれ考えすぎて私が体調が悪くなり心療内科に行きました。
益田:
疲れだったり体力がなかったりで通学できない子は、都内だと結構います。都内だと1時間かけて学校に行くのが珍しくないんですけど、それに耐えられないんですよね。せっかくいい学校に受かったのに、学校が遠くて通学できない。
混んでいる電車とか、クネクネした道のバスとか、キツイ子はキツイだろうなと思いますね。
このお子さんの場合は、それがトラウマ――医学的な意味のトラウマじゃなくて、日常用語としてのトラウマ――みたいになって、条件反射みたいに、車に乗って吐き気が出るという感じですよね?
対応としてどの形がいいのかっていうのは、難しいですよね。データを取ってみることや、その子が持っている体力の感じも大事です。本当に痩せっぽっちで体力がなさそうな子もいれば、普段は元気いっぱいな子もいますので。
そのあたりは、自分の子どもだけを見ていると分からないので、単刀直入に医師とかと話しながら聞くのがいいですよね。
なお、高校にうまく通えなくても、普通に大学に受かることもあります。大学生になったら、大学には通えるようになった人もいます。入試の形態も総合型選抜などいろいろありますから、何とでもなります。高2なので、通信制高校への転校もありますね。
心配せずに、やれることを考えてもらえばいいかなと思います。
そして、大人になると体力がついてきます。今電車で1時間で通学できないからといって、大人になってもそうとは限りません。
伊藤:
この質問者様は、お母様のほうが、心配しすぎて体調が悪いということも心配です。支える側のお母様の健康もすごく大切だと思うのですが。
益田:
親が「何とかなる」と思わないとダメ、というのはありますね。子どもが自分を受け入れるためには、親がその子を受け入れなきゃいけません。
でも、母親がその子を受け入れるには、お父さんとか周りの親族も「これでもいいよね」と受け入れる必要があります。
皆がちょっと少しずつ力を出し合って受け入れていく、受容していくことが重要です。
質問6:家からもあまり出られない子ども。親はどの程度関わればいい?
伊藤:
中3の保護者様からのご質問です。
中学生の子たちが不登校ですが、家からあまり出られない時期が続いています。親は、見守るときっかけを作るのどちらに重心を置けば良いのでしょうか?更に最近、いろいろやってみたいという小さな芽が出てきたようですが、親はどの程度関わればいいのか分かりません。
益田:
この質問は、「医師だから分かる」「主治医だから分かる」というものではありませんね。
まず重要なのは、データを取ることです。プラス大事なことは、1に傾聴、2に傾聴。聞いてみることです。
あとは、家族会などにしっかり出たほうがいいのかなと思いますね。いい家族会って、昔はこんなになかったんですよ。Branchさんやキズキさんもやっていますよね。
そういうところで「他の家はどうやっているのかな?」っていう、そのN数を増やすっていうのは結構大事ですね。
お医者さんだけじゃなくて、当事者同士とか親同士とかで、「うちの子はこうだったよ」という数を、10とか20じゃなくて100とか200とか集めていくという、データを取っていくっていうのが大事ですね。そうすると、もうちょっと立体感を持って分かったりするのかなと思います。
「どの程度関わればいいのか分からない」という場合は、傾聴ですね。聞いてみる。聞いて、相手を見ていく。聞いたものに応えてみる。対応してみる。
そうしながら、他の親御さんの話とかも聞いていくと、「自分はこうで良かったのかな」というのが分かってきます。
伊藤:
なるほど。何事も日々のデータを取ったり、他のお家はどうしているのかな?という情報を集めたりとか、そういったことが大切ということですね。
益田:
エビデンスのような、「抽象度の高い、こうしたらいいという黄金率」ではなくて、とにかく大量のデータが大事だなと思いますね。
今は、大量のデータを取れるようになったんですよ。キズキさんもBranchさんも、昔はなかったんですから。この10年の話ですよね。
親の会で聞く話は、「どこかで聞いたことのあるような話」だったりするんですけれども、同じ悩みを持っている親御さんから実際に聞くと、全然違いますから。目から鱗というか、パーッと視界が開けます。ぜひ参加してください。
■動画もご覧いただけます
※動画中で紹介しているクラウドファンディングは、現在終了しております。
■関連記事
関連記事