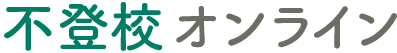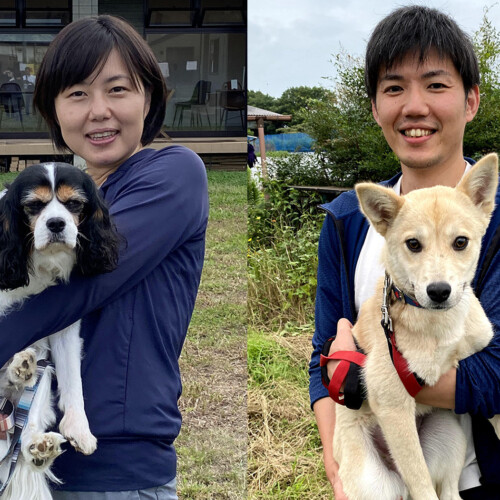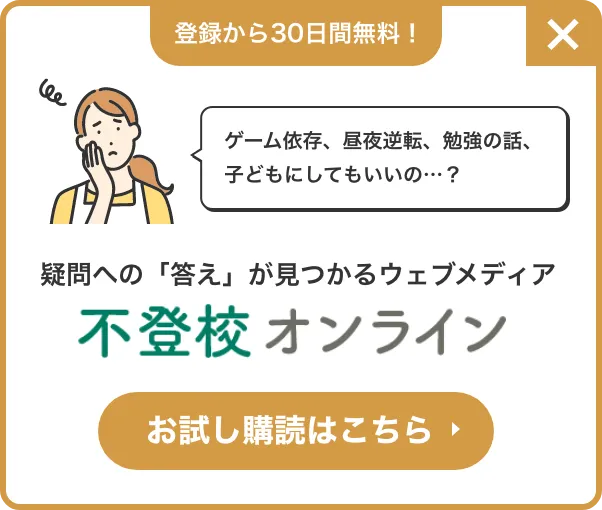『どうか生きてください』樹木希林が亡くなる直前、娘につぶやいた9月1日への思い
樹木希林さんが亡くなる直前まで心を痛めていた9月1日の子ども自殺。その思いを突然、聞かされた娘・内田也哉子さんは「何かできることは」と思い立ち、識者や当事者との対談を行ない、樹木希林さんへの本紙インタビューなどとともに一冊の本にまとめられた(『9月1日 母からのバトン』(8月1日発行/ポプラ社))。今号はその対談のひとつ、本紙編集長・石井志昂との対談を再編集し掲載する。
* * *
内田也哉子(以下・内田) 私が初めて「9月1日」について聞いたのが、母が亡くなる2週間前、2018年9月1日でした。
入院中だった母が病室で窓の外を眺めながら「死なないで、ね……どうか、生きてください」と絞り出すようにつぶやいていたんです。
あまりに突然の出来事に驚きましたが、母は「今日、死ぬ子がたくさんいるのよ」って説明してくれたんです。
石井志昂(以下・石井) そこまで樹木さんが心を砕かれていたのは、なぜなのでしょうか。
内田 あそこまで打ちひしがれていたのは、やっぱり今まさに自分が「死」に向かっていたからなのかな……と。もう長くないことは、お医者様からも伝えられ、1カ月の入院期間中には何度も危篤状態になっていました。
死が現実的に迫ってきたときに、子どもたちが命を絶っていること、そして、たぶん自分の孫や子どもを持って、命の尊さみたいなものが身をもってわかったからこそ、こんなに理不尽な、もったいないことはない、と。
石井 そういうことだったんですね。
樹木希林の最期
内田 じつは、母は亡くなる直前、急に「家に帰る」と言い出したんです。私は「いやいやムリでしょ」と思ったんですが、主治医の先生からは「本当に帰りたいなら、今を逃したらもう帰れないです」と。
そこで病院にも協力をいただき、2日後には家に帰りました。そして母は、家に戻ったその12時間後に息を引き取ったんです。
石井 ええ……!!
内田 「日常のなかで死にたい」とずーっと言っていた願いが叶えられたんですよね。本当に見事な最期でした。
ただ、あのタイミングで「家に帰りたい」と言ったのは、母が理屈ではなく「今だ」と感じることへの感度がすごく高かったからかな、と。
もしかしたら私を育てているときも、いろんな壁にぶつかったんだけど、そのたびに「これは大丈夫」「ここまでは大丈夫」というのを感じ取っていたんじゃないかとさえ思います。
ふだん生きていると、いろんな情報に押しつぶされちゃって、感覚だけでは、なかなか選びきれないじゃないですか。でも母はそれをすごく上手に、75年の生涯だったけれども、やってきたんだろうなあと思います。
石井 この対談の直前に也哉子さんはフリースクールを初めてご覧になられて「ショッキングですね」とも話されていました。印象的だったのは、どんなところだったのでしょうか?
内田 それは私が育ってきた環境もあるんだと思います。というのも、私は母からとても自由にさせてもらっていました。何に対しても「あなたが決めてよ」と。
私が出した結論については、その結果がどうであれ、母から責められることはありませんでした。でも、私にとっては「自分が決めた」という責任はつねに重く感じていました。
だから、私にとって自由は重く感じられるもので、フリースクールでは「授業も子どもたちが自由に選べる」と聞いて、これはシビアだな、と。
石井 なるほど。樹木さんの方針が影響していたんですね。

内田 私がインターナショナルスクールから、「日本の学校に行ってみたい」と公立の小学校に移ったときもそうでした。
小学校6年生の終わりごろに公立に入ってみましたが、すごく合わなかったんです。私という「異物」が突然入ってきたことで、クラスのコミュニティがざわざわしてしまった。
今思えば「いじめ」だったと思いますが、お友だちができないまま数カ月間をすごして、私は毎日泣いて家に帰っていました。
ある日、そのようすを見た母が「何をガマンしているの、やめればいいじゃない」って。たしかに学校はつらかったんですが、私が相談する前から選択肢をバーンと与えられてしまい、とまどったんです。
石井 それだけつらい気持ちのときには、その子の気持ちを受けとめてあげるのが必要だったでしょうね。
内田 そう! 私、全然、受けとめられてない(笑)。母は一貫して「好きなほうを」と言う人でしたので、私としては「世の中的に良いのか悪いのか」を考えて学校へ通い続けようと決めました。
石井 今、「世の中的には」とおっしゃいましたが、その“世の中”を伝える人がどこにいたのか、ということですよね。だって、ご両親は……。
内田 破天荒(笑)。父とはいっしょに暮らしていなかったので、母が大人のロールモデルになっていたと思います。
母は精神の拠りどころを強く持っている人だったので、いつもまっすぐ立っていました。
一方で、小さいころから私は「うちの親はヘンだぞ、あれを基準に考えてはいけない」という危機感もつねにあったんです。
石井 その後、結局、学校には通われたのでしょうか。
内田 卒業式まで通いました。悲しい思いもしましたが、最後まで通って卒業式を迎えたとき、なんとも言えない達成感があったんです。
そこで気持ちが吹っ切れたからか、中学校からは友だちもできて、いじめもなくなり、楽しい中学校生活を送れました。
話は変わりますが、今日、お聞きしたいことのひとつが、いまだに「学校へ行かなければ一人前にはなれない」という感覚は定着しているのか、ということです。
石井さんが不登校をされていた20年前と比べるとどうでしょうか。
石井 私が不登校したときと比べれば不登校の認知度は上がり、「死ぬぐらいなら学校へ行かなくても」という認識も広がりました。
しかし「学校を出なければ一人前ではない」という感覚も強く残っています。
以前と変わらぬ不登校の孤立感
3年前に不登校をした子は、パニック障害が起きて、不登校になりましたが、それでも「行けない自分が許せなかった」と話してくれました。
取材したほとんどの不登校の人は、一度は死を考え、その「死線」をくぐってきています。
そういう意味では「不登校の苦しさ」が根本的に変わったとは思いませんし、だからこそ「9月1日」の夏休み明けに子どもの自殺が突出して多い、という現象が今も続いているんだと思います。
内田 「9月1日」の問題が今も続いているのは切実な問題だと思います。それを踏まえたうえで、現時点で私たちは何をしたらいいと思いますか。
石井 その質問に対して、誰にでも説得力のある回答ができれば、現実はもっと変えられると思っています。正直、答えが見えなくて私も苦しんでいます。
ただ、少なくとも「学校以外の選択肢がない」という現実が子どもを苦しめているのはまちがいありません。「不登校の人がいる」という認知だけでは選択肢にはなりません。
内田 たしかに学校で、「選択肢がありますよ」とは言わないですよね。

石井 ロバート キャンベルさんは「魅力的なハッチ(非常口)が必要だ」と本紙の取材で話されていました。
不登校にかぎらず、教室のなかにも魅力的な非常口はあったほうがいい。クラスの席替えや修学旅行の班決めなどで「あぶれた人」に対する選択肢がないんです。
非常口が見えないことで、子どもからも大人からも余裕を奪っているのかな、と。
内田 私の友だちのお子さんは、ハーバード大学に合格した直後に「ギャップイヤー」(休学期間)をとったそうです。彼は1年間、九州の窯元で修行をしてから入学しています。
本人も親も社会に出ることが遅れる心配よりも「何かに伸び悩む、立ち止まる、疑問を抱く、遊んでみる、転んでみる、模索する。そういうことをやる時間が大切だ」って思ったそうなんです。
石井 すごくよい制度ですね。樹木希林さんは、「ありがたいというのは漢字で書くと『有難い』、難が有る、と書きます。人がなぜ生まれたかと言えば、いろんな難を受けながら成熟していくためなんじゃないでしょうか」と言われていました。
そう思うと、日本でも、もう少し立ちどまれるような設計、それこそ「有り難く生きられる設計」は本気で考えられるべきです。
内田 そうですね。今日はありがとうございました。
石井 こちらこそ、ありがとうございました。(了/撮影:宮家和也)

■『9月1日 母からのバトン』
著者・樹木希林、内田也哉子/発行・8月1日/ポプラ社/協力・不登校新聞、登校拒否・不登校を考える全国ネットワーク、ほか ※お求めは全国の書店にて。
■略歴
内田也哉子(うちだ・ややこ)76年生まれ。文章家、音楽ユニットsighboatメンバー。3児の母。
(初出:不登校新聞512号(2019年8月15日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)