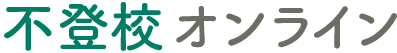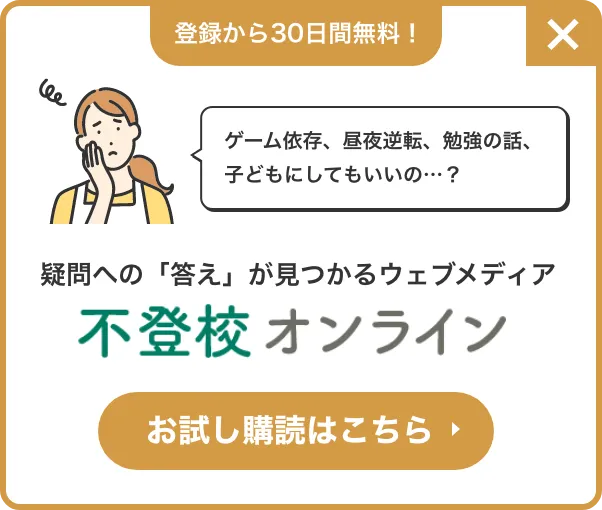漫画家・ちばてつやさんに聞く
今回、子ども若者編集部が取材したのは、マンガ家・ちばてつやさん。ちばてつやさんは旧満州で育ち、その後日本に引き揚げてきた経験を持つ。ちばてつやさんの戦争体験や、戦争を知らない世代に伝えたいメッセージ、またマンガ家になろうと思った経緯などをうかがった。
――ちばさんの戦争体験からお聞かせください。
終戦当時、6歳だった私は、旧満州・奉天というところで暮らしていました。まだ幼かったこともあってどこまで語れるかわかりませんが、少なくとも、戦争が終わったとたんに平和になったわけではありません。戦争の傷跡を引きずりながら5年、10年と飢えの時代を生きてきましたから、そういう意味では戦争体験者ですね。
65年前の話というと、ずいぶん昔のことのように思われるかもしれませんが、私にとってはつい昨日のことのようです。
――当時のことで、とくに印象に残っていることは?
私は放浪癖があってね。ふらっと出かけては、中国人たちの市場に潜り込んだりしていました。私のような子どもがふらふら街中を歩いていても、なんの問題もなかったんです。私が日本人の子どもだったからなんでしょう。なかには、売り物の飴をつまみ食いしてしまう子もいましたが、「ダメだよ~」とたしなめられる程度ですんでいました。
ところが「日本が劣勢だ」という戦況は中国人には伝えられていたのでしょう。日本人を見る眼が次第に変わっていき、売り物に手を出そうなら容赦なく手を叩かれるようになりました。
なかでも一番驚いたのは日本兵への対応です。以前は日本兵が通ると、さっと道を譲ったりしたものですが、わざと肩でぶつかったり、すれちがった後その足元にツバを吐く人もいました。
日本が劣勢だなんて知らなかったのは日本人だけでしたから、あまりの変化にわけがわかりませんでした。直後に日本が戦争に負けたと知り、「あぁ、これが戦争に負けるということなんだ」と痛感しました。
終戦後、すぐにでも日本に帰りたかったのですが、なにせ人が多くて引き揚げ船が足りないんです。船を待つあいだ、私たちを含め、多くの日本人が着の身着のままで中国各地を転々としました。
そのたったひと冬のあいだに、24万人もの人たちが亡くなりました。殺された人もいますが、ほとんどが餓死や凍死でした。
私がようやく日本に戻ってこられたのは終戦の翌年、7月21日でした。中国・大連にある葫蘆島という島から船に乗って九州の博多に到着しました。
父の実家が千葉県・飯岡にあったので博多から列車で向かうわけですが、通る町すべてが完全な廃墟でした。「こんな焼け野原のなかで、どうやって生きていけばいいのだろう」と、子どもながらに感じたのをおぼえています。
そういうなかで新たな生活を始めるわけですから、まさに地獄でした。終戦イコール平和ではない、というのはそういう意味です。食べ物もろくにありませんから、12~13歳くらいまでは、いつもひもじかったですね。
――ちばさんはどんなお子さんだったんですか?
いわゆる”もやしっ子”のような子どもでしたね。家のなかで本を読んだり絵を描いたりラジオを聴いたりと、何日間家にいても平気でした。
ただ、マンガを描くということは、ひきこもらなければできないんです。机に向かってひたすらに描き続けなければ積み重ねられない作業ですから、ひきこもるということは、非常に大事なことだと思うんです。
私自身、もとから引っ込み思案な性格もあって、家のなかで自信をなくしてひきこもっていた時期もありました。
――その後、マンガ家としてデビューされた当初、苦労されたことは?
新人は仕事がありませんから、最初は少女マンガを描いていました。当時、女性のマンガ家はほとんどいなかったので、少女マンガも男性が描いていたんです。私と同世代の手塚治虫さん、石ノ森章太郎さん、赤塚不二夫さん、松本零士さんたちはみな、少女マンガからスタートしています。
私は男兄弟ばかりで、女の子を描くのがすごく苦手で。でも、少女マンガなのに可愛い女の子が描けないなんて話になりませんから、一生懸命描く練習をしました。
――ちばさんのマンガ家としての「核」は、どこにあるのでしょうか?
マンガ家としての「核」ですか。いや、わたしね、「核」がないような気がするんですよ(笑)。
いい絵本を読むと「あぁ、絵本作家になりたいなぁ」って思うし、いい詩を読むと「詩人になりたい」とも思うんです。小説家を目指していた時期もありましたし、音楽家になりたくて手書きで五線譜を書いたりもしました。
でも、イマイチなんです。書いた直後は会心の出来だと思っていた詩も、あとで見直すと思っていたほどよくない。
私が10代のころは小説家にも詩人にもなりたかったんだけれど、どれも長く続かないし、結局なにもモノにならなかったんです。

アルバイトもうまくいかず