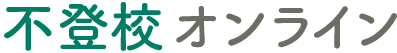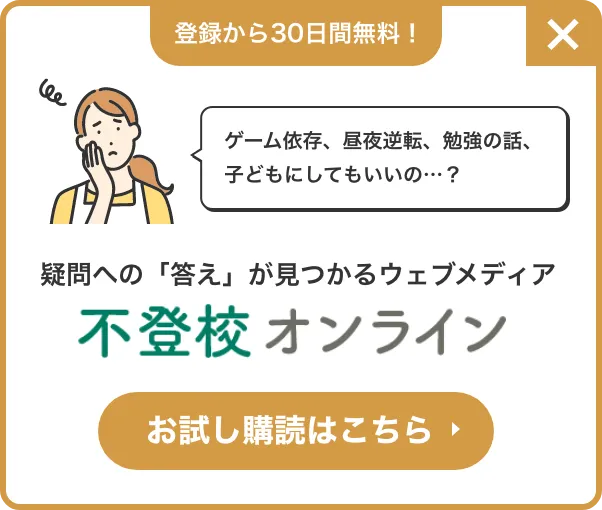ロバートキャンベルが語る不登校 自身のいじめ経験を背景にした提言とは
アメリカ出身の日本文学者・ロバート キャンベルさん。豊富な知識に裏打ちされたコメントがTVでも人気を集める学者だ。キャンベルさんほど日本を外と内から見つめてきた人はいないかもしれない。子どもを取り巻く現状や不登校について、お話をうかがった。
不登校は当たり前に認められる権利
――日本には不登校の子が12万人います。この現状について、どう感じられているでしょうか?
不登校は日常のなかに置かれたハッチ(非常口)だと思っています。ハッチに向かうかどうかは、自分の体と時間の使い道を自立的に決定するということですから、当たり前に認められる権利です。
一方、国際的な調査に照らしてみると日本の公教育は優秀です。アメリカのように格差を生まずに「みんなが同じように」を心がける制度になっています。しかし、「ちがう人」への眼差しや待遇はけっしていいとは言えません。いま大切なのは不登校だけなく、家庭や学校のなかでさまざまなハッチを子どもから見えるようにすることではないでしょうか。
いじめが突如、始まった
――「ハッチが大事」という指摘はご自身の経験も背景になっているのでしょうか?
生まれ育った環境から「ハッチを探す習慣」は私自身に身に着いていますが、一度だけ「まったくハッチが見えない」という経験をしました。それが学校のいじめです。
中学2年生のころ、突如としてそれまで仲間だと思っていた同級生から攻撃を受けるようになりました。待ち伏せされてボコボコに殴られたり、物を盗まれたりすることが続きました。いじめが始まった理由は今でもわかりません。
どうやっても逃げようがなく、まったく出口が見えない地獄のような日々をすごしましたが、突如、母が何かを悟って引っ越しを決めてくれたことで救われました。

魅力的な「ハッチの先」を周囲が示す必要性が
一方で、ハッチが見えていたことによって救われた経験もあります。高校生時代、勉強が手につかず、教室に居づらい時期がありました。しかし、学校外でダンスに打ち込んでいる仲間が見つかって、そこでやりがいを見出していたので気は楽だったんですね。
中学生時代と高校生時代でのちがいは、ハッチが見えたか否か、そしてハッチの先に魅力的な場があったかどうかです。
そうした経験から言えるのは、不登校という大きなハッチだけでなく、あらゆるレベルのハッチが子どもたちから見える必要があると思うんです。地域の同好会やサークル、学校のなかにも保健室や図書室といった「教室とはちょっとちがう場」もあります。ハッチの先に、もう一つの魅力的な世界が広がっていること、これを周囲が示していく必要性があります。
――ありがとうございました。(聞き手・東京編集局 石井志昂)
(初出:不登校新聞467号(2017年10月1日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)