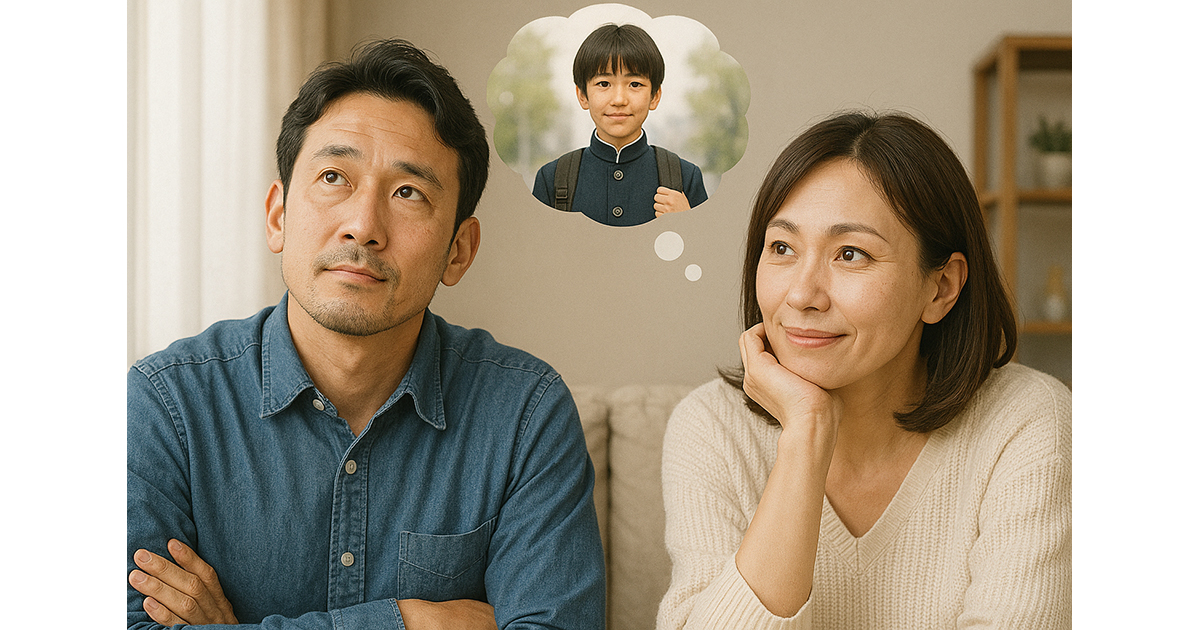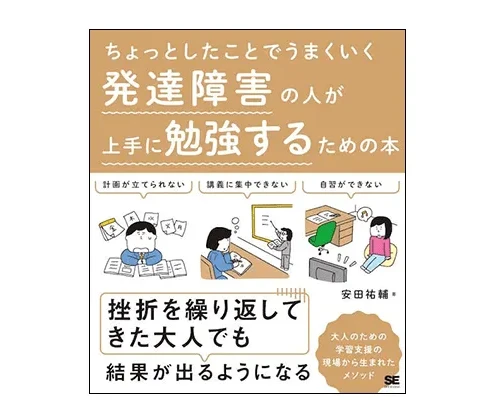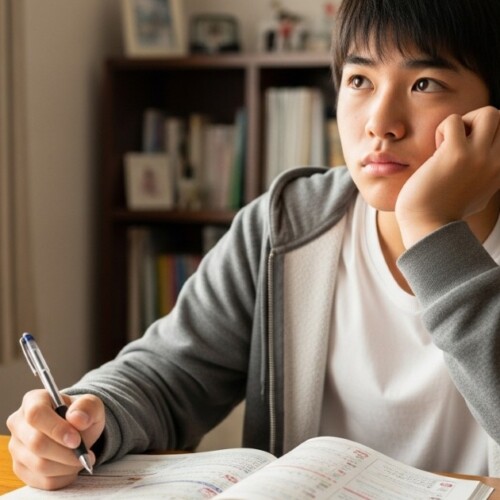【調査報道】「不登校と、親の仕事」のリアル(2)〜働き方を変更した方の自由記述〜
子どもの不登校は、親の働き方にも大きな揺らぎをもたらします。
ウェブメディア「不登校オンライン」は、不登校の子どもがいる親438名にアンケートを実施。結果、約6割が退職・転職・就業、または働き方の変更を経験していました。
この記事では、お子さんの不登校に関連して働き方を変えた方の自由記述と、それに対する編集部の分析・コメントを紹介します(回答は原文ではなく、編集部が類型化・編集を行っています)。
目次
1.働き方の変更につき、役立ったことの詳細を教えてください
回答者:母親50名、父親2名
1. 子どもの状況に応じた柔軟な勤務対応
- 登校可否が当日にならないと分からない中、当日の遅刻や中抜け、急な休みに柔軟に対応してもらえた。
- リモートワークに切り替えたことで、登校の付き添いや早退への対応がしやすくなった。
- 子どもが家にいる日も、在宅で仕事ができたため、精神的にも金銭的にも大きな助けとなった。
- 中抜け対応や勤務時間の変更により、イライラを子どもにぶつけずに済んだ。
2. 介護休暇・休職制度の活用
- 小児精神科医の助言をもとに、介護休暇を申請・取得し、半年間そばにいられた。
- 起立性調節障害などの診断で、休職や介護休暇が認められたことは非常に助かった。
- 有給や介護休暇でほとんど給与が減らず、家計への影響を抑えることができた。
3. 家にいることで得られた変化
- 受験勉強のサポートや昼食の準備ができるようになった。
- 登下校を見守れることで、子どもの変化に早く気づけるようになった。
- 子どもと会話する時間が増え、不安定な時期をともに過ごすことで関係性が良くなった。
- 自分にも1人の時間を確保でき、精神的なバランスが保てた。
4. 勤務形態変更が家族の安定につながった
- 正規職から非常勤・パートに切り替えたことで、夜勤や土日勤務を避けられ、子どものケアに集中できた。
- 勤務時間の短縮で、放課後デイサービスの利用や通院の付き添いも可能に。
- 勤務日数や勤務時間を調整したことで、子どもの精神状態が安定した。
5. 職場の理解と協力が支えになった
- 上司や同僚の理解があり、「お子さん優先で」と声をかけてもらえたことで気持ちが救われた。
- 週2勤務や午前休など、相談の上で働き方を決められた。
- 同伴出勤を認めてもらえたことで、仕事を継続することができた。
- 育児時短制度や社内のシステム(中抜け→残業カバー等)も活用できた。
6. フリーランス・自営業・一人職場での対応
- フリーランスになり、子どもの調子に合わせてスケジュールを立てられるようになった。
- 1人作業の職場だったため、遅刻や早退でも他人に迷惑をかけずに対応できた。
- 勤務時間を自由に組めたことで、学校行事や相談機関の面談に参加しやすかった。
回答者ペンネーム(敬称略):7091、HK、Inkochan、cc、mr、natsumi、t、teruteru、あおかな、あんりんゆ、いっちゃんママ、かいちゃん、かくりん、かなえ、きよぽん、くじら、くにちゃん、くり、こちよ、こつぶ、ぐっさん、さきママ、すー、ちい、ちーちゃん、ちょこぶき、とふ、ともぴぃ、ぴりか、ひなた、ひら、ぶーりん、ぽぽ、まみーB、まるちゃん、まぁ、み、みちみち、みんみん、もも、ゆっこ、ゆもみ、よよよ、らす、りさ、キリム、クープふわ、ジーコ、パオ、ハマチ
2.働き方を変えて「よかったこと」の詳細を教えてください
回答者:母親51名、父親3名
1. 子どもに寄り添う時間が増えた
- 登校・欠席の判断や送迎にゆとりをもって対応できるようになった。
- そばにいることで子どもが安心できる環境を作ることができた。
- 不登校のさまざまなステージにおいて、子どもと一緒に考えたり、新しい一歩に付き添うことができた。
- 子どもと過ごす時間が物理的にも精神的にも増えたことで、関係性が改善された。
- 面談・病院・カウンセリング・福祉関係の手続きにも平日に対応しやすくなった。
2. 自分の心に余裕が生まれた
- 焦って出勤する必要がなくなり、子どもに「行かなくてもいいよ」と言いやすくなった。
- リモート勤務や時短によって、通勤や勤務時間のプレッシャーから解放された。
- 職場のストレスを抱えたまま子どもに接することがなくなった。
- 家にいることで、自分の休養・メンタルケアにもつながった。
- 抑うつ傾向や心身の不調が軽減されたという声も。
3. 子どもへの理解・関わり方が深まった
- 子どもの行動や様子を観察しやすくなり、変化に気づきやすくなった。
- 学習サポートや受験勉強のフォローができるようになった。
- 一緒にフリースクールを探す時間が持て、進路選択をサポートできた。
- 不登校や発達障害に対する理解が深まり、専門分野の仕事にも活かせるようになった。
4. 働くことが気持ちの支えに
- 短時間でも働くことで、自分の時間を持てたり、リフレッシュになった。
- 仕事を辞めるか迷ったが、継続できたことで自分の精神を保てた。
- 職場で必要とされている実感が持て、自己肯定感につながった。
- 子どもに「お母さんも頑張ってる姿」を見せることができた。
5. 子どもの変化や成長が見えた
- 子どもが「休みたい」と言ったときに素直に受け止められるようになった。
- 無理をさせずに過ごすことで、子どもの精神状態が安定してきた。
- 自分の行動を見て、子どもの意識や行動に良い影響があったと感じるという声も。
- 家族全体に穏やかな時間が増えた。
6. 新しい働き方・生き方への視点が生まれた
- 時間に縛られない働き方に切り替えたことで、新たなキャリアへの挑戦ができた。
- 家族のサポート体制を再構築し、夫婦の役割も見直すきっかけになった。
- 一時的に仕事を辞めた後、少しずつ仕事に復帰するプロセスが自信に繋がった。
- 子ども優先で柔軟に生活を整えることの大切さに気づいた。
回答者ペンネーム(敬称略):153、HK、HN、Inkochan、K、m、moco、mr、natsumi、sayuki、t、teruteru、あおかな、あややん、あんりんゆ、いっちゃんママ、かあちゃん、かいちゃん、かくりん、こちよ、ぐっさん、くじら、さきママ、さく、しのぶ、すー、ちい、ちょこぶき、とも、にこ、はるひな、ひなた、ひら、ぶーりん、ぽっぷこーんまる、ぽぽ、まみーB、まるちゃん、まぁ、みちみち、みん、みんみん、めいぷる、ももねこ、ゆきり、ゆもみ、らす、りさ、クープふわ、ジーコ、ジュニママ、ジョゼ、パオ、ハマチ
3.働き方を変えて「よくなかったこと」の詳細を教えてください
回答者:母親54名、父親3名
1. 収入が減った・経済的に厳しくなった
- 介護休暇や休職は無給で、収入が大きく減少した。
- フルタイムから時短やパートに切り替えたことで、月10万円以上の収入減。生活費や学費の工面に苦労している。
- 社会保険料の支払いが継続する一方、収入がゼロの時期もあり、実家の援助に頼らざるを得なかった。
- 子どもの不登校による支出(通院・教材・外出先など)は増え、家計への影響が大きい。
- フリーランスや自営業は、働く時間が減ると直接収入に響く。欠勤が増えた分の補填も難しい。
2. キャリアの停滞・喪失感
- 管理職やマネージャー職を降りることになり、キャリアが断絶。昇進のチャンスも逃した。
- 勤務日数が減ったことで、新しい業務のチャンスが減り、職場での役割も縮小された。
- 長く勤めた仕事から離れたことで、キャリア再構築への自信が持てなくなった。
- 非常勤に変わったことで、社会保険や将来の年金にも不安を感じている。
3. 職場での居場所・人間関係の変化
- 休職や働き方変更後、職場での居場所がなくなったと感じる。
- 周囲に「迷惑をかけている」という意識が常につきまとい、気を遣ってしまう。
- 在宅勤務などで査定が下がる通達があり、自分の価値が下がったように感じた。
- 職場の理解があっても、制度面の制約や同僚の本音にギャップがあり、居心地が悪くなった。
4. 精神的なストレス・葛藤
- 「キャリアをあきらめるしかない」と感じたときの無力感や悔しさが大きかった。
- 子どもと一緒にいる時間が増えたことで、すべてを自分が担わなければならないというプレッシャーが強くなった。
- 子どもの状態が改善しない中、仕事もできずにいることへの無力感から抑うつ状態に。
- 「この対応が本当に子どものためになっているのか」と迷うことが多く、自責の念に苦しむ。
5. 生活・家庭内での負担増
- 家事・育児の全負担がこちらに集中し、夫の協力のなさにストレスを感じる。
- 家族のスケジュール調整でパートナーと衝突することが増えた。
- 子どもと過ごす時間が長くなりすぎた結果、親子双方の距離感が近くなりすぎて疲れてしまった。
6. モチベーション・仕事への意欲の低下
- やりがいのある仕事を任されなくなり、モチベーションが下がった。
- 自分がやりたかった仕事にチャレンジできず、「自分らしさ」を発揮できていないと感じる。
- 職場復帰後も常に遅刻・欠勤の不安があり、気持ちが安定しない。
回答者ペンネーム(敬称略):153、7091、HK、K、Sakukae、Taka、kmama、moco、natsumi、t、teruteru、あんりんゆ、いっちゃんママ、おけい、かあちゃん、かいちゃん、きよぽん、くじら、くにちゃん、こはく、ぐっさん、さきママ、しのぶ、すー、たけ、たつ、ちい、ちほ、ちょこぶき、ともぴぃ、とふ、にこ、なるなる、ぱんだうさぎ、ひなた、ひら、ぽっぷこーんまる、ぽぽ、まくた、まご、まみーB、まるちゃん、まぁ、みずき、みちみち、みん、みんみん、もも、ゆもみ、らす、キリム、クープふわ、ジュニママ、ジョゼ、パオ、ハマチ
4.働き方の変更の職場への相談について、詳細を教えてください
回答者:母親69名、父親5名
1. 柔軟に対応してもらえたケース
- 子どもの送迎や留守番への不安を理由に、時短勤務・リモートワーク・休暇取得を相談し、柔軟に対応してもらえた。
- 上司や社長、同僚の理解があり、「子ども優先でいい」と言ってもらえたことが励みになった。
- フリーランスや裁量労働制で、自身の判断で働き方を調整できた。
- 面接時点で不登校のことを伝えていたため、配慮を前提に働くことができた。
- 週1出勤や一時的な長期休暇など、自身の精神的安定にも配慮した提案を受けた。
2. 相談した結果、一定の調整はできたが限界も
- 勤務時間の変更やシフト調整はできたが、他のスタッフの負担が増えたことで肩身が狭くなった。
- 一時的に理解を得られても、状況が続くと昇格見送りや降格、減給などに繋がった。
- リモート勤務の実現には時間がかかり、派遣元→派遣先→本部といった段階を経る必要があった。
- 有給やフレックスなどを希望しても制度がなかったため、やむを得ずパートへの切り替えを行った。
3. 相談がしづらい・制度上の壁があった
- 職場の制度(育児時短・休職など)が不登校には適用されず、要望書や労基への確認が必要だった。
- 人手不足や業務の性質上、相談はしづらく、代替要員が見つかるまで辞められない状況もあった。
- 育児休職やフレックス制度が整っておらず、職場に改善を求めても受け入れられなかった。
- 子どものことを話すことで周囲に“気を使わせる”ことへの抵抗があり、初めは伝えられなかった。
4. 相談せざるを得なかった背景や経緯
- 学校や病院から職場に頻繁に連絡が入っていたため、事情を隠しきれず相談に至った。
- 登校してもすぐ早退の連絡が来る、登校できない日が続くなど、日々変化する状況に対応が必要だった。
- 家族や自分自身のメンタル不調もあり、制度利用や働き方の見直しを申し出た。
- 事務職や管理部門の理解が乏しく、自ら根拠を調べて制度利用に至った。
5. 職場環境や関係性が相談のしやすさに影響
- 子育て世帯が多い職場であったり、職場内に不登校経験のある親がいたため、相談しやすかった。
- 社長や弁護士、学校との交渉にまで職場が協力してくれたケースもあった。
- 上司や事務担当が退職したことで、理解者がいなくなり、やむなく一緒に辞めた。
- 家族ぐるみの関係がある職場では、状況をよく理解してもらえた。
回答者ペンネーム(敬称略):153、7091、HK、HN、Inkochan、KO、kmama、mr、natsumi、saka、sayuki、Sakukae、t、teruteru、あおかな、あんりんゆ、いっちゃんママ、おけい、かあちゃん、かいちゃん、かくりん、かな、かなえ、くじら、くにちゃん、くり、こいけ、こつぶ、こちよ、こはく、しょーい、すー、さきママ、さく、たつ、ちい、ちーちゃん、ちほ、ちょこぶき、ともぴぃ、にこ、のん、ぴりか、ひなた、ひら、ぶーりん、ぽう、まくた、まみーB、まるちゃん、まぁ、みずき、みちみち、みっこ、みん、みんみん、もも、ゆきり、ゆっこ、ゆもみ、より、よよよ、りさ、りんご、らす、オイルヒーター、クープふわ、ケイコ、ジーコ、ハマチ、夏奈
5.編集部の分析・コメント
子どもの不登校をきっかけに働き方を変えた親たちは、「家庭を守るために現実的な再設計を行った」と言えます。
遅刻・中抜け・在宅勤務などの柔軟な勤務対応は、子どもの安心と家庭の安定に直結していました。特に、「そばにいられることで関係が良くなった」「朝の会話が増えた」といった変化は、単なる勤務調整を超えた“家族再生のプロセス”を示しています。
一方で、「収入減」「キャリア停滞」「居場所喪失」といった代償も明確です。
正社員からパートやフリーランスに切り替えた人の多くは、経済的・社会的基盤の揺らぎを抱えながら、それでも「後悔はしていない」と語ります。
子どもの不登校を支える過程は、親自身のメンタル回復や生き方の見直しにもつながっていました。
「職場への相談」をめぐっては、理解ある上司や柔軟な企業文化に救われたケースがある一方、「制度の壁」「周囲の目」「長期化による不利益」に悩む声も目立ちました。
現行の育児・介護制度では不登校対応を想定しておらず、「理解があっても制度がない」ことが大きな壁になっています。
働き方を変えた親たちは、キャリアを手放したのではなく、家庭の安全と子どもの回復を最優先に据えた結果として新しいバランスを探したのです。
不登校支援を“家庭だけの問題”に閉じず、職場や社会の側から支える仕組みづくりが急務だといえます。
6.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント
今回の調査は保護者様を対象に行っており、働き方を変更した方々のリアルな声が届いています。
一方、私たちキズキ共育塾の現場では、お子さん側の声も拾っています。
「親が自分に真剣に向き合ってくれているのが分かり、直接は言えないけれど感謝をしている」
という声や
「自分のせいで親が仕事をやめることになってしまったのでは」
という罪悪感やプレッシャーなど
お子さんの意見も、保護者様と同じようにポジティブとそうではない意見両方に分かれています。
お子さんによって感じ方は千差万別ですが、
感受性が強く、だからこそ疲弊して不登校の状況にあるというお子さんの中には、親御さんの状況を見て申し訳なく思っているというケースがとても多いように感じています。
どんな選択も間違いではありません。
だからこそ、どんな方向に進んでも、お子さんが「自分のせいで親を振り回してしまった」と思わないような工夫が必要です。
7.「不登校と、親の仕事」のリアル〜関連記事一覧〜
今回のアンケートの関連記事は、下記でご覧いただけます。
関連記事