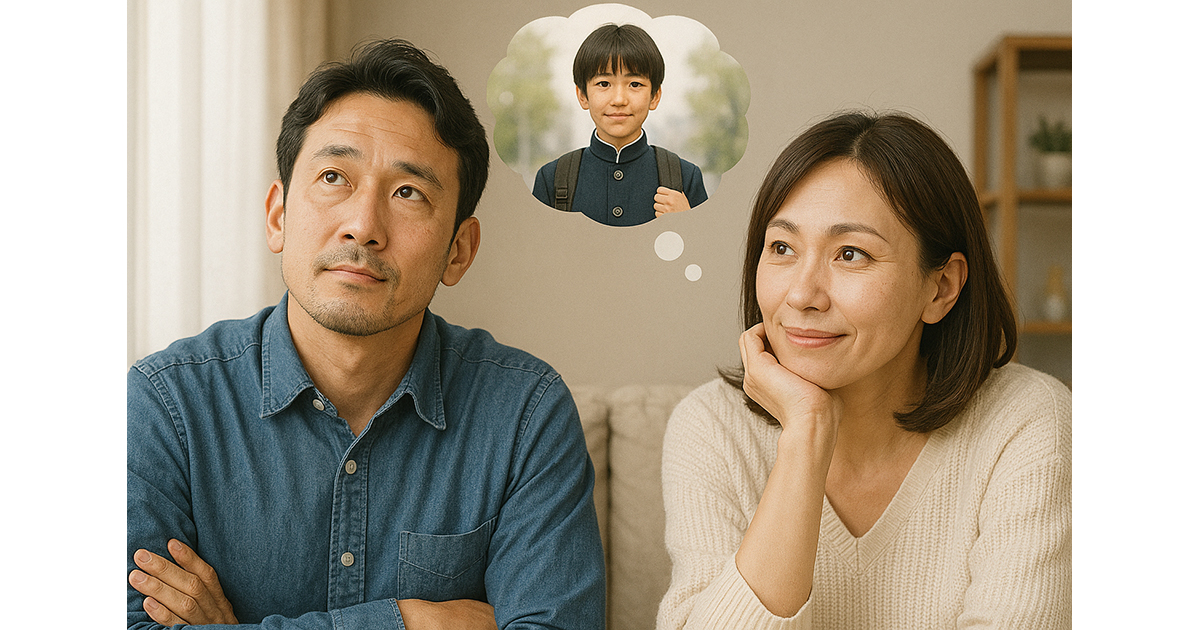【調査報道】「不登校と、親の仕事」のリアル(4)〜就業した方の自由記述〜
子どもの不登校は、親の働き方にも大きな揺らぎをもたらします。
ウェブメディア「不登校オンライン」は、不登校の子どもがいる親438名にアンケートを実施。結果、約6割が退職・転職・就業、または働き方の変更を経験していました。
この記事では、お子さんの不登校に関連して就業した方の自由記述と、それに対する編集部の分析・コメントを紹介します(回答は原文ではなく、編集部が類型化や編集を行っています)。
目次
1.就業した理由について、詳細を教えてください。
回答者:母親10名
- 「社会性がなくなる」と言われたことをきっかけに、近所の子どもたちが集まれる環境づくりや地域の祭りへの参加を通じて、自分自身も外とつながる場を持ちたいと思った。
- 24時間365日、精神的に不安定な子どもとずっと一緒にいることが苦しくなったため、心の余裕を保つために就業を選んだ。
- 高校進学を控えた時期で、家計的に収入が必要になった。
- 理由は主に2つ。1つは子どもと離れるため。ずっと家にいるとお互いに干渉しすぎてしまい、関係が悪化しそうだったから。もう1つは自分だけの時間を持ちたかったため。家にいると常に親モードになってしまい、気が休まらなかった。
- 不登校の子どもと同じ空間にいると、心配や不安から気持ちを探ろうとしてしまい、結果的に子どもを追い詰めてしまった。適度な距離を保つためにも、時間的に離れる必要を感じた。
- 周囲から「外に出た方がよい」と勧められたこと、自分の時間や収入が少しでも確保できれば心の余裕につながると感じたことが理由。
- 子ども自身がある程度安定してきたタイミングで、高校進学に備えての費用も考え、就労を決めた。
- 子どもの将来の選択肢を広げるためには、一定の経済力が必要であると感じた。働かなければ選べない現実があると気づいたから。
- 四六時中一緒にいることで、酸素が薄くなっていくような感覚に陥った。自分の呼吸ができる場所、自分のための時間がどうしても必要だった。また、子どもに過干渉になってしまっている自分にも気づき、少し距離を置きたかった。
- 在宅で働くスタイルを子どもに見せたかったことがきっかけ。在宅での開業準備中に子どもの不登校が始まり、一時中断したが、自分の世界を持ちたいという思いが強く、準備を再開し開業に至った。
回答者ペンネーム(敬称略):あお、あおましいろ、ふくちゃん、まぁしゃん、みなこ、れんげ、カエル、プリン、ほしの、咲
2.就業して「よかったこと」の詳細を教えてください。
回答者:母親10名
- 子どもたちが「その頃がとても楽しかった」と、今でも思い出を語ってくれる。
- 職場が保育園だったため、相談もしやすく、比較的柔軟にシフト対応をしてもらえた。子どもと離れる時間ができたことで、以前より安定して関われるようになり、親子ともに「少し頑張る時間」を持てた。
- 専業主婦として家にいた時は、子どもと一緒に過ごすことだけを考えていたが、就業して家を空けるようになったことで、子どもも一人の時間を充実させて過ごせた。結果的に精神的に安定していった。
- 気分転換になったことで、気持ちに余裕ができ、子どもにおおらかに接することができるようになった。その結果、子どもにも笑顔が増えた。金銭的な面を重視していたわけではないが、臨時収入もやはり嬉しかった。
- 学校で働いているため、先生や学校のことをよく知ることができた。また、自分の子ども以外にもさまざまな特性を持った子どもがいることを学べた。
- 収入があることで心に余裕が生まれた。子どもの様子を「見過ぎる」ことを防げ、自分の時間も持てるようになった。子連れ出勤が可能な職場なので、不登校の子どもも連れ出すことができた。
- 子どもが不安定な時期は地域活動などで将来的な収入を模索していたが、就労できたことで安定収入が得られ、精神的に安心できた。 自分のやりたいことに取り組む時間を持てている。
- 職場の人たちがみな子育てを経験していることもあり、事情をよく理解し柔軟に対応してくれる。仕事自体も楽しく、自分にとってのリフレッシュになっている。
- 働く姿を子どもに見せたことで、「自分を守りながら働くこと」について子ども自身が考えるきっかけになっているように感じる。
回答者ペンネーム(敬称略):あお、あおましいろ、ふくちゃん、まぁしゃん、みなこ、れんげ、カエル、プリン、ほしの、咲
3.就業して「よくなかったこと」の詳細を教えてください。
回答者:母親5名
- 自分も子どもも「一緒に頑張る時間」として就業を選んだが、結果的に子どもにとっては負担だったかもしれない。
- 就業によって時間的な拘束が生まれ、自由が利かないことに不便さを感じている。
- 家事が手抜きになり、掃除もまったくできていないため家の中がホコリだらけ。ただ、家族の誰もあまり気にしていないので「まぁいいか」と思っている。
- 下の子の世話も必要だが、自分の時間も欲しくて、心身のバランスがうまく取れないことがある。
- 三女がまだ就学前ということもあり、彼女の対応や家事の負担が、本人たちにとってやや想定以上に増えてしまっている。
回答者ペンネーム(敬称略):あおましいろ、まぁしゃん、れんげ、プリン、咲
4.編集部の分析・コメント
この自由記述から見えてくるのは、「就業=経済的理由」だけではなく、心理的距離を保ち、家庭を健全に維持するための“セルフケアとしての就業” という側面です。
多くの回答者が語るのは、「ずっと一緒にいることのしんどさ」や「自分の時間を持てない苦しさ」。不登校の子どもに寄り添うことは、親自身のエネルギーを大きく消耗させます。その中で「働く時間」は、社会との接点を取り戻し、呼吸を整えるための大切な時間になっていました。
一方で、「家事が回らない」「下の子への負担」「子どもにとっての負担だったかも」という声もあり、就業が必ずしも解決策ではないことも示されています。重要なのは、働くことそのものではなく、親自身が“自分の心と時間を取り戻す方法”をどう選ぶかです。
親が自分の世界を取り戻すことは、子どもを安心させる第一歩にもなります。就業は「親が立ち直るための選択」であり、その姿が結果的に、子どもに「自分を守りながら生きていく力」を見せる機会にもなっていました。
5.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント
今回の調査では
「ひとりの時間や外の社会と触れる時間が息抜きになった」
「ずっと親子で一緒にいるとお互いに干渉しすぎてしまうため健全に距離をあけることができた」
上記のような意見がありました。
それは、お子さんの側に立っても同じ気持ちである場合が多いです。
不登校のお子さんに”親御さんへの想い”を質問するとよく聞かれるのが「申し訳ない」という気持ちです。
保護者さまに直接言うことは難しくても、私たち第三者の不登校相談員にはこのような気持ちを話してくれることがよくあります。
「自分のせいで親の活動が制限されているかも」
「自分のせいで家族が楽しくなさそう」
こういった思いを持っているお子さんは少なくありません。
その中で、保護者さま自身が働いたり、趣味に打ち込んだり、自分の時間を持つ様子を見せるとお子さんが安心するきっかけにもなります。
つまり、保護者さまが自分の人生を大切にすることは、不登校サポートの大きなカギになるのです。
6.「不登校と、親の仕事」のリアル〜関連記事一覧〜
今回のアンケートの関連記事は、下記でご覧いただけます。
関連記事