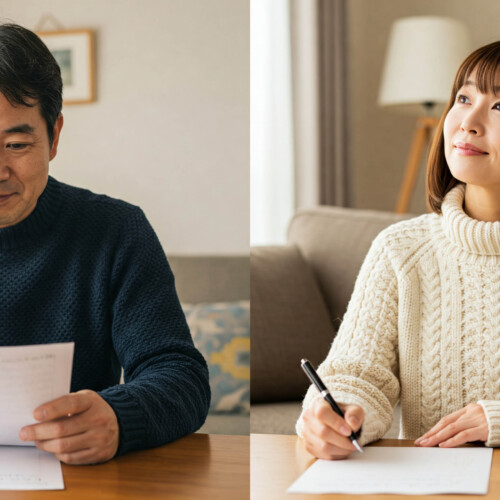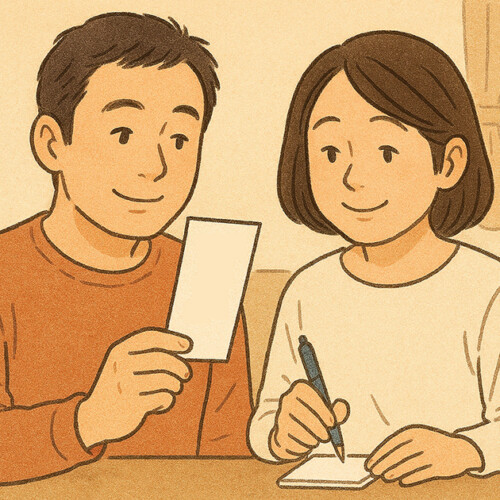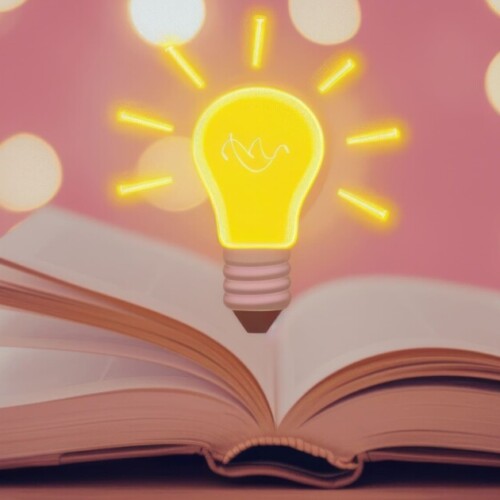実際どうなの? 「学びの多様化学校」経験保護者が語るリアル
「不登校オンライン」では、子どもの不登校・行き渋りを経験している保護者を対象に、学びの多様化学校に関するアンケート調査を実施しました。
「学びの多様化学校」経験者のリアルな声から、学校の魅力や課題が見えてきました。少数派だからこその貴重な経験談、ぜひ参考にしてください。
前回記事
9割が「通わせたい」と回答 「学びの多様化学校」アンケート結果
学びの多様化学校で迷う保護者たち「うちの子に合う? 合わない?」
目次
1. 学びの多様化学校「入学申請中」の方の声
アンケート回答者のペンネーム・いとさんは、小学校6年生のお子さんの保護者です。今回の調査でただ1人、学びの多様化学校への入学に向けてアクションを起こしているお立場でご回答いただきました。
入学申請した理由
説明会に行き、子ども本人がこの学校に行きたいと言ったので、申請しました。また、「子どもが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせます」といった説明に私も魅力を感じました。
学びの多様化学校に対するご意見・お考え
毎日通学することが基本で、さらに申請する際に「人数が定員よりオーバーした場合には、毎日通学する意思のある子を優先します」との説明を受けました。
申請はしたものの、本人も毎日行けるかどうか不安やプレッシャーを感じています。週に何日かだけ登校するということも、オプションで選択できるといいと思います。
2. 学びの多様化学校へお子さんを通わせたことのある保護者の視点
学びの多様化学校の「よかったところ」
※以下、各コメント末尾の( )内は回答者のペンネーム・お子さんの学年・現在の在籍状況。
学校の対応。無理をさせない。先生方が熱心。多くのスタッフがいらっしゃる。カウンセラーがほぼ毎日いらっしゃる。体験を重視した教育計画。決まりの遵守。(アラビアータさん・中学校2年生・卒業)
子ども一人ひとりに合わせてくれる。一人の子どもに対して、複数の先生が見守ってくれている安心感がある。子どもたちのやりたいことを尊重し、臨機応変に対応してくれる。(みー母さん・小学校3年生・在籍中)
本人がやりたいと思うことをある程度やらせてもらえる。学年問わずに仲良くなれる。(yuriさん・小学校5年生・在籍中)
本人のやる気を買ってくれて、成績をとても良くつけていただき、進学に有利になった。クラス人数が少なかった。(ひゅーまさん・中学校3年生・在籍中)
わが家の息子は、不登校ではありませんでした。学習障害のため、読み書き中心の学校の授業のテンポについていくことが難しく、息子のためにできることを探していた時に、「不登校特例校」の存在を知りました。
はじめは、不登校じゃないと入れないと思っていたのですが、見学に行き、お話を聞き、不登校じゃなくても入れると初めて知りました。
イエナプランを取り入れたカリキュラムが組まれていますが、先生方の対応が、子どもたちと横並びで接してくれるので、どの子も安心して過ごしていると思います。
保護者との距離感も、今までの縦の関係ではなく、伴走者のような関係です。親子共々安心して通うことができています。(ikoさん・小学校6年生・在籍中)
「学校へ行かなくてはいけない」や「みんなと同じことをしなくてはならない」といったことを無理強いしないで、子どものペースに合わせられる。(SAさん・小学校5年生・在籍中)
一人ひとりの特性を理解し、適切なコミュニケーションをとってくれる。個別の学習内容なので、それぞれの学習レベルに合った学びができる。ゆとりのある時間割と環境で子どもたちそれぞれのペースで過ごせる。(こーたママさん・小学校4年生・在籍中)
不登校経験のある子や、発達特性のある子など、さまざまな生徒がいること。自宅からオンラインで授業が受けられること。先生方が個々の生徒に合わせた丁寧な関わりをしてくださること。(まるまるだんごむしさん・中学校2年生・在籍中)
想像していた以上に素晴らしい学校です。教育課程や日々の学習もよく、本人も楽しく通わせていただいております。(アクアさん・中学校1年生・在籍中)
子どもに無理強いをしない。様子を見て声をかけてくれる。活動に参加したくない子、したい子どちらにも対応できるような方法を考えてくれている。不登校で病んだ親のケアにも力を入れてくれている。(晴れパンさん・小学校1年生、3年生・在籍中)
子どもの意見に寄り添い、上からの指導ではなく共に歩いていく感じでいてくれたこと。子どもの好きなことの話を聴いてくれたこと。勉強は強制しないところ。「やってみたい!」と言ったことは叶えてくれるところ。保護者会学習会があり不安を共有できたところ。(15歳のくまさんさん・中学校3年生・在籍中)
遅刻や早退、お休みをした時に、クラスメイトは何も聞きません。みんなそれぞれいろんな理由があるのを分かっていて察してくれます。(シーソーさん・中学校2年生・在籍中)
わが子や学びの多様化学校へ通っている子どもたちを見ていて感じることは、不登校の子どもたちが学びたくないわけではないし、学校へ行きたくないわけでもないということです。
学びの多様化学校は、そんな子どもたち一人ひとりにあった学びを提供しているところが、素晴らしいと思います。(takatakaさん・中学校1年生・在籍中)
子どものペースに合わせて対応してくださる。人との関わりがあったかい。いろんな先生方に見ていただいている。よいところをたくさん見つけてくださる。少人数だからこそできる行事や遠足の機会を多く作ってくださっている。(たこやきさん・小学校5年生・在籍中)
学びの多様化学校の「よくなかったところ」
通常校と比べて授業時数、内容が少ないこと。(アラビアータさん・中学校2年生・卒業)
授業料などの費用がかかるので、公立校と比べてしまう。(みー母さん・小学校3年生・在籍中)
学習の内容が個人で違うのでプリント学習主体になっているところ。一人ひとりへのサポートが難しい。(yuriさん・小学校5年生・在籍中)
なんとなく勝手に、スタッフがみんなカウンセラーのように寄り添う気持ちを持っていると、期待して転校したが、まったくそんなことはなく、みんなドライで、悩みごとや揉めごとがあっても、特に問いかけもフォローもない。商売として「学びの多様化学校」をしている感じ。
ニーズがあり、注目を浴びている分野ということは、利益目的ということが起こっても仕方ないのだと、感じた。
うちに限って言うと、地元の学校の先生の方が、よほど子どもを理解しようとしてくれた。(ひゅーまさん・中学校3年生・在籍中)
私立なのでお金がかかる。通う距離も長い。(SAさん・小学校5年生・在籍中)
私学なので学費がかかる(シングル世帯や兄弟での通学が難しい。市内には私学しかなく通いたくても通えないご家庭が多い)。学校の場所が遠い。市内には多様化中学校がないため、小学校卒業後の地元の中学へ在籍することが親子で精神的に苦痛である。(こーたママさん・小学校4年生・在籍中)
先生によって考え方や指導の仕方に差が見られること。登校を促す圧力が強い先生もいて、親子共々負担に感じることがあること。欠席する日は当日の朝電話連絡をする必要があること(公立小に通っていたときは、メール連絡ができました)。学費が高いこと。(まるまるだんごむしさん・中学校2年生・在籍中)
ありません。(アクアさん・中学校1年生・在籍中)
勉強に関しては公立の子よりは積極的指導はしないので、学力は劣る。家でのフォローが必要。それでも学びへの意欲は上がるので、本人次第。小学卒業後、また公立に戻る選択肢しかないので、子どもが中学への変化には対応できないと思う。(晴れパンさん・小学校1年生、3年生・在籍中)
私立だったので費用がかかる。それ以上の価値はありましたが、全世帯が通学できるとは限らないところ。(15歳のくまさんさん・中学校3年生・在籍中)
結局は先生次第なところ。担任の先生が不登校の勉強をしていたり、関心がある先生なら登校できる日も増えて行きましたが、異動でなんとなく配置されたであろう先生が担任になるとまた不登校になります。
このような特別な学校にきてくれる先生にはどうか不登校児の対応について勉強していただきたいと思います。(シーソーさん・中学校2年生・在籍中)
学びの多様化学校のよくないことは、絶対数が不足していることです。そのため、学びの多様化学校へ通いたいと思っても通うことができない子どもたちが多いということが、よくないことでもあり、課題でもあります。(takatakaさん・中学校1年生・在籍中)
「無理しないでね」や「休んでもよい」という気持ちに甘えてしまう。子どもにとっては気持ちが軽くなるが、親は行かせたい、行ってほしい気持ちが抜けきれないのでもどかしさを感じる時もある。今は自宅から近い場所にあるが中学校のことを考えると通学時間がかかるため不安はある。(たこやきさん・小学校5年生・在籍中)
学びの多様化学校に対するご意見・お考え
不登校になった子どもが、通いたいと思う居場所になるよう、当たり前の選択肢になればいいなと思いました。
子どもが不登校になる前は私自身も知らなかったのですが、当事者になってから必死に情報を探し知るのではなく、困っている方により情報が届くよう望んでいます。(みー母さん・小学校3年生・在籍中)
「多様性」が強調される一方で、人との距離が広がり、本音を言えない関係が増えています。その中で学校生活に馴染めない子は増えていくと思います。自由を尊重することは、本来、責任を伴うものですが、それが見落とされがちなので。長期でサポートできるようなところたくさんできるといいなと思います。(yuriさん・小学校5年生・在籍中)
ほかと比較することはできないが、かなりイメージと違った。これからは、商売としての参入も多くなると考えられるため、当たりはずれや、合う合わないが出てくると思う。
うちはほかに通えるところもなかったので仕方ないが、これからはもっともっと学校が増えて、生き残るために熱意を持ったスタッフがいるような学校にしていってほしいと思う。(ひゅーまさん・中学校3年生・在籍中)
これは、学校へではなく、国の制度への要望です。不登校の子どもたちが約34万人を超えている現状をもっても、教育のスタイルを変えずにいくのはどうなんでしょう? 34万人の子どもたちが、いずれ大人になった時、国への信頼をつくるなら、今すぐに変えられるところに着手していくべきだと思います。
学びの多様化学校を増やすなら、公立の小学校と同じ負担にするべきだと思います。なぜなら、経済的理由から、通うことを諦めてしまっている保護者がたくさんいるからです。義務教育の意味と、子どもたちのどんな力を育てていくためのものなのか、大人がチャレンジする姿を見せる時なんじゃないかな、と思います。(ikoさん・小学校6年生・在籍中)
まだ、通い始めて日が浅いので、もう少し見守っていきたい。(SAさん・小学校5年生・在籍中)
各市町村に多様化中学校、小学校を作ってほしい。息子は2年前に学びの多様化小学校へ転入して毎日登校し、友だちもできました。不登校期間は何度も自分はダメなやつだ、死にたいと泣き喚いていました。
親子共に地獄のような日々でした。自己肯定感も回復して、発達障害(ASD)なのを忘れてしまうくらい落ち着いて過ごせてます。
息子のように本当は学校に行きたい、友だちがほしいと思っているお子さんには学びの多様化学校の存在は必要だと思います。私学の学びの多様化校については、自治体または国からの助成金で必要なお子さんみんなが通えるようになってほしいです。(こーたママさん・小学校4年生・在籍中)
よい点ばかりではありませんが、選択肢としてこういった学校があることはありがたく思います。たまたま自宅から通える場所にあったことは幸運でした。もっと全国各地にたくさんあればと思います。(まるまるだんごむしさん・中学校2年生・在籍中)
上の子は学校への抵抗が強く多様化学校も拒否した。
下の子のみ通っている。繊細な上に兄の不登校を見て不安感から母子分離不安に。母子登校しながら、多様化学校に通っている。
多くのカタチの学校が増えて、上の子にも合う場所に出会えると嬉しいと思っている。(晴れパンさん・小学校1年生、3年生・在籍中)
先生方が不登校の子どもを理解するまで時間がかかると思う。
一気に増やしてしまうと指導方法がバラバラで、教室に戻すのが目標になってしまう学校がでてきそうで不安。(15歳のくまさんさん・中学校3年生・在籍中)
学びの多様化学校は、決して学校へ戻す学校ではありません。
学校へ通いたくても通えない、学校で学びたくても学ぶことができない、学びの多様化学校はそんな子どもたちにとって寄り添うことができる学校だと思います。
世間の方々に学びの多様化学校のことを正しく理解してほしいです。そして、全国に300校と言わず、もっと増えてほしいと思います。(takatakaさん・中学校1年生・在籍中)
わが子はたまたま開設校に入学することができて少しずつ毎日行けるようになり、歩き方、行動、表情にも変化が出てきました。
1年前までは登校に向け支度を終えた後、玄関での吐き戻し、原因不明の発熱などがありましたが、学びの多様化学校に行ってからは吐き戻すことが一度もありません。
転校するのも不安はありましたが、居場所ができて変わりつつあります。
1歩進んで2歩下がることもありますが、戻れるところがあるのが心強いです。送り迎えなど、いろいろな問題もあると思いますが、悩まれている方にきっかけを作ってあげてほしいです。(たこやきさん・小学校5年生・在籍中)
* * * * * * * * * *
次回は、「学びの多様化学校」へ通わせたい方、通わせたくない方、それぞれのご意見を紹介します!
「不登校オンライン」では、会員向けの記事(有料)をご用意しています。不登校のお子さんをサポートするために知っておきたい情報や、同じ悩みをもつ親御さんの体験談などを掲載しています。お申し込みは下記から(30日間無料)。