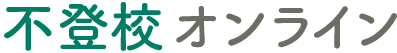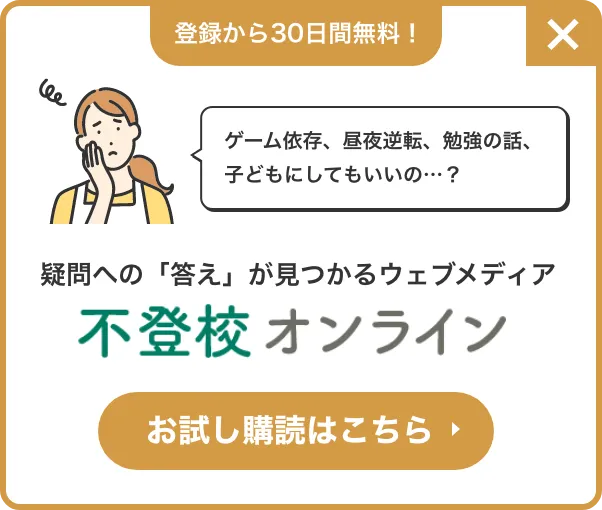「生徒会長から不登校に」優等生だった私が死を望むほどの限界だったあのころ【全文公開】
「事故で死ねば許されると思っていた」。高校で不登校になったという古川寛太(かんた)さん。今23歳の古川さんが、不登校時代をふり返り、当時の思いをまとめました。(連載「前略、トンネルの底から」第1回)※写真は古川寛太さん
* * *
「轢いてくれ」と念じながらよく道路を飛び出していた。みずから死に足をかけるのは、今の俺を虐げてくる「彼ら」からの憐れみを生むだけ。それは負けた気がして嫌だった。事故による不可抗力であれば自分が楽になることも許されるはずで、高校を休んでいることにも正当性が出る。動けない自分を分かりやすく納得させる理由がほしかった。
けれど、平日の昼下がり。死角の多い危険通路といえどもそう都合よく(悪く?)飛び出してくる車体は、結局3年間で一度も現れてくれなかった。
高校で不登校になった。学校へ行きたくなかった。明確な理由があったわけではない。いや、「行きたくない」という意思すらない。ただ、自分の意識とちがうところで唐突に、「行けなくなってしまった」。
中学校まではあたりまえのように学校に通っていた。いたってふつうの生徒だったと思う。まわりとちがうところといえば、同級生よりすこしだけ勉強ができて、同級生よりすこしだけ真面目だったこと。中学校最後の1年間は生徒会長を務めていたりもした。
さて、これは自慢ではない。むしろ自虐である。なぜならすくなくとも以後10年間、こういった特性や経歴が呪いとなってどん底へ沈ませる枷となることを、今の俺は知っているからだ。勉強ができて真面目な自分、そんなセルフイメージができあがっていた中学生の段階で、じつはもう勝負がついていた。無自覚なうちに八方ふさがりとなっていた俺の、症状として表面化した最初の問題が、「不登校」だった。
中学の卒業式で学年代表として答辞を読み、晴れやかに母校を卒業した数カ月後。高校1年生の春。課題提出でいきなりつまづく。小テスト前、数学の課題がまだ終わっていなかった。授業の始まる数十分前に仮病を使って早退。さいわいなことにその場でのおとがめはなかった。しなければならないことをしなかった、そんなことは短いながらも過去15年で何度もあったはずである。けれどこれが響いた。勉強ができて真面目な自分。勉強ができて真面目なこと「しか」能がない自分。それがなくなったら、何が残る? 小学生のころから俺の全体重を支えていた細い杖は「もう限界」と折れて、挫けた。
7時15分。朝起きたら体が起き上がらない。うつろな高校生活の始まりである。(つづく)
(初出:不登校新聞619号(2024年2月1日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)
記事一覧