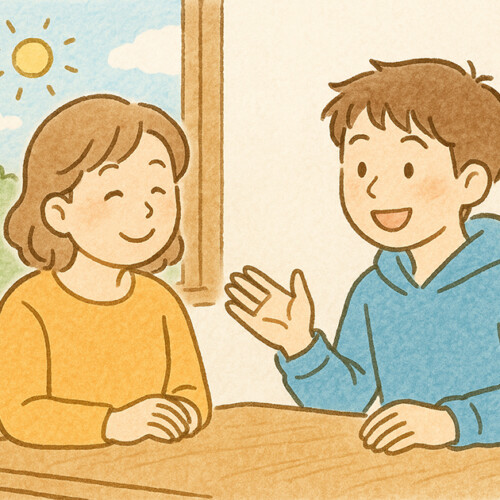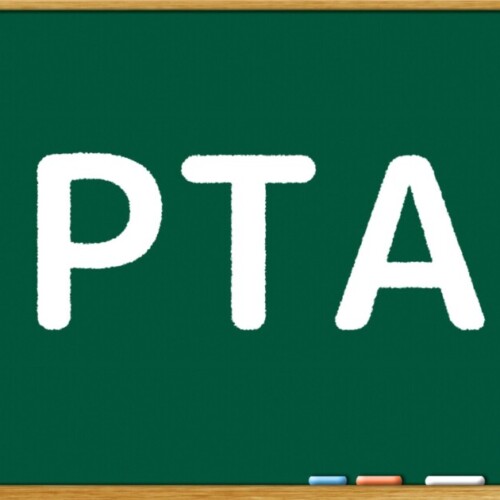【不登校回復期】少し元気が戻ってきたとき、親が“やりすぎない”ことの大切さ【不登校の知恵袋】
不登校の少しずつ子どもの元気が戻ってくる——それは、長く続いた不安や緊張の中で、親にとって本当に嬉しい瞬間です。
しかしこの時期、焦りや期待が先走り、「せっかく元気が戻ってきたのだから、次のステップへ」と急ぎたくなる気持ちも芽生えます。
でも実は、「元気が戻ってきたとき」こそ、親が“やりすぎない”ことが、子どもの回復を支えるうえでとても大切です。
この記事では、不登校回復期における親のかかわり方について、焦りすぎず、子どものペースを尊重する視点から、具体的なノウハウを交えて解説します。
保護者の不安に寄り添いつつ、安心して実践できる方法を紹介します。
【不登校回復期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
親の焦りと子どもの「回復」のギャップを理解する
子どもに少しずつ笑顔が見られるようになった。
自室から出てくる時間が増えた。
趣味に没頭する姿が見られるようになった。
そんな状況になると、親御さんとしては「そろそろ学校に戻れるのでは?」「何か積極的に働きかけた方が良いのでは?」といった期待や焦りが生まれるのは自然なことです。
しかし、子どもにとっての回復期は、心のエネルギーを充電し、自信を取り戻す準備段階。
目に見える「元気」だけを判断材料にすると、親の側が早く結果を求めすぎてしまう恐れがあります。この“ギャップ”を理解することが、親子ともに安心して過ごす第一歩です。
回復期に“やりすぎない”ための6つの視点
回復期には、何かを「する」よりも、「しない」ことが重要になる場面があります。ここでは、具体的な6つの視点を紹介します。
1. 登校を急かさない・プレッシャーをかけない
「学校どうするの?」「いつになったら行くの?」といった言葉は、お子さんにとって強いプレッシャーになる可能性があります。登校再開は一つの選択肢であって、必ずしも目標ではありません。
ポイント:
- 学校に関する話題は、子どもから出てこない限り、親からは積極的に触れない。
- 「行かなくても大丈夫」「あなたのペースで良い」と伝え続ける。
- 学校の話を子どもがした場合は、「話してくれてありがとう」とまず受け止める。
また、学校の行事や友人の話など、子どもがまだ関わっていない情報を一方的に伝えるのも控えましょう。
2. 励ましやアドバイスは“提案型”にする