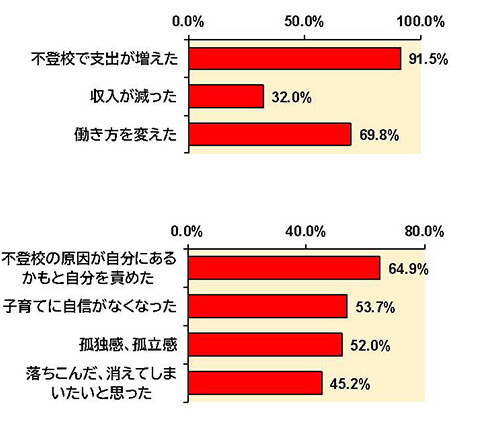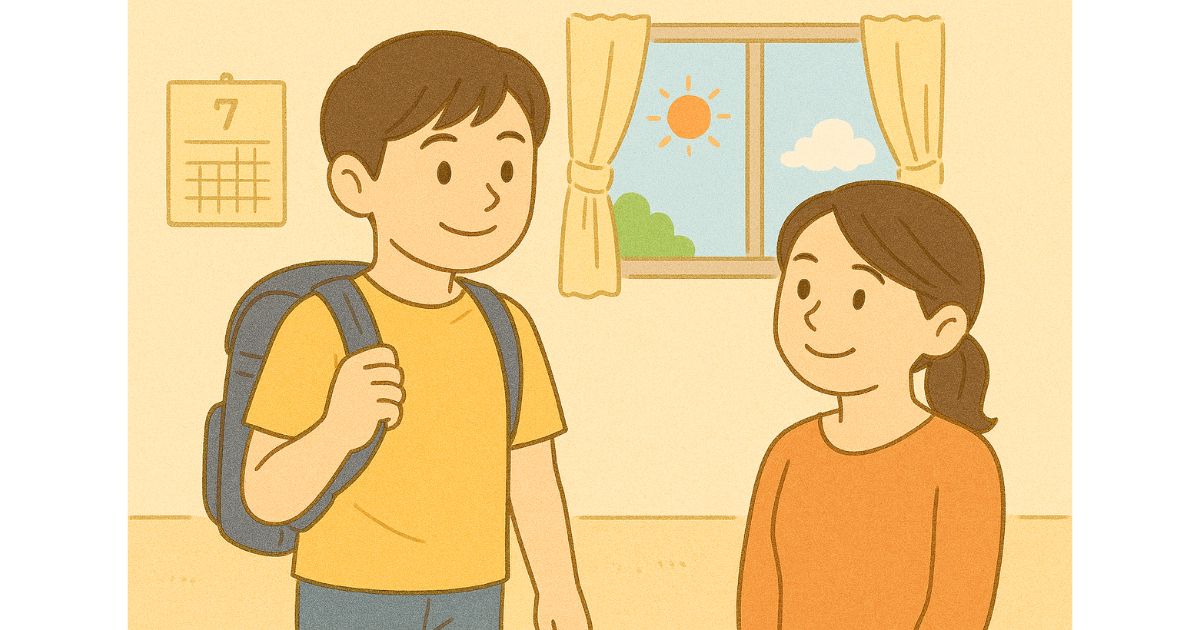
【不登校回復期】「夏休みだからこそ自由に動ける」──外出がプレッシャーにならない工夫【不登校の知恵袋】
夏休みは、みんなが学校に行っていません。不登校の子どもにとっては、「自分だけが行けていない」という悩みから解放される時期です。
そして、「学校以外への外出」からも離れていた子どもにとっては、自分のペースで外の世界に触れるチャンスにもなります。
一方で、「せっかくの休みなんだから」「どこかに行かせないと」といった親の期待が、かえってプレッシャーになることもあります。
この記事では、回復期の子どもが“自分らしく”夏を過ごせるよう、外出を押しつけず、さりげなく後押しするための工夫を紹介します。
【不登校回復期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「動けるようになってきたから、もう大丈夫」ではなく「まだ休みながら」が前提
不登校の回復期では、それまで外出を避けていた子どもでも、家族と一緒のときだけ外出できていた子どもでも、(一人で)外出できるようになることもよくあります。
そう聞くと、「うちの子も、そろそろ(一人で)外出できるようになるのでは」と思いたくなるかもしれません。
でも、その「そろそろ」という感覚には、焦りや期待が潜んでいることもあります。
心の回復は「波」や「ゆらぎ」があるもの
不登校回復期といっても、心身の調子は毎日右肩上がりでよくなるわけではありません。昨日までは元気だったのに、今日は一日寝ていた。そんな波があるのが自然です。
日によってエネルギーの充電量も異なりますし、刺激に敏感になることもあります。
だからこそ、親の側も「今の状態なら、問題なく行動できるはず」と思い込まず、「気分の波があること」を前提に接していくことが大切です。
「計画」ではなく「選択肢」の提示を
夏休みの行動について、親が立てた「計画・予定」は、子どもにとっては“動かねばならないこと”に変わってしまうことがあります。
「誘う」のではなく「知らせる」
たとえば、「○日に○○に行こう」といった予定の立て方は、子どもにとって重荷になりがちです。
一方、「近所で縁日があるみたい」「少し涼しくなってきたね、公園に行くのもありかもね」といった“情報提供”のような言い方であれば、選択の余地を子どもに残すことができます。
また、複数の選択肢を出すことで、「その中から自分で選べる」という感覚が生まれやすくなります。
ただし、子どもの性格によっては「誘いたいならはっきり誘ってよ。なんで回りくどい言い方をするの?」と思われることもあるでしょう。
そんなお子さんについては、「○○で××のイベントがあるけど、一緒に行く?一人で行ってみる?」というように、行く・行かないを選択できるような声掛けがよいでしょう。
「夏らしさ」を押しつけないことの意味
夏は行事が多く、親としては「子どもに楽しい思い出を」と思いがちです。でも、その“善意”が、子どもを縛ることもあります。