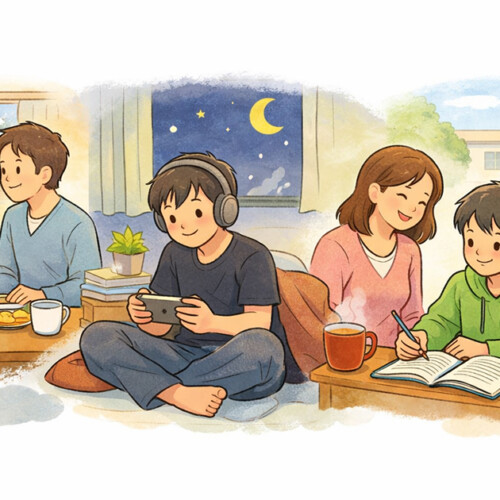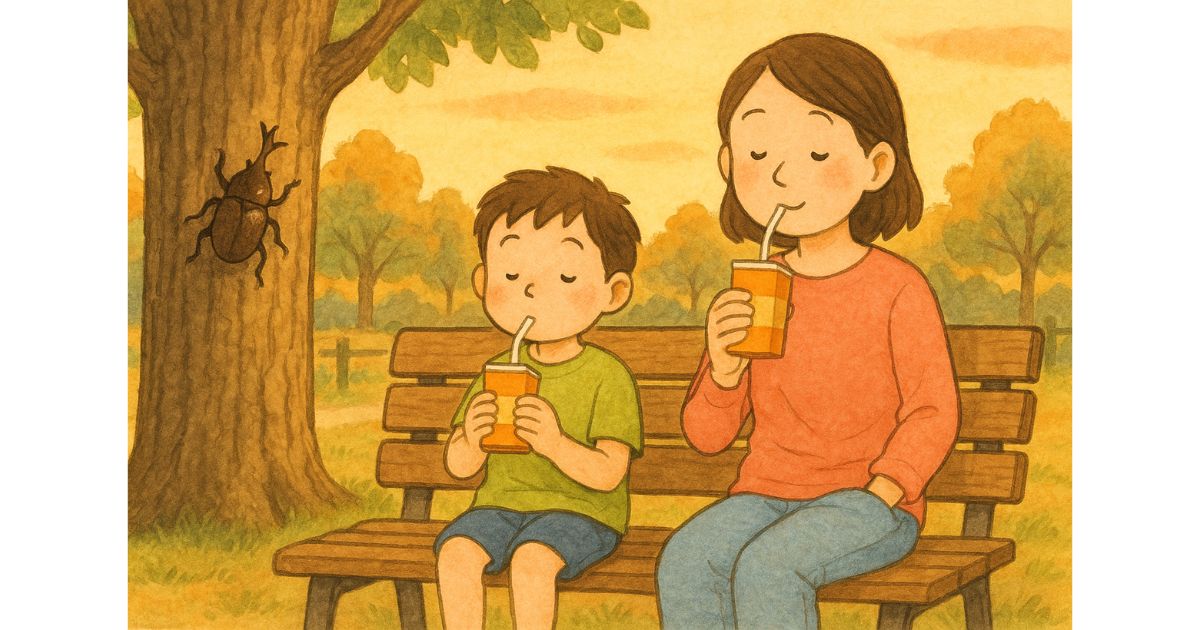
【不登校混乱期】「人が多い場所に行きたくない」混乱期にありがちな感覚への理解【不登校の知恵袋】
夏休みはイベントや外出の機会が増える時期です。
しかし、不登校の混乱期にある子どもにとって、人の多い場所は思っている以上に負担になることがあります。
本記事では、そうした感覚にどう寄り添えばよいか、具体的な対応のヒントをお届けします。
【不登校混乱期とは】
不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校混乱期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「人が多い場所がしんどい」は、とても自然な反応です
夏休みには、夏祭り、盆踊り、花火大会、家族旅行、帰省(親戚の集まり)など、人が多く集まるイベントが多くあります。
不登校状態にない子どもや大人にとっては楽しみなイベントでも、不登校の混乱期にある子どもにとっては「人が多い場所」に出向くこと自体が、心身に大きな負担となることがあります。
「せっかくの夏休みだし、少しは外に出たら?」と声をかけたくなる気持ちもよくわかります。しかし、無理をさせることで心身に悪影響を及ぼすこともあります。
特に不登校混乱期の子どもは、気力や体力が落ちています。そうすると、人の気配、音、視線、匂いなど、周囲からの刺激すべてを「つらい」と感じることがあるのです。
たとえば、雑踏の中で誰かの声が大きく聞こえるだけで心拍数が上がったり、クラクションや音楽の音に圧倒されて動けなくなったりすることもあります。
これは、「疲れている心身が、外部の刺激を処理しきれない」という自然な反応です。
本人の中では「何がしんどいのか、うまく言えないけど、とにかくつらい」という漠然とした不快感として現れることもあります。
「誘うこと」がプレッシャーになることもある
子どもを元気づけたい、外に出て気分転換させたい、という親心から、「○○に行かない?」と誘うこともあると思います。
しかし不登校混乱期の子どもは、「行きたくないけど断ったら申し訳ない」「本当は楽しめないけど、合わせたほうがいいかな」など、自分の本心を抑えがちです。
その結果、無理に外出してぐったりと疲れて、しばらく何もできなくなるケースもあります。
「行く?」「どうする?」と聞かれることが、実は負担になることもあるのです。
「誘うことは、絶対的によくない」とまでは言いません。しかし誘う場合は「断ってもいいと明言する」「断られたときにガッカリしたり怒ったりしない」ということを心がけましょう。
親が「無理に誘わない」ことは、回避ではなく“信頼”です
「このまま引きこもっていたら、余計に外に出られなくなるのでは?」という不安は、誰しも感じるところだと思います。
でも、不登校混乱期の子どもにとっては、「外に出ないこと」は、「自分の状態に合わせて、刺激を制限している」状態とも言えます。つまり「自己防衛」です。
親が「今は無理をしなくていいよ」と言うことで、子どもは「今のままでも大丈夫なんだ」と安心できます。
安心できることで、心身が整い、「ちょっと外に出てみようかな」と思える日が自然と来るのです。
外出できない夏でも、心が動く時間を
不登校混乱期の子どもにとっては、人の多さに関わらず、「外出」そのものが大きなハードルになっていることも少なくありません。
そんな状況でも、気分の波や体調に合わせながら、家の中で、無理のない範囲で「少し楽しい」「ちょっと落ち着く」時間をつくることが、結果的に子どもの安心や自己肯定感につながります。
家の中でできる「小さなひとり時間」
- 好きな音楽を流すだけの時間
ヘッドホンやスピーカーで好きな曲を聞くだけの時間を意識的につくるだけでも、リラックスや気分転換につながります。「今、無理に何かしなくてもいい」という感覚を支えてくれます。
- スマホやPCでの“ゆるい”創作活動
動画編集、イラストアプリ、日記アプリなど、創作につながるツールを「成果を出さなくていい」前提で触れるのもおすすめです。誰かに見せなくてもいい。ちょっと手を動かすだけで、自分の世界を大切にできます。
- 天気のよい日に「ベランダで本を読む」
外出は難しくても、外気に触れるだけで気分が軽くなることがあります。家の中からベランダに一歩出て、漫画や雑誌をパラパラめくるだけの時間でも、少ない刺激の中で、気分を転換することができます。
家族との「近すぎない」つながり方
- 一緒に動画や映画を“ながら見”する
面と向かって会話をしなくても、同じものを同じタイミングで見るだけで、共有の安心感が生まれます。「一緒にいるけど放っておいてくれる」のバランスがうまく取れた時間です。
- 夜にお茶だけ飲みに来る“呼ばない時間”
「ご飯は自分のタイミングで」としても、たとえば夜に「お茶だけ用意しておくから、好きに飲んでね」と声をかけることで、接点は保ちつつも無理にコミュニケーションを求めない安心感を伝えられます。
- ペットや植物と過ごす時間を増やす
人間関係がしんどいときでも、生き物との時間は癒しになります。散歩は難しくても、部屋で犬と過ごす、観葉植物に水やりをするといったささやかな行動が、心のを支えることもあります。
「何もしない」時間を否定しない
何かに取り組むことが大事なのではなく、「何もしないままの時間が、今のわが子には必要かもしれない」と思える視点が、とても大切です。
動けない、考えたくない、自分でもよくわからない――そんな心の状態が、「今の自分」を守るために働いていることもあるのです。
親がその“止まっているように見える時間”を、焦らず・責めず・見守れるかどうかが、その後の回復の足場になります。
大切なのは「行けた/行けなかった」で判断しない姿勢
最後に、親が意識したいのは「結果で判断しない」ことです。「結局、○○には行けなかったね」「せっかく誘ったのに…」といった言葉は、たとえ悪気がなくても、子どもには強いプレッシャーになります。
大切なのは、子どもが「行かない」と選んだことを否定しないこと。そして、「行かなくても、あなたは大丈夫」というメッセージを伝え続けることです。
「無理に頑張らせないこと」は、あきらめや放任ではなく、今の子どもを丸ごと受け止める大切な姿勢なのです。
不登校混乱期で、人が多い場所への外出が苦手な子どもへの親の対応につまずきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ)が見聞きした、「不登校混乱期で、人が多い場所への外出が苦手な子どもへの親の対応」につまずきがあったエピソードを紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
『せっかくのお祭りなんだから』という押しつけ
中学2年生の陽菜さんは、夏休みに入ってからも自室で過ごす時間がほとんどで、外に出たがらなくなっていました。
母は「○○神社でお祭りがあるよ。あそこならちょっと遠いから、同級生とも会わないでしょ。今晩行ってみようね!」と声をかけ、浴衣を用意して参加を促しました。