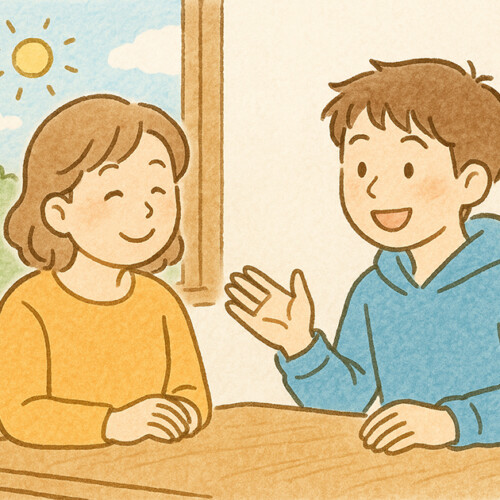【不登校回復期】一緒にいるだけの夏。「会話がなくても大丈夫」と思える時間の価値【不登校の知恵袋】
「夏休みなんだから、たまには話してくれたらいいのに」。
そう思うのは、ごく自然なことです。しかし、不登校の回復期にある子どもにとって、その何気ない期待や願いが、時に大きな負担となることもあります。
この記事では、「会話がなくても、一緒にいるだけでいい」と思える夏の時間の価値を、親子双方の視点から見つめ直します。
無理に変化を求めない、でも確かなつながりが生まれるような関わり方を一緒に考えていきましょう。夏以降の参考にもしていただけると思います。
【不登校回復期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
会話のない時間にも意味がある〜親が気づきにくい「安心」のサイン〜
「今日どこか行く?」「何かしたいことある?」と聞いても、子どもから返ってくるのは曖昧な返事や無言。そんな時間が続くと、親としては「このままでいいのだろうか」と不安になるものです。
けれども、会話がないことは、必ずしも“関係が悪い”ことを意味しません。むしろ、親子の間に「無言でも安心できる時間」があるというのは、子どもにとって大きな意味を持ちます。
不登校回復期の子どもは、心のエネルギーを少しずつ取り戻しつつある状態です。
会話を「やらなきゃいけないこと」として捉えると、再び心が疲弊することもあります。そのため、言葉や行動では見えない心の動きを、親が静かに見守る姿勢が大切になります。
無理に話しかけなくてもいい。共にいるだけで育まれる安心感〜会話がなくても、そこに「いる」ことの意味〜
子どもがリビングに来て、何も話さずただゴロゴロしている時間。スマホを見たり、音楽を聴いたりするだけの様子に「何もしていない」と思いがちです。
しかし、親子が同じ空間で静かに過ごす時間は、子どもにとって「見守られている」「受け入れられている」という感覚を育みます。
親が何かをしていて、隣で子どもが無言で過ごしている──それだけでも、十分に関係性は築かれています。
逆に、「せっかく夏休みなんだから」と無理に話しかけすぎることで、子どもが居場所を失うこともあるのです。
子どもにとっての「居心地のよさ」とは? 親ができる工夫〜親が先にリラックスする時間をつくる〜
「今日は会話できるかなと思ったけど、やっぱり口数が少ない…」と、親が焦った気持ちで接すると、その空気は子どもにも伝わります。
すると、子どもは「自分が期待に応えられていない」と感じることがあります。
そうならないためには、親自身が意識的にリラックスした時間を持つことが大切です。
たとえば、好きな音楽を聴いたり、趣味の時間をつくったり、本を読んだり。親が「自分の時間」を大切にすることで、家庭全体の空気が少しずつ柔らかくなります。
子どもは、そうした大人の姿から「無理をしなくていいんだ」と感じ取ります。
「どう過ごすか」より「どういられるか」
不登校の回復期の子どもにとって大切なのは、「今日は何をするか」よりも、「今日をどう感じられたか」です。
無言の時間を「何もない時間」とネガティブに考えるのではなく、「今、落ち着いていられた」とポジティブに捉えることで、親子関係への見方も変わってきます。
リビングで同じ番組を見る。キッチンで何気なく隣に立つ。アイスを一緒に食べる。それだけでも、子どもにとっては「大事な経験」となっていきます。
不登校回復期で、会話の少ない子どもへの親の対応につまずきがあったエピソード
不登校オンライン(キズキ)が見聞きした、「不登校回復期で、会話が少ない子どもへの親の対応」につまずきがあったエピソードを紹介します。
※個人の特定に紐づかないよう、複数の事例を統合・編集・再構成しています。
※これまでに同じような対応をしている親御さんを不安にさせるつもりはありません。その上で、「お子さんへの対応」は親だけ・家庭だけで対応しようとせず、不登校のサポート団体を利用することをお勧めします。
沈黙を埋めようとしすぎて──詰め込みすぎた「おでかけ計画」
中学2年の葵さんは、夏休みに入ってから少しずつ自室から出てくるようになり、リビングでぼんやりと過ごす時間が増えてきていました。