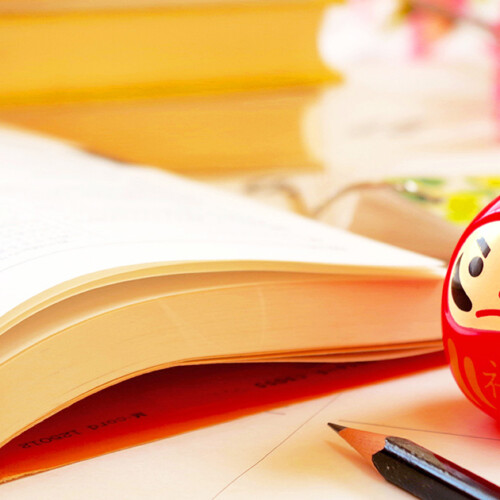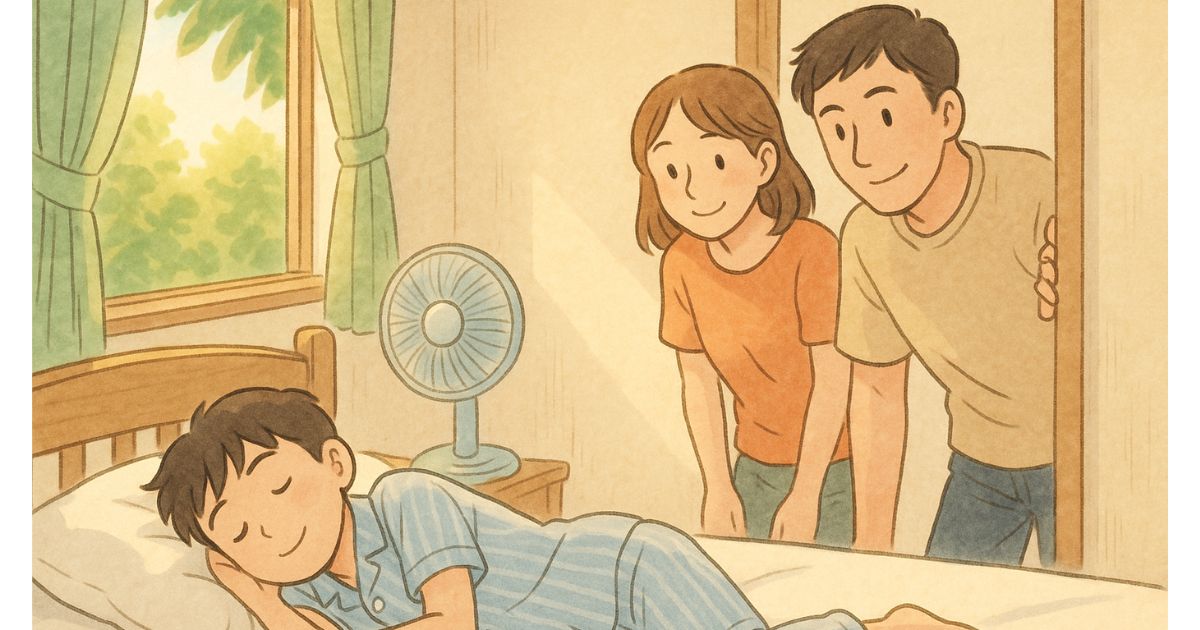
【不登校進行期】「昼夜逆転」を戻そうとしないほうがうまくいく?夏の睡眠の考え方【不登校の知恵袋】
夏は、ただでさえ夜型の生活に傾きやすい季節です。そこに(夏休み中とはいえ)「不登校進行期」という状況が重なると、子どもの昼夜逆転は一層深まることもあります。「早く直さなきゃ」と焦る気持ちは自然ですが、実は“戻そうとしないほうがうまくいく”こともあるのです。
この記事では、「昼夜逆転」の背景を丁寧に捉えながら、親子ともに疲れない睡眠との付き合い方を紹介します。
この記事でお伝えすることは、あくまでも参考情報です。体調については、医療機関などに相談します。
【不登校進行期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。進行期とは、不登校が始まり、心理的な落ち込みが激しくなり、やがてその状態が固定化されるまでの期間のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校進行期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「夜型になるのは当然」と考えてみる
不登校の子どもが夜型の生活になるのには、きちんと理由があります。特に夏は気温や周囲の生活音、人の活動時間などの環境要因も加わり、昼間を避けて夜間に安心を求める傾向が強くなります。
昼はまぶしく、暑く、落ち着かない
夏の昼間は、日差しも強く、外の音や周囲の活動も活発です。こうした「刺激」の多い時間帯は、気力が落ちている不登校進行期の子どもにとって、しんどいものです。
特に心理的に不安定な時期には、静かで涼しい夜間にだけ心が落ち着くということもあります。夜中にスマホを見たり、動画を流しっぱなしにしていたりするのも、本人なりの「気を紛らわせる」「安心できる時間」だからかもしれません。
夜にしか「自分の空間」を感じられない
昼間は家の中にも家族の気配があり、否応なく「社会」とつながるような感覚があります。
一方で、深夜は誰にも干渉されず、自分のリズムで過ごすことができるため、子どもにとっては唯一リラックスできる時間帯になっていることも多いのです。
「戻す」よりも、「崩れすぎない」を目指す
睡眠リズムが気になるとき、つい「早寝早起きをさせよう」としがちです。しかし、心理的にエネルギーが不足している時期には、それが子どもにとって大きな負担になります。
ここでは、「戻す」よりも「崩れすぎない」ための工夫を紹介します。
「ズレ」があっても、リズムの“まとまり”があればOK
たとえば、朝6時に寝て昼3時に起きるような生活であっても、起床・食事・入浴・就寝の順番が毎日同じであれば、それは一つの「まとまりある生活」として捉えて問題ありません。
無理やり「朝に起きよう」と声をかけるよりも、「起きたら“おはよう”を言う」「夕方に“一緒におやつを食べる”」といった小さな接点の方が、子どもにとっては安心できるのです。
日中の活動を“軽く”取り入れる
完全に昼夜逆転していると、運動不足や日光不足が続いて、さらに気分が落ち込みやすくなります。ただし、無理な外出は逆効果になりがちです。
おすすめなのは、エアコンの効いた室内でできる軽いストレッチや、家の中でのちょっとした片づけ。「身体を動かしている」という実感があると、夜の眠りも深くなりやすくなります。
また、夕方〜夜にかけての短時間の外出(たとえば夕暮れのコンビニやスーパーへの散歩)も、リズムの切り替えにつながります。
「生活を正す」ことが目的ではない
昼夜逆転を気にして、どうしても「正しい生活に戻さなきゃ」と考えてしまうことがあります。しかし、子どもの状態にとっては「今の生活」が精一杯ということもあります。
ここでは、「正しさ」にとらわれすぎないためのヒントを考えてみましょう。
睡眠リズムの乱れ=本人の責任ではない
気温、ストレス、精神的疲労、自律神経の乱れ――こうした複合的な要因が重なると、自然と睡眠リズムは崩れます。特に、不登校の進行期では、夜にしか落ち着けないという状態そのものが「回復に必要な形」なのです。