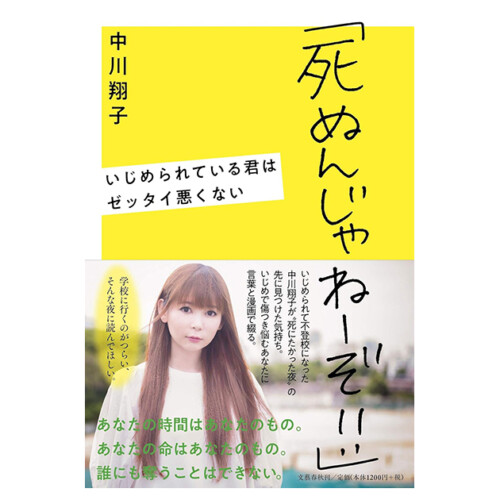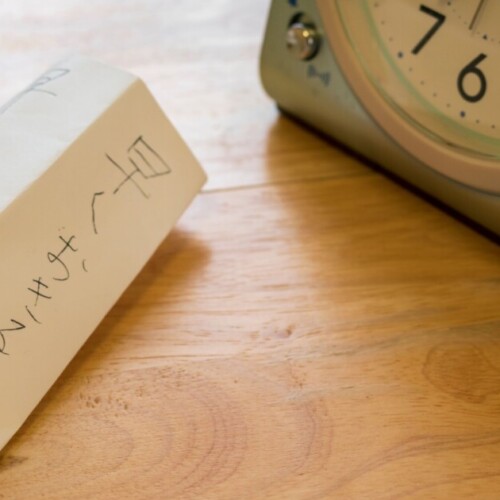【不登校混乱期】「もう半年経ったのに…」——変わらない日々に“焦らない”という選択を【不登校の知恵袋】
半年、あるいはそれ以上の時間が経っても、夏休みを経て2学期が1か月経っても「学校に行かない子ども」。大きな変化が見られない…。
そんな日々の中、「このままで大丈夫なのだろうか」と不安になる親御さんは少なくありません。
でも、「変わらない」と感じる時間にも、確かに意味があります。焦りを手放すことが、実は子どもの心の回復を支える第一歩になるのです。
【不登校混乱期とは】
不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校混乱期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
「変化がないように見える」時間にも、心の中では動きがある
静止して見える時間にも、子どもの心は少しずつ変化しています。ここでは、外から見えにくい“回復の準備”をどう理解するかを整理します。
外からは見えない「心の再生期間」
「ずっと部屋にこもっている」
「表情が変わらない」
——そんな状態が続くと、親としては「何もしていない」「何も変わらない」と感じるかもしれません。
けれど実際には、子どもの内側では「心の再生」が静かに進んでいます。
人の心は、傷ついたあと再び動き出すまでに“停止”の時間を必要とします。これは怠けではなく、回復の準備です。
「定着」は「停滞」ではない
不登校状態が“定着”して見えるときは、むしろ落ち込みの激しさが落ち着き、心の底で安定しているサインと捉えることもできます。
安定は次に来る回復の前段階。
目にみえる変化が乏しくても、内側の変化は起きています。
“変わらなさ”への焦りが子どもを追い詰めることも
「そろそろ○○してみたら?」
「半年も経ったのに…」
といった声かけは、善意でも“急かし”として伝わりがち。
親が自身の焦りに気づいたら、一度立ち止まりましょう。
「焦らない」ためにできる3つの工夫
焦らないことは難しくても、「焦らない状態を整える」ことはできます。