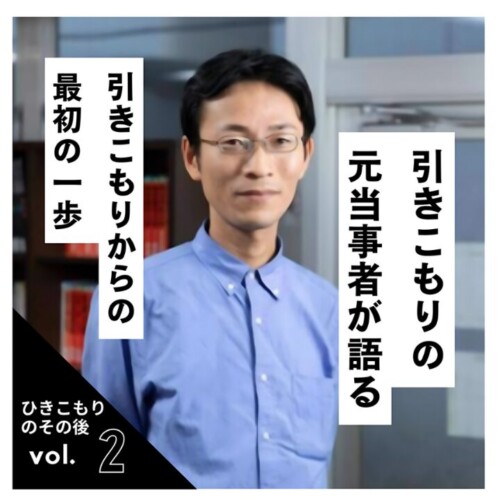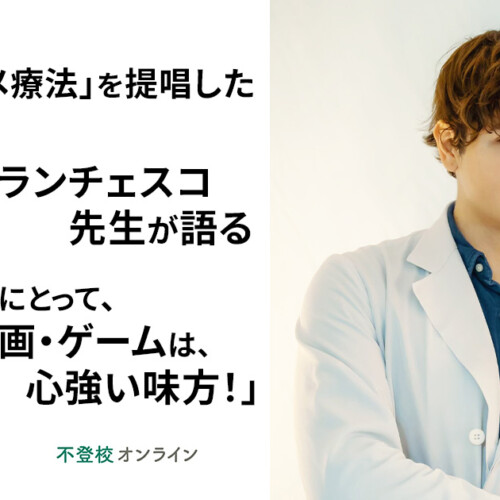大学での不登校を経て、“世界一の娘”へ〜娘と母の30年の物語〜【不登校親子対談】
不登校は子ども本人だけでなく、家族にとっても大きな悩みとなるものです。
しかし、その状況をどう受け止め、どのように支えていくかによって、未来は大きく変わります。
今回は、大学時代に不登校を経験した娘さんと、その姿を見守り続けたお母さんの対談です。
娘さん:岩城みちるさん。
写真右。取材時48歳。大学時代に不登校を経験。現在はキズキ共育塾(※)の講師、お母さまとともに運営する英会話教室の講師、通訳ガイドとして活躍中。
※キズキ共育塾:不登校オンラインと同じく株式会社キズキが運営する「不登校の子どもたちのための完全個別指導塾」。
お母さま:えり子さん。
写真左。取材時80歳。現在も英会話教室で講師を務める。
不登校当時の心境や親子の関係、どのように立ち直っていったのかなど、赤裸々に語っていただきました。
「不登校だったあの日々が、今の自分をつくった」。不登校に悩む保護者の方にとって、ヒントとなる言葉が見つかるかもしれません。ぜひ最後まで読んでみてください。
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
不登校のはじまり—大学での挫折と体調不良
みちるさん:
私が大学に通えなくなったのは、2回生の途中くらいです。
父が大学の入試の日に亡くなり、その後もアルバイトと学業の両立で心身ともに疲れ切っていました。
想像以上に勉強が大変で、睡眠時間を削って頑張る日々。気づけば、無理が祟ってガス欠のような状態になっていたんです。
次第に食事ができなくなり、拒食症になってしまって……。
母は心配してくれました。
それでも当時の私には病院に行こうという発想すらありませんでした。
心療内科を受診したのはかなり後になってからで、診断は「うつ病」。
その後は入退院を繰り返しながら療養生活を送りました。
えり子さん:
娘の異変にはすぐに気がつきました。
でも、学校に行く・行かないよりも、まず健康が心配でしたね。
「とにかく元気になってほしい」その一心で心療内科の先生と相談しながら入院のサポートをしました。
食事についてはあえて口出しせず、ただそばにいることを心がけました。
何を言っても受け入れてもらえない時期もありましたが、「どんなときも愛しているよ」と伝え続けました。
大学は、先生方のサポートのおかげで、なんとか卒業できました。
海外での新たな挑戦—オーストラリアでの療養と学び
えり子さん:
娘はその後、オーストラリアで療養することを決めました。