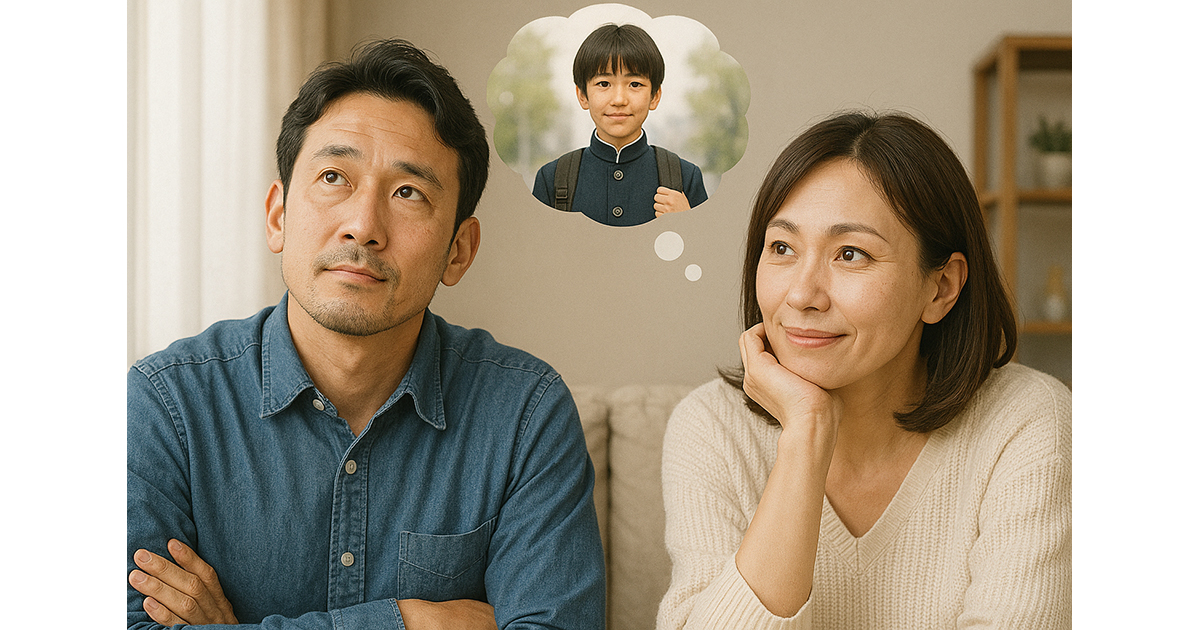【調査報道】「不登校と、親の仕事」のリアル(5)〜退職した方の自由記述〜
子どもの不登校は、親の働き方にも大きな揺らぎをもたらします。
ウェブメディア「不登校オンライン」は、不登校の子どもがいる親438名にアンケートを実施。結果、約6割が退職・転職・就業、または働き方の変更を経験していました。
この記事では、お子さんの不登校に関連して退職した方の自由記述と、それに対する編集部の分析・コメントを紹介します(回答は原文ではなく、編集部が類型化や編集を行っています)。
目次
1.退職した理由について、詳細を教えてください。
回答者:母親52名、父親1名、その他1名
1. 子どものケアが優先となり、仕事との両立が困難に
- 朝の登校渋りや遅刻、欠席に対応するため出勤が難しくなった。
- 登校付き添いが必要だが、朝の判断がギリギリまで読めず、勤務に支障が出た。
- 子どもが家にひとりで留守番できず、常にそばにいる必要があった。
- 就学不安や精神的な不安定さが続き、目を離せない状態だった。
- フリースクール等に通うにも親の付き添いが必要で、自由な時間が確保できなかった。
- 自殺未遂があったり、夜中に悩みを打ち明けられたりし、生活リズムが崩壊した。
2. 精神的・肉体的な限界を感じて
- 心身ともに疲弊し、仕事に集中できずミスも増えた。
- 不登校と職場のストレスが重なり、うつ病を発症した。
- 仕事中も子どものことが頭から離れず、精神的に限界だった。
- 自身がパワハラを受けており、同時期に子どもの問題も重なって耐えきれなかった。
- 体力がもたず、重責や残業に耐えられなくなった。
3. 職場環境・理解の不足
- 突発的な欠勤・早退への職場の理解が得られなかった。
- 人手不足や業務負担を理由に、休みへのプレッシャーを感じ続けた。
- 子どもの病名がなければ介護休職が取れないと断られた。
- 子どもを見ながらのリモート勤務が認められなかった。
- 社内にいじめや陰口があり、居づらくなった。
4. 働き方の制度や待遇面での制限
- コロナ前だったため、柔軟な勤務形態がなかった。
- 有給が尽きたあと、休職制度も十分に機能せず退職を選んだ。
- 社会保険料の支払いが無収入時には負担となり、在籍継続が難しかった。
- リモートや時短勤務の打診が通らなかった。
5. 家族・家庭の事情の変化
- 夫や祖父母の協力が得られず、育児負担がすべて自分にのしかかった。
- 離婚や家庭不和が重なり、環境を整える必要があった。
- 子どもの転校や新たな生活環境への適応を優先し、サポートに専念した。
6. キャリアの見直しと葛藤
- 激務や将来的な残業が見込まれる働き方に疑問を持った。
- 自身のキャリアや働き方に限界を感じ、新しい学びに踏み出した。
- 「保育士である自分が、自分の子どもを預けて他の子を見る」という矛盾に耐えられなかった。
7. 子どもに寄り添うための意思決定
- 児童精神科の医師から「退職も選択肢」と助言され、決断した。
- 専業主婦としてしっかり向き合えば子どもが回復すると思った。
- 子どもと一緒に模索しながら支えるために仕事を手放した。
回答者ペンネーム(敬称略):happy、monmon、na_yo、non、qwert、sar、skkt、あん、いとさん、おもち、かめさん、こっしい、ささら、しゅん、すず、ちぃ、たかとも、たっちゅさん、ちひろ、ちひろ、つむぎ、とこ、なかむら、なな、のっち、はる、はるあのママ、はるまま、はるママ、ひよこ、ほり、みっくす、みぴまま、みみみ、もみ、やっちゃん、やま、ゆあ、ゆきぶぶ、ゆうちゃん、カク、ケイティ、クローバー、シュンシュン、ナナフシ、リーナ、トトロ、不登校母、河本、山、草、晴れパン、花ちゃん、葵 ※「ちひろ」さんが2名いますが、ペンネームが重複した別人です。
2.退職して「よかったこと」の詳細を教えてください。
回答者:母親38名、その他1名
1. 子どもと向き合う時間が確保できた
- 子どもと過ごす時間が増え、密に状態を観察し、言語化できない不登校の原因を見出せた。
- 子どもの様子をより把握できるようになった。
- 子どもが相談したいときにすぐそばにいられた。
- ゆっくりと向き合う時間ができ、日々穏やかに過ごせている。
- 朝の登校を強制せず、気持ちに寄り添った対応ができるようになった。
- 子どもと「他愛もない話」ができるゆとりができた。
2. 子どもの変化・安定につながった
- 子どもが笑顔を見せるようになった。
- 不安が強く留守番できなかった子が、安心して過ごせるようになった。
- 心の余裕をもって接することで、結果的に復学につながった。
- 子どもが情緒的に安定し、夜驚(やきょう)も収まった。
- 子どもの精神状態が明るくなった。
- 学校関連・学習に時間が割けるようになり、再登校や第三の居場所への意欲が出てきた。
- ゲームやYouTubeとの接し方を観察でき、依存を防ぐことができた。
3. 学習・生活のサポートができた
- 勉強に並走できるようになり、学力が年齢相応に追いついた。
- 食事づくりや買い物に時間をかけ、少しずつ食べられるようになった。
- 温かい料理を提供できるようになった。
- フリースクールへの送迎や、短時間登校時の送り迎えも柔軟に対応できた。
4. 保護者自身の心身の変化・回復
- 精神的・肉体的な疲労が減った。
- 激務から解放され、不眠や抑うつが改善した。
- 心の負担が減り、自分自身にも目を向けられるようになった。
- プレッシャーから解放され、気持ちが楽になった。
- 自分の人生や生き方を見直すきっかけになった。
5. 家族全体に良い影響があった
- 自分のゆとりが家族のゆとりにもつながった。
- 家事に時間がかけられるようになり、家が整ってきた。
6. 実際の行動・体験として得たもの
- 子どもとともにフリースクールへ通ったり、付き添って登校する時間が持てた。
- 通信制高校の見学や手続きができた。
- 就職活動を子どもと一緒に行うことができた。
- 不登校について学ぶ時間が増え、対話の質が深まった。
- リモートワークなど新たな働き方の経験もできた。
回答者ペンネーム(敬称略): happy、na_yo、non、qwert、sar、skkt、sumyu、あん、しゅん、ちぃ、ちひろ、なな、はる、はるあのママ、はるまま、はるママ、みぴまま、みぱぴ、みみみ、ゆあ、ゆきぶぶ、ゆうちゃん、ららら、りこ、こっしい、ケイティ、クローバー、シュンシュン、トトロ、リーナ、たかとも、たっちゅさん、ほり、河本、山、晴れパン、花ちゃん、葵
3.退職して「よくなかったこと」の詳細を教えてください。
回答者:母親41名、父親1名
1. 経済的な不安・収入減の影響
- 収入が激減し、生活が赤字になった。安定収入がなくなり、家計の見通しが立たない。
- 母子家庭で無収入となり、貯金も底をついた。どうしていいか分からない。
- 退職から再就職しても年収が三分の一に減り、子どもの教育費の捻出が苦しい。
- 通信制高校やサポート校、フリースクールの費用がかさみ、出費が増加。
- 校納金や教材費、食費、体験活動の費用など、登校していなくても支出は続く。
- 生活保護の受給に至った。
- 貯蓄を切り崩す生活となり、将来の不安が強まった。
- 高校卒業後ずっと働いてきたが、収入がなくなり充実感も喪失。喪失感や後ろめたさもあった。
2. 就労困難・キャリアの断絶
- 子どものケアと両立できる働き方が見つからず、再就職が困難。
- 地方では短時間勤務(タイミー等)も難しく、リモートワークもハローワークで難色を示された。
- 朝早く起きられず、社会復帰に対する不安も増加。
- 20年以上続けた仕事を手放したことで、自分のキャリアが途絶えたという実感がある。
- 小学校での学習支援ボランティアができると思って退職したが、許可が下りず無職期間だけが残った。
3. 精神的負担・社会的孤立
- 「社会と断絶した」という気持ちや孤独感がある。
- 母と子が家から出ない日々が続き、自分のメンタルが不安定に。
- 子どもにばかり意識が向き、お互いに緊張感が増した。
- 働く夫との格差から、「自分だけが犠牲になっている」という気持ちになる。
- 「不登校の親」という社会のネガティブなイメージに苦しみ、助けを求めても理解されない。
- 「不登校なんて気にしなくていいよ」といった軽い励ましに逆に孤独を感じる。
- 常に子どもと一緒で自分の時間がなく、ストレス過多な生活になっている。
4. 支出増による生活圧迫
- フリースクール・教材・習い事・交通費などで支出が増える。
- 子どもが家にいることで食費も増え、外出や娯楽費もかかる。
- 経済的に節約せざるを得ず、好きな場所に行けない・必要な支援が受けられない。
- 子どもの活動や学習を支えるための支出と、自分の収入ゼロが直結し、生活が厳しくなった。
5. 自身の葛藤・後悔・気づき
- 精神的負担の大きさに比べ、周囲の理解が得られず、心が折れそうになった。
- 仕事を失ったショックと「これでよかったのか」という迷いに悩まされた。
- 安定収入はなくなったが、子どもと過ごす時間はお金に代えがたく、結果としてよかった面もある。
- 「キャリアは定年までの“お約束”にすぎない」と気づき、新しいことに挑戦するきっかけになった。
回答者ペンネーム(敬称略):happy、monmon、na_yo、non、qwert、sar、skkt、sumyu、あん、こっしい、ささら、しゅん、たかとも、たっちゅさん、ちぃ、ちひろ、つむぎ、なな、のっち、はる、はるあのママ、はるまま、はるママ、ひよこ、ほり、みぴまま、みぱぴ、みみみ、やっちゃん、りこ、ゆきぶぶ、ゆうちゃん、アラレ、ケイティ、クローバー、シュンシュン、トトロ、リーナ、不登校母、河本、山
4.「退職する前の、働き方の調整」で役立ったことの詳細を教えてください。
回答者:母親15名
1. 制度や柔軟な勤務による支援が役立ったケース
- 子どもの登校意欲に合わせて、時間単位で休暇を取ることができた。
- 時短勤務だったおかげで、登校する子どもの付き添い、不登校の子の対応、下の子の保育園送迎と出勤の両立が可能だった。
- 時短勤務制度内で勤務時間の調整ができ、非常に助かった。
- 有給休暇を1時間単位で取得できたのがありがたかった。
- 午後勤務やかなり遅い時間へのシフト変更ができ、子どもへの対応がしやすくなった。
- 学校への送迎対応や、スクールカウンセラーへの相談時間を確保できた。
- 「来られるときだけでいい」と言ってもらえ、精神的に支えられた。
- 「大変だね」と労いの言葉をもらえる環境だったことが励みになった。
- 有給でしばらく休ませてもらえたことで、気持ちを整える時間が持てた。
- 退職を検討する際、介護休暇や休職の取得可能日数などを丁寧に教えてもらえた。
2. 個人で働き方を工夫したケース
- 最も働きやすかったのは、退職して個人事業主となり、元の職場から仕事を請ける形だった。子どもの調子に応じて仕事を断ったり受けたりできたため。 ただし、断り続けると次の仕事は来なくなるリスクもあった。
3. 柔軟な勤務でも限界があったケース
- 週4勤務から週3勤務に減らし、通信制高校への転校準備や子どもとの時間を確保できたが、それでも足りず、最終的には退職を選ぶことになった。
- 子どもが落ち着いてきた頃に新しい職場に就職したが、再び子どもの体調が悪化。勤務形態を在宅勤務に切り替えてもらった。
- 在宅勤務が週5回になり、激務ではあったが、子どもと昼食・夕食を一緒に取れるようになり、コミュニケーションの時間が取れた。
回答者ペンネーム(敬称略):na_yo、sar、いとさん、ささら、ちひろ、はる、はるまま、はるママ、ほり、みっくす、みぴまま、ケイティ、シュンシュン、トトロ、河本、葵
5.退職する前の、働き方の変更の職場への相談について、詳細を教えてください。
回答者:母親32名、父親1名
1. 相談したが状況は改善しなかった/限界を感じた
- 働き方の柔軟な変更を提案してもらえたが、実行に移す前に自分の気持ちが折れてしまった。
- 上司に相談し、勤務日数と時間を減らす形で続けてみたが、子どものケアや学校対応が多忙で心身ともに限界となり、最終的に退職を申し出た。
- 柔軟な遅刻や早退はできたが、人員不足で業務量は調整されず、自分への負担が増えるばかりだった。
- シフトの変更を店長が認めても、担当者に伝わっておらず、再調整時に他のスタッフから不満を持たれた。
- 仕事と家庭を両立しようと相談したが、「他の育児中の社員と公平に」と言われ、特別な配慮は受けられなかった。
- 不登校が病気と見なされず、介護休暇の取得も無給で苦しかった。
- 付き添い登校のため、シフトを減らしてもらったり休職したが、支援は限定的だった。
- 子どもの不登校について相談し、制度を調べてもらったが、該当する休職制度がなく困難だった。
2. 職場に理解や配慮があったケース
- 子どもの登校しぶりに合わせて、時短勤務の時間変更を受け入れてもらった。
- 上司が話を丁寧に聞いてくれ、自分に合った働き方を提案してもらえた。
- 一度退職した後、非常勤で職場復帰し、柔軟な遅刻・早退にも応じてもらっている。
- 「子どもを1人にするのが不安」と伝えたところ、上司が了承してくれた。
- 不登校と再登校希望について、時間単位の年休取得を認めてもらえた。
- 担任代行を教務主任が引き受けてくれた。
- 在宅勤務の回数を一時的に増やしてもらえた(週3→週5)。
3. 制度や職場の制限により配慮が受けられなかった
- 不登校が理由での休職制度がないと断られた。
- リモート勤務を希望したが、会社パソコンの自宅使用が不可で実現できなかった。
- 在宅勤務の打診をしたが、叶わなかった。介護休暇も不登校では適用されないと説明された。
- 子どもを連れての出勤を一度は許可されたが、継続は拒否された。他の職員への配慮が理由だった。
- シフト制の接客業で子連れ出勤は不可だった。
- すでに時短勤務だったため、それ以上の相談は遠慮した。
- 既に緩和勤務の中でさらに調整を望むことはできず、理解も得られなかった。
- 昇進異動を辞退し続けたが、最終的に異動されてしまい、家庭と両立できず退職に至った。
4. 相談できなかった/相談が困難だったケース
- 出産や本人の傷病以外で休職した前例がなく、制度を活用する発想自体が持てなかった。
- リモートやフレックス、子連れ出勤などを希望したが、制度的に厳しく、特別扱いも拒否された。
- 相談する余裕もなく、診断書を提出して休職に入った。
- 退職の意向を伝えてもすぐには認められず、実際に辞めるまでに4か月を要した。
- 子どもが不登校であることを職場には隠していたため、相談できなかった。
回答者ペンネーム(敬称略):monmon、na_yo、qwert、sar、skkt、sumyu、あん、いとさん、かめさん、きしゃぽっぽ、しゅん、ささら、すず、たかとも、たっちゅさん、ちぃ、ちひろ、のっち、はるあのママ、はるまま、はるママ、ひったーち、ほり、みっくす、みぴまま、もみ、ゆうちゃん、ゆきぶぶ、ららら、トトロ、晴れパン、河本、葵
6.編集部の分析・コメント
不登校をきっかけにした退職は、「働けなくなった」というよりも、「家族を守るための現実的な選択」として位置づけられていました。
多くの保護者が、子どもの急な不調や登校しぶり、夜間の不安対応などに追われ、時間的にも精神的にも両立が難しくなったと語っています。制度や理解があっても限界を迎え、心身のバランスを取るために仕事を手放した人も少なくありません。
一方で、退職によって「ようやく子どもと穏やかに過ごせた」「焦らず向き合えた」と語る声が多数を占めました。子どもの回復には、親の安定が欠かせないことがうかがえます。しかしその裏で、収入減・孤立・将来への不安を訴える声も根強く、「安心して一度立ち止まれる仕組み」が社会に欠けている現実が浮かび上がりました。
不登校と仕事の両立を個人の努力に委ねるのではなく、柔軟な働き方・家族支援・経済的セーフティネットの三本柱で支える社会的仕組みが求められています。
7.キズキ共育塾・不登校相談員・伊藤真依のコメント
前提として、どんな選択肢にも間違いはありません。
家庭の状況や保護者さま自身の心の状況から、退職が最善である場合も多くあります。
働くということは、社会の一員であることを最も実感できる活動のひとつですので、
その繋がりがストップされると、どうしても家庭のこと(特に不登校のお子さん)に気持ちが集中しやすくなります。
そんなときに是非心にとめておいてほしいのが、
「お子さんのサポートだけを生きがいにしない」ということです。
もちろん、大切なお子さんと一緒にいる時間を増やしたり、
精一杯お子さんに向き合うことは大切なことです。
しかし、物理的に一緒にいる時間が長くなればなるほど、
そして、大切な存在であればあるほど、
自分の考えをお子さんに重ねたり、お子さんも自分と同じ考えであってほしいと感じやすくなります。
親子も別々の人間である以上、お子さん自身が自分で人生を選び取れるように一定の距離感が必要です。
保護者さま自身も趣味に打ち込んだり、
一日の中でお子さんについて考えない時間を持つことも大切です。
健全な距離感ってどんなだろう…と悩まれましたら、まずは現在の状況を私たちキズキや専門家にお聞かせいただけたらと思います。
8.「不登校と、親の仕事」のリアル〜関連記事一覧〜
今回のアンケートの関連記事は、下記でご覧いただけます。
関連記事