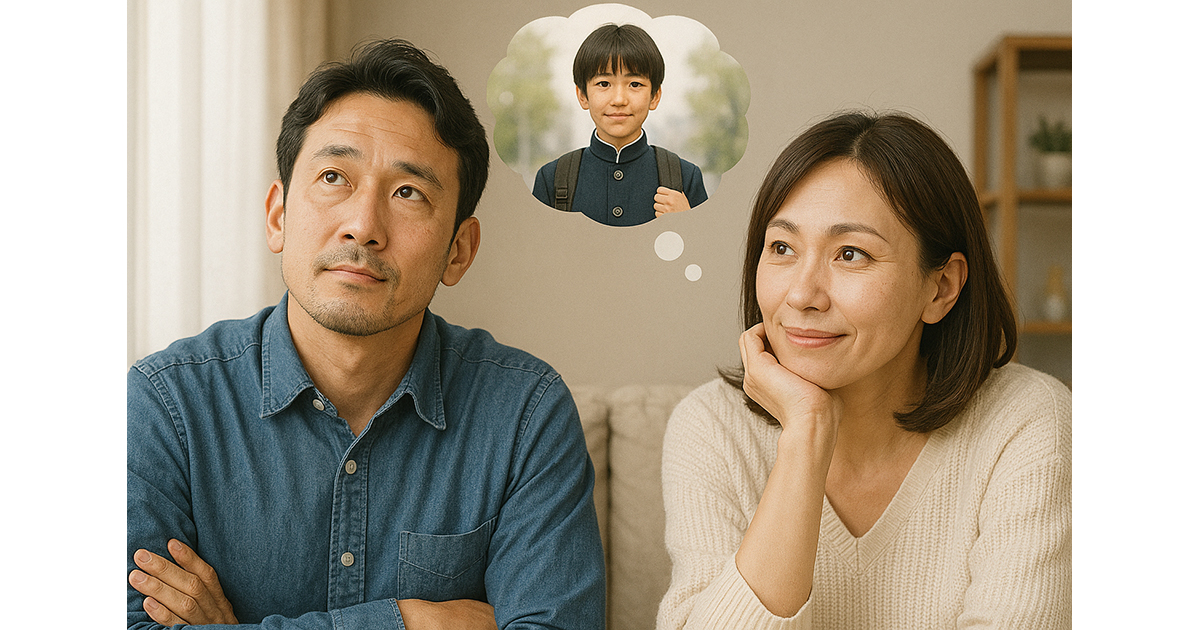【調査報道】「不登校と、親の仕事」のリアル(8)〜工夫したこと〜
子どもの不登校は、親の働き方にも大きな揺らぎをもたらします。
ウェブメディア「不登校オンライン」は、不登校の子どもがいる親438名にアンケートを実施。結果、約6割が退職・転職・就業、または働き方の変更を経験していました。
この記事では、お子さんの不登校と仕事に関連して「工夫したこと」自由記述と、それに対する編集部の分析・コメントを紹介します(回答は原文ではなく、編集部が類型化した上、再構成を行っています)。
目次
1.仕事をしながら子どもと向き合うために工夫したことがあれば、具体的に教えてください。
回答者:母親208名、父親11名、その他1名
1. 勤務時間や働き方を変えて、子どもに合わせました
- 子どもの体調や気持ちは日によって大きく変わるので、勤務時間を柔軟にしてもらいました。朝が一番不安定なことが多く、午前中は子どもの様子を見て、落ち着いてから午後に出勤するようにしています。最初は同僚に迷惑をかけている気がして苦しかったのですが、上司に事情を話すと「家庭を優先していい」と言ってもらえて、心が軽くなりました。在宅勤務ができる日は、子どもも私も少し安心して過ごせます。付き添い登校のあとに出勤できるようシフトを組んでもらったことで、子どもに付き添う時間と仕事の両立ができるようになりました。働き方の自由度が増えることで、親子の生活リズムも穏やかになりました。
2. 職場に正直に話して、理解を得るようにしました
- 最初は「子どもが不登校で」と言うのが怖くて、理由を濁して早退していました。でも、隠して苦しむよりも正直に話す方が楽だと思い切って打ち明けたんです。理解を示さない人もいましたが、「家庭を優先していいよ」と言ってくれた上司の言葉に救われました。その言葉で初めて、自分を責める気持ちが少し和らぎました。勇気を出して話してみると、意外にも周囲は温かく、「家庭の事情だから仕方ない」と受け入れてくれる人が多かったです。職場に味方ができることで、仕事を続けることへの自信が戻りました。子どものために休むことを“特別なこと”とせず、自然な選択として認めてもらえる社会になってほしいと強く思います。
3. 働き方そのものを見直して、家でできる仕事に変えました
- 出勤が難しい日が増えたため、思い切って在宅でできる仕事に切り替えました。子どもの様子を見ながら、自分のペースで働けるようにしました。家で働くようになってから、子どもが安心した表情を見せてくれるようになりました。 通勤がなくなった分、朝の時間を子どもとの会話に使えるのも大きいです。最初は仕事と家庭の境界があいまいで疲れてしまう日もありましたが、今では「仕事の時間」と「子どもと過ごす時間」を分ける工夫をしています。収入は減りましたが、心に余裕ができました。無理して続けるより、“できる形で働く”に切り替えたことで、親子の関係が穏やかになったと思います。
4. 家の中のリズムを整えて、穏やかに過ごせるようにしました
- 不登校が始まったばかりのころ、家の空気が張り詰めていました。仕事から帰ると子どもは不安そうな顔で待っていて、私も気が抜けず、常に緊張していた気がします。それで、「家の雰囲気をできるだけ明るく保つ」と決め、出勤前に少しでも会話をしたり、一緒にお茶を飲んだりする時間を作るようになりました。朝から怒らない、焦らない。それだけでも子どもの表情が少し柔らかくなります。 事については、仕事がある日は「今日はこれができたら十分」と自分にも言い聞かせ、完璧を手放しました。頑張りすぎないことを心がけています。家のリズムを整えることは、仕事を続けるための大切な土台になりました。
5. 自分の気持ちを守るために、支援を利用するようにしました
- 子どものことばかり考えて、自分のことを後回しにしていた時期があります。一人で抱え込みすぎて、体調を崩しました。その経験から、カウンセリングや親の会に通うようになりました。同じ立場の人たちの話を聞くと、自分だけじゃないと感じられて、涙が止まらなかったことを覚えています。相談できる場に通うようになって、気持ちが軽くなりました。それ以来、何かあってもすぐに助けを求めるようにしています。支援を受けることを恥ずかしいとは思わなくなりました。自分の心が元気でいることが、結局は子どもの安心につながるのだと思います。
6. 家計を守るために、形を変えて仕事を続けました
- 子どものサポートで時間が取れなくなり、正社員からパートに切り替えました。仕事の時間は減りましたが、「完全な退職」ではなく「仕事を続ける」ことで、社会とのつながりを感じられています。また、家にいる時間を活かして在宅ワークも始めて、収入を補っています。経済的な不安は残りますが、“働いている自分”を持ち続けることが、心の支えになっています。仕事があるからこそ、子どもと適度な距離を保てる日もあります。家庭を守ることと働くこと、その両方が今の私の生き方の一部です。
7. 夫婦で役割を分けて、負担を一人にしないようにしました
- 最初のころは、子どもの対応をすべて自分一人で背負っていました。でも限界が来て、夫とよく話し合うようにしました。夫にも少しずつ子どもの送迎や家事を頼むようにしました。お互いに仕事がある中で、できる範囲で助け合うことを意識しています。夫が「今日は俺が学校に連絡するよ」と言ってくれたとき、涙が出るほど嬉しかったです。「子育ては、母親がやるもの」と思い込んでいたけれど、話してみれば分担できる、夫に任せられることも多いと気づきました。家庭内で支え合えるようになってから、私自身の焦りも少しずつ和らいでいきました。夫婦で支え合えば、背負う重さも半分になる。いまはそう実感しています。
8. 周囲に助けを求めて、支えてもらう勇気を持ちました
- 以前は「他人に迷惑をかけたくない」と思い、誰にも言えずにいました。でも、「自分が倒れたら子どもも困る」と考え直して、職場の同僚や友人に打ち明けるようにしました。周囲に事情を話したら、「無理しないで」と声をかけてもらえて救われました。それからは、無理なスケジュールを組まず、頼れるときには頼るようにしています。地域の支援センターやスクールソーシャルワーカーともつながり、「こういう仕組みがあるんだ」と知っただけでも気持ちが軽くなりました。支援者に話を聞いてもらうことで、働きながらでも親としての立て直しができました。“助けを求める力”も、仕事を続ける上での大切なスキルだと感じています。
9. 子どもの自立を信じて、干渉しすぎないようにしました
- 不登校が始まった直後は、どうしても子どもの行動一つひとつが気になって、仕事中も「子どもから連絡があるかも」とスマホばかり見ていました。でも、「四六時中子どものことを考えていても、かえって関係が悪くなる」と気づきました。適度な距離を保つために、あえて仕事に集中する時間を作りました。子どもが一人で過ごす時間を“放っておく”のではなく、“信じて任せる時間”に変えたつもりです。私が落ち着いて働いている姿を見せることが、安心感につながっているのか、少しずつ子どもも笑顔が増えました。在宅で仕事をしている日に、その姿を見た子どもが「自分も何かやってみようかな」と言ったこともありました。過干渉をやめ、信頼を選んだことで、私自身の働き方にも余裕が生まれたように思います。
10. 完璧を目指さず、「できる範囲」でやると決めました
- 不登校の子どもを支えながら働くのは、本当に大変です。最初のころは家事も仕事も完璧にこなそうとして、いつも疲れ切っていました。でも、ある日「もう無理をしない」「肩の力を抜く」と決めてから、家族全員に少しずつ笑顔が戻りました。家が散らかっていても、子どもが安心していればそれでいいと思えるようになりました。食事も手抜きの日があっていい。休んでもいい。そう思えるようになってから、仕事も続けやすくなりました。“頑張らない勇気”を持つようにしています。仕事も家も、どちらも100点でなくていい。いまはそう感じています。
2.編集部の分析とコメント
不登校の子どもがいる親たちの自由回答には、「仕事と家庭を両立する」以上の切実な模索がにじんでいました。
多くの親は、勤務時間の調整や在宅勤務の導入など、働き方そのものを変える工夫をしています。
朝は子どもの不安が強いため出勤を遅らせる、付き添い登校のあとに出勤する、シフトを柔軟に組んでもらう——その一つひとつが、家族を守るための現実的な選択です。
また、職場に事情を打ち明け、理解を得ようとする姿も多く見られました。最初は「迷惑をかける」と自分を責めていた親が、上司の「家庭を優先していい」という言葉に救われたと語ります。
働き方を変えるだけでなく、自らの気持ちを守る工夫も印象的です。完璧を目指さず「できる範囲で」と決める、カウンセリングや親の会を利用して気持ちを整える、夫婦で負担を分け合う、地域の支援を頼る。
どの工夫にも共通するのは、「自分を犠牲にしすぎない」という意識でした。子どもを信じ、親自身の安定を取り戻すことが、結局は家庭全体を支える力になる——それがこの調査の核心です。
不登校をきっかけに、親たちは“働き方”ではなく“生き方”を問い直していると言えます。
3.キズキ共育塾不登校相談員・伊藤真依のコメント
私が不登校相談員として多くのお子さんに伝えていることがあります。
それは
「勉強は”試す・工夫する・継続する”の繰り返しである」
ということです。
やってみないと状況は変わらない。
上手くいかなかったら工夫しながら合う形をみつけていったらいい。
良い方法が見つかれば、それを続けていったらいい。途中で難しかったら工夫したらOKーー
それは保護者さまにも共通して言えることだと思います。
今回の調査で皆さんからいただいた「工夫する」の体験談は、そこれから不登校サポートに取り組む保護者さまが「工夫する」のステップに進む際の大切なメッセージになると考えております。
一方で、「試す」の段階では、
後戻りできない重大な決断(退職など)の場合慎重な検討が必要です。
工夫できる幅を増やすために、
今の状況に合った方法は何か、ファーストステップに迷われましたらどうかキズキをはじめとした専門家に頼ってください。
回答者ペンネーム(敬称略、本名と思われるものは編集部で変更済み):153、7091、aki、at、A母、Belle mama、biscuit、HK、HN、Inkochan、iqoooo、JJ、KIMIKO、kmama、KO、m、m-mama、Maicco、moco、momoneco、monmon、mr、ms、na_yo、natsumi、non、panda、qwert、REIKO、Sakukae、sar、sayuki、shimaky、skkt、ssss、sumyu、SY、t、teruteru、tomori、tomoto、yuuside、あいびー、あおかな、あおましいろ、あか、あきき、あきゆう、あっこ、あや、あやこ、あゆ、ありこ、あるろ、あんりんゆ、いっちゃんママ、いづみ、いぶき、えんちゃん、おじぞう、オヒルネスキー、かあちゃん、ガーベラ、かいちゃん、カエル、かくりん、かなのママ、かめさん、かよなお、きいろ、きしゃぽっぽ、きょりの、キラリ、キリム、くぅ、クープふわ、くじら、ぐっさん、くにちゃん、ケイコ、ここ、こちよ、こつぶ、こめの、さきママ、さきりんこ、さくら、さち、サハラサバク、さらさ、ジーコ、しのぶ、しのまま、ジャム太郎、ジュニママ、じゅら、しゅん、シュンシュン、ジョゼ、スイカ、すー、スカイブルー、スピカママ、すん、ゼロ、ぞー、そら、だいぶつ、たか、たかとも、たけ、たけこ、だっち、たっちゅさん、たみち、たろう、ちー、ちぃ、ちびまま、ちひろ、ちほ、ちょこぶき、つむぎ、とこ、ドナルド、とふ、とも、ともこ、ともぴぃ、なおなお、ナカジ、なな、ななな、なるなる、ぬこさん、ネコ、ねこままん、のっち、のん、パオ、はち、はっし〜、はな、ハマチ、ハム太郎、はるママ、はるりん、ハレルヤ、ぱんだうさぎ、ぴちょん、ひっとん、ひなた、ひよこ、ヒロ、ぷーた、ぶーりん、ふくちゃん、プリン、ほしの、ポッポのママ、ぽんた、まぁ、まぁしゃん、まくた、まご、まどぱぱ、まみーB、まむ、まる、マルのママ、まるまる、まろやか、みかん、みかん太郎、みずき、みずは丸、みちみち、みっこ、みっちょん、みなこ、みぴまま、みゆ、みよ、みん、みん、みんみん、めいぷる、めんめぐ、もっちぃ、もふもふ、もみ、モモ、もも、もりこ、やぎめーめー、やま、やま、やま、ゆ、ゆか、ゆっこ、ゆもみ、よう、よし、よよよ、より、らす、りま、りをはや、りんご、ルテ、レモン、わたあめ、河本、花ちゃん、瑞浪、晴れパン、不登校母、龍、苺
4.「不登校と、親の仕事」のリアル〜関連記事一覧〜
今回のアンケートの関連記事は、下記でご覧いただけます。
関連記事