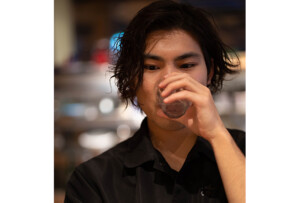
「学校に通う夢を見た」不登校中のオレが何よりも望んでいたこと
高校入学直後に学校へ行けなくなった古川寛太さんが、眠れない夜をすごすなかで渇望したのは、「学校に通う夢を見る」ことだったといいます。不登校中のリアルな...
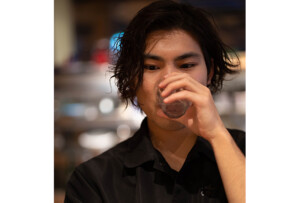
高校入学直後に学校へ行けなくなった古川寛太さんが、眠れない夜をすごすなかで渇望したのは、「学校に通う夢を見る」ことだったといいます。不登校中のリアルな...

「なぜ学校へ行けないのか」。その問いに明確に答えられず、長年苦しんできたという喜久井伸哉さん。大人になって、そもそもその問いが「回答可能なものかどうか...

学校支援員を経て小学校教員になり、20年近く教壇に立ち続けている江口ひとみさん(仮名)。現在は、2人の子育てをしながら1年生の担任として奮闘しています...

何をしていても悲しい。誰とも話したくない。そんなときでも、本を開けば、これまで出逢ったことのない世界、まったく見たことのない景色が広がっているかもしれ...

夏休みには実家や親戚宅へ帰省する家族も多いです。不登校の子どもとその家族はどう対応しているのでしょう。 「不登校オンライン」が行なったアンケートの結果...

夏休みには実家や親戚宅へ帰省する家族も多いです。不登校の子どもとその家族はどう対応しているのか、アンケートを取りました。 帰省をしたくない? 帰省を楽...

不登校生の理解が広まり学ぶ場所・居場所が整備されている昨今、文科省の調査では4割の当事者が学校内外の専門・相談機関に繋がれていない現状がある。 映画『...

「お子さんの得意科目は何ですか?」とお尋ねすると、「ぜんぶ苦手なんです」とおっしゃる親御さんは、少なからずいらっしゃいます。 「小学生のときは算数が好...
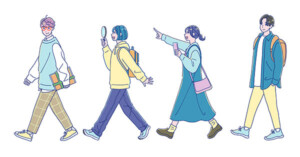
家でずっと過ごしている不登校の子を見ていると、多くの親は「そろそろ何かはじめてみない?」と声がけしたくなると思います。 「そろそろ宿題やってみようか」...

不登校の回復期の子が、勉強や学校から離れてしばらく休養するようにと勧められることはよくあります。 「好きなことをさせて、ゆっくり休養させてあげてくださ...

「不登校の子が勉強しない」という悩みは、多くの親御さんが抱えているもののひとつです。 中には、「もう何か月も(何年も)勉強していない」「小学校からずっ...

【2024年8月9日追記】 アンケートへのご協力、誠にありがとうございました。 いただいた回答をもとに記事を作成しましたので、ぜひご覧ください(アンケ...