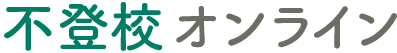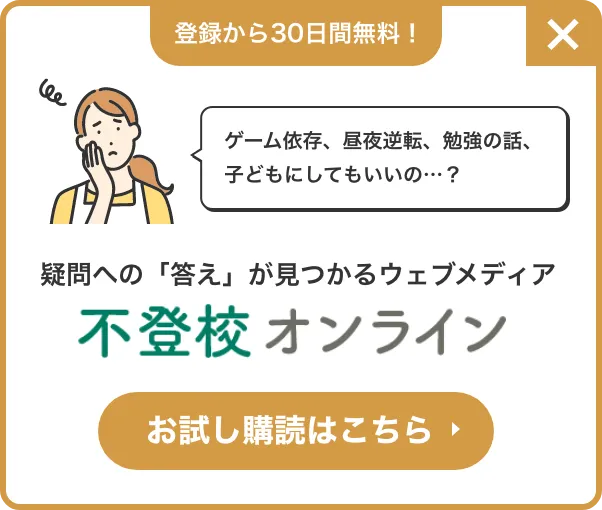「憐れむ目で俺を見るな」高3で中退した男性の自尊心が崩れた出来事【全文公開】
最後の砦さえ、跡形もなく崩れ落ちた――。高1で不登校になり、高3の秋に高校を中退した古川寛太さんは当時をこう振り返ります。今回は、出席日数を稼ぐためだけに登校していた日々のつらさについて執筆していただきました(※写真は古川寛太さん)。
* * *
高校1年生の春から学校へ行けなくなった。基本的に不登校だったが、進級するための最低限の出席をもらいに登校する機会があった。
友だちはいない。はじめは仲よくしていた彼らも、俺の出席が減るにつれ、腫れ物にさわるように距離をとっていった。1年が経つころにはもう誰も目を合わせてくれなかった。2年生になると、登校した日はクラスメイトのある男子に金魚のフンのようにくっついていた。後で知ったことだが、彼はただでさえ偏差値の高かった当時の高校の中でも1位2位を争う秀才で、卒業後は一橋大学へ進学するほど熱心な勉強家だった。俺のことを特段無視することもなければ気にかけることもない、優しいとも冷酷とも取れる態度で接した。彼とは連絡先の交換さえしていない。きっと俺のことだってもう覚えていないだろう。
勉強はわからない。得意だった勉学も、もうあっという間にわからなくなった。予習が必要な授業で俺は何度も授業の流れを止めた。中学で好成績だった数学はダントツでクラス最下位。計算式の解説では授業時間の大半がマンツーマンの指導になった。それがとても恥ずかしかった。日本史や世界史は追えないほど授業が進み、物理や化学では知らない公式にさらなる応用が加わる。音楽では歌唱テストの連絡を当日知らされるし、体育は準備運動だけで体調が悪くなり、報告なしにトイレの個室に4時間籠城する。もう何もかもがわからなくなった。
まわりからの評判も悪い。優等生だった以前とはうって変わり、「問題児」の烙印を押され続けた。学校へ行くと黒板の左上に自分の名前が複数書かれている。各教科の担当教員から呼び出しのかかった生徒の名前が入る欄。休み時間や放課後を使って各教員のいる部屋をまわり、最後に担任のいる社会科準備室へ行く、というルートをたどる。出席もしなければ課題も出さない俺に説教や小言をする教師が大半だった。何より、彼らの「困った生徒を見る目」や「憐れむような目」が俺の自尊心をこれでもかというほど砕いた。それは、数年前に大人から送られていた目線と明らかにちがったから。
それでも「学校へ行きたくない」と俺は言わなかった。行かなければならない場所だと思い続けていた。「行きたいのに行けない」という言葉で自分を守っていた。「行きたい」とは言ったものの、学校には何もなかった。なんにもなかった。結局、高校3年の秋で中退。「今の学校に通える自分」という最後の砦さえ、桜が咲くのを半年も前にして跡形もなく崩れ落ちた。(つづく)
(初出:不登校新聞620号(2024年2月15日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)
記事一覧