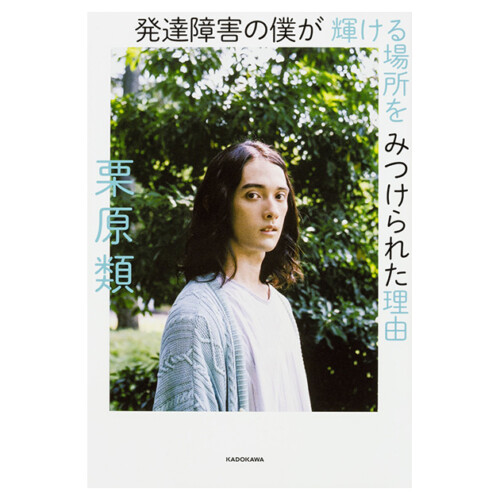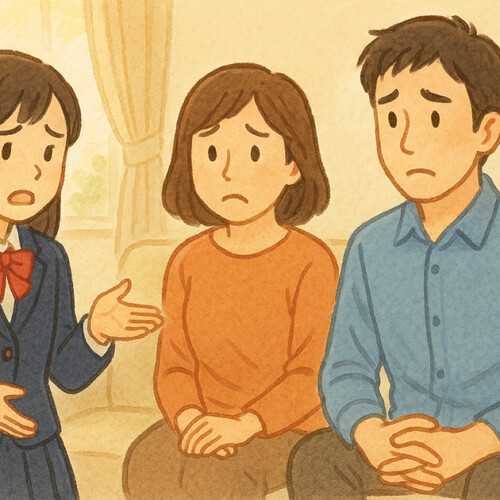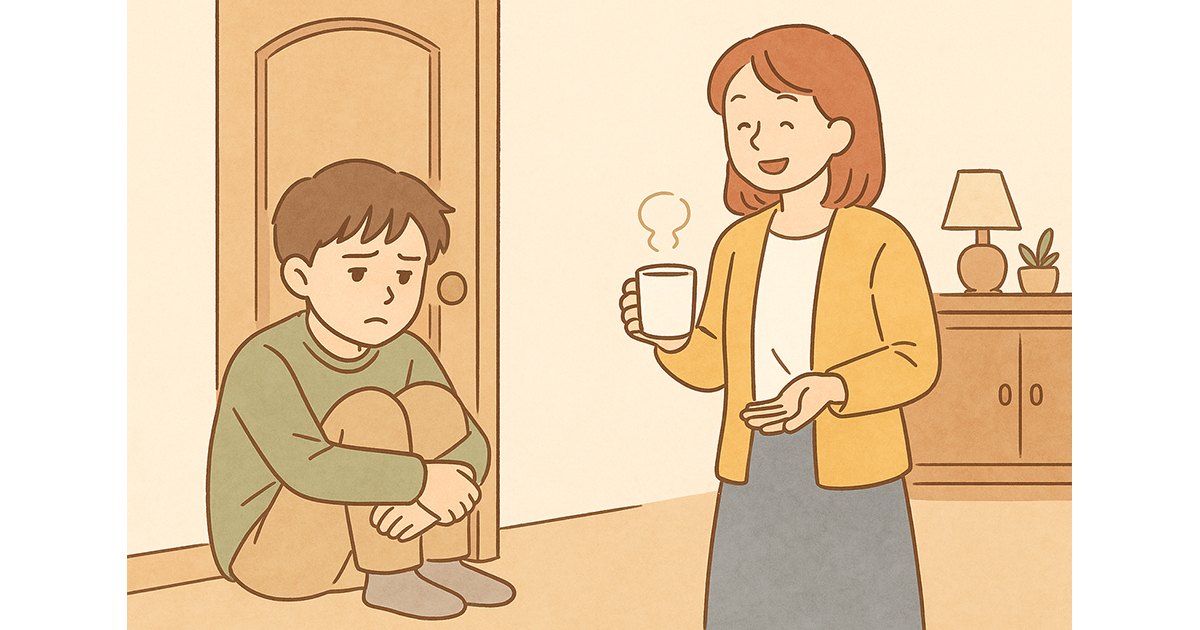
【不登校混乱期】「部屋から出てこない」わが子にできる、“距離を近づけすぎない”関わり方【不登校の知恵袋】
不登校の混乱期には、「子どもが部屋から出てこない」「1日中カーテンを閉めて過ごしている」などの状態が続くことがあります。
親としては心配になり、ついドアの向こうに声をかけたくなりますが、その距離の取り方が、子どもの心の安定に大きく関わる時期でもあります。
この記事では、「距離を近づけすぎない」ことをキーワードに、部屋にこもるお子さんへの実践的な関わり方を、より具体的に解説します。登校再開を急がず、家庭を「安心して休める場所」として整えることを目的とします。
【不登校混乱期とは】
不登校状態が定着し、今後の見通しがつかないまま時間が経過している時期です。この記事は、主にはこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校混乱期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
不登校混乱期は「見守りのプロ」になる時期〜ただし、親だけで抱え込まないで〜
不登校が始まってしばらく経ち、お子さんが自室から出てこなかったり、家族との会話が極端に減ったりしている状況は、まさに「不登校混乱期」の特徴です。
この時期は、先の見通しが立たず、親御さんにとっても不安が最も強くなる時期でしょう。しかし、お子さん自身も非常に強いストレスと疲労を感じており、外界(家族を含む)との接触を最小限にして心身の回復を最優先しています。
親御さんの役目は、この回復のための「安全基地」を提供することに尽きます。焦りや不安から「なんとかしなければ」と介入したくなる気持ちを抑え、お子さんのテリトリーに踏み込みすぎず、かといって放任でもない「絶妙な距離感での見守り」がカギとなります。
登校再開を目指すことよりも、まずは家庭内で心身のエネルギーが溜まるのを待つ、「見守りのプロ」になる意識を持ちましょう。
ただしもちろん、お子さんのことを親だけで抱え込む必要はありません。不登校や引きこもりの専門家・サポート団体に相談することで、「実際の、あなたのお子さん」が次の一歩に進むための具体的な方法がわかっていきます。
この後に紹介する対応もあくまで「例」とご認識の上、親御さんも「外」や「専門家」とのつながりを保ってください。
距離を取りつつ「安心」を届ける具体的な関わり方
この時期、親がどう関わるかによって、お子さんの安心感は大きく変わります。物理的な距離があるからこそ、不安を増幅させないような「非接触型の安心感」を伝える工夫が必要です。