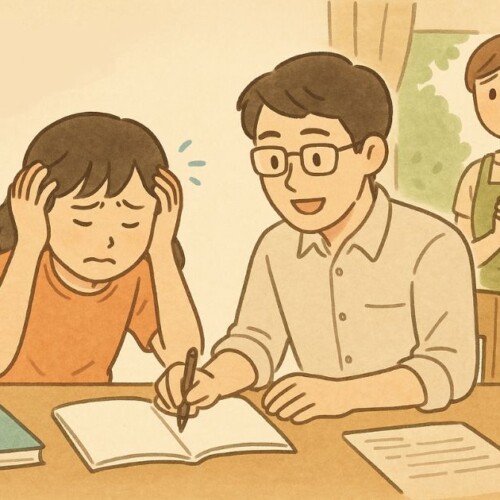【不登校回復期】「学校はムリだけど外には出たい」中学生の”次の一歩”を応援する「親の言葉」【不登校の知恵袋期】
「学校はまだムリだけど、外には出たい」——。
不登校回復期の中学生には、そんな変化が見られることがあります。
家の外に興味を持てるようになったということは、心の回復が確かに進んでいるサインです。とはいえ、親としては「それならそろそろ学校も…?」と期待がよぎる瞬間でもあります。
この記事では、「外に出られるようになった中学生」の“次の一歩”を応援するための、親の言葉かけと関わり方を具体的に紹介します。
登校の再開を急がず、子どものペースで社会とのつながりを広げていく視点を大切にしましょう。
【不登校回復期とは】
不登校は、前兆期→進行期→混乱期→回復期という経過を辿ることがよくあります。回復期とは、「不登校状態ではあるものの、心理的状態が改善され、心的エネルギーが溜まりだし、一人での外出が自由になってくる期間」のことです。この記事は、主にこの時期のお子さんがいる保護者さんのための内容です。もちろん、それ以外の時期の方にもお役立ていただけます。不登校回復期の記事一覧はこちら
【サポート団体を利用しましょう】
不登校のお子さんのことを、保護者だけで対応する必要はありません。不登校のサポート団体を適切に利用することで、お子さんも保護者さまも、「次の一歩」に進みやすくなります。サポート団体の探し方は、こちらの記事をご覧ください。
目次
回復期の「外に出たい」は、社会へのリハビリの始まり
外出できるようになるのは、心のエネルギーが戻り始めた証拠です。この時期の「外に出たい」という思いは、単なる気晴らしではなく、自己肯定感の回復と社会との接点の再構築につながる重要なサインです。
無理に目的を作らず、「行ってきたね」と受け止める
この段階では、買い物や散歩など、日常的で小さな行動から始まります。大切なのは「行動に意味づけをしない」ことです。
「えらいね」「元気になったね」といった評価よりも、「行ってきたね」「楽しかった?」と淡々と受け止める言葉が、子どもの安心感を支えます。
子どもにとっては、「親が自分の行動を安心して見守っている」と感じられることが、次の一歩につながります。
子どもの主体性を育む「選べる自由」と「待つ勇気」
外に出るようになった子どもは、少しずつ「自分で決めたい」という気持ちを取り戻しています。