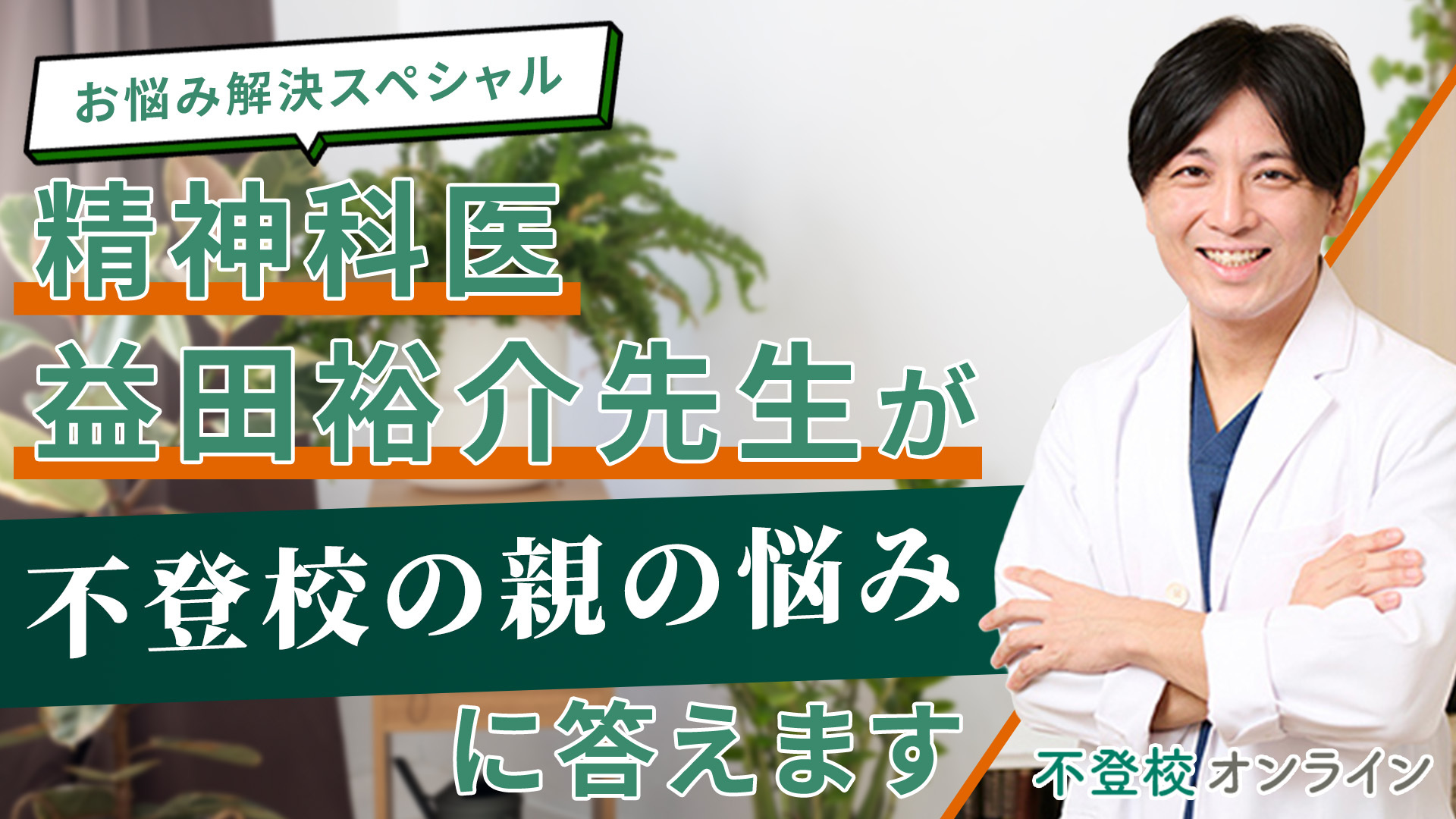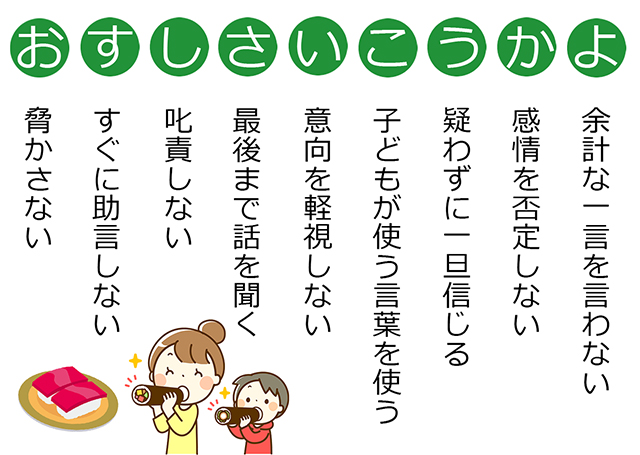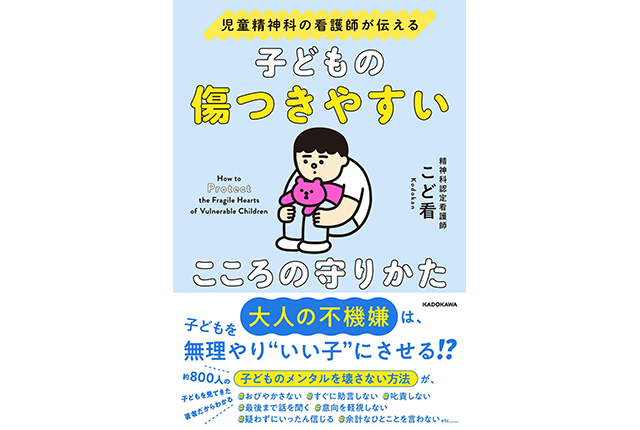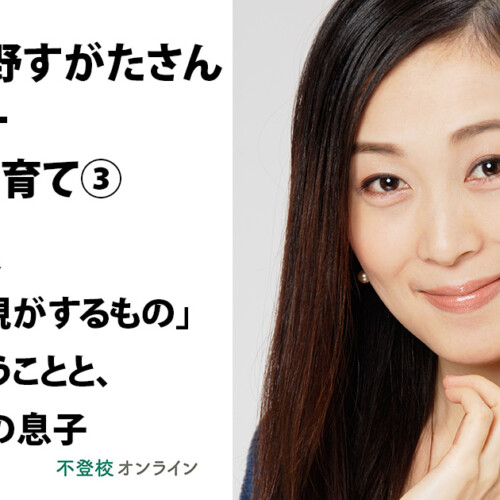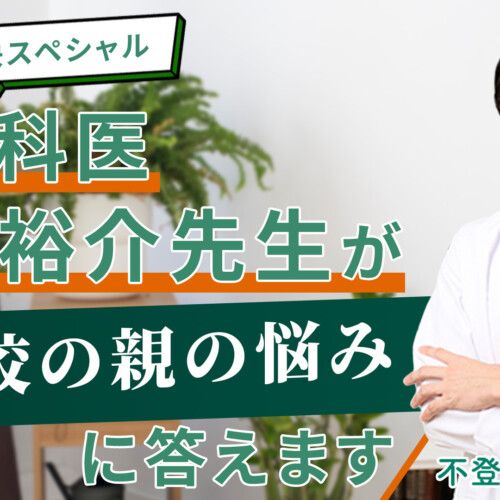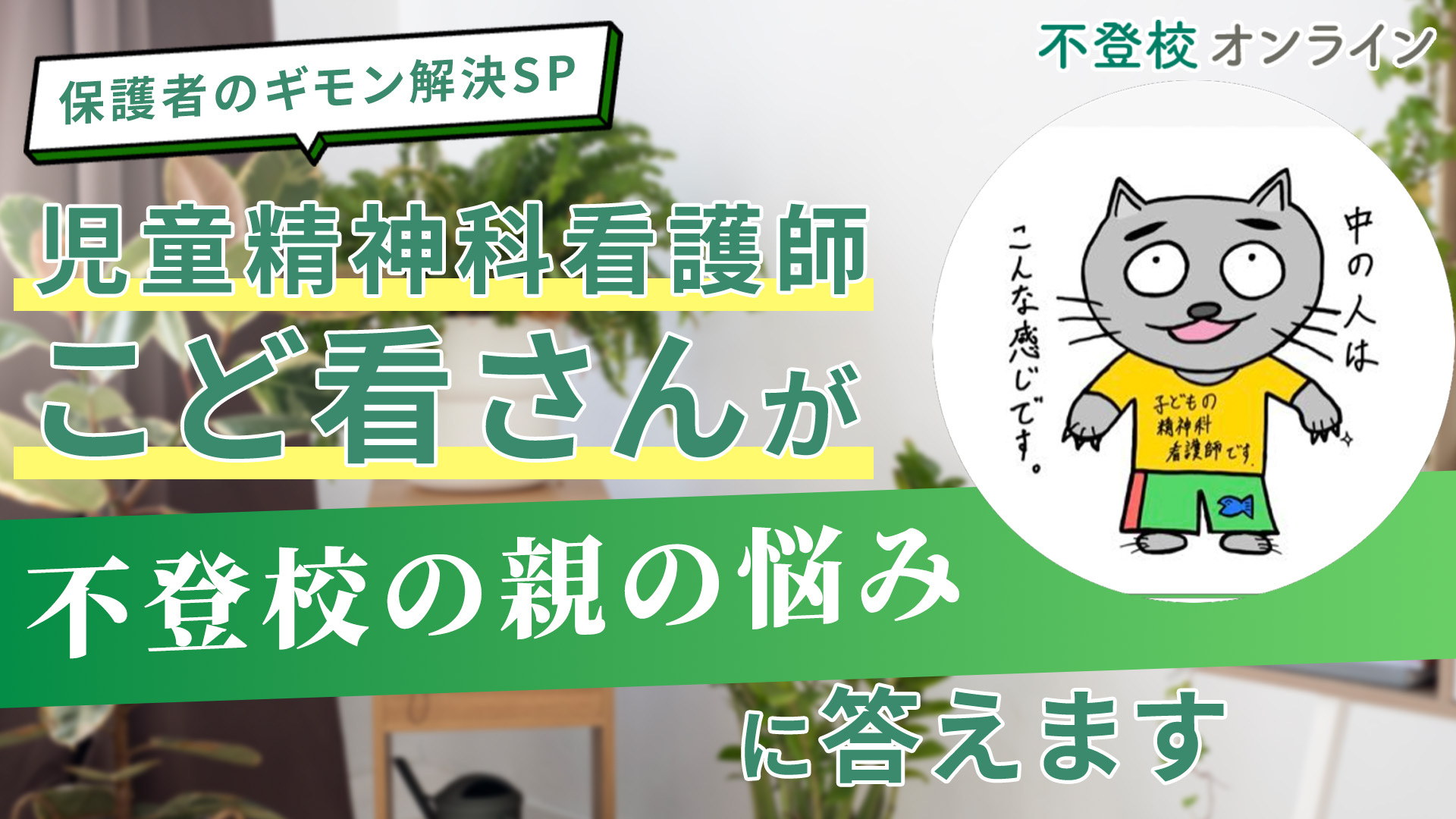
児童精神科看護師・こど看さんが“不登校の親の悩み”に答えます(1)〜児童精神科に繋がる親子に持ち帰ってもらいたいことは?〜
2025年10月24日(金)、「学校休んだほうがいいよチェックリスト(※)」を運営する3団体が、児童精神科看護師・こど看さんをお招きして、無料のオンライン講演会を実施いたしました。
テーマは「【児童精神科看護師×不登校支援のプロ】不登校の子どもの気持ちとは…?保護者のギモン解決SP」。
オンライン講演会でのこど看さんからのメッセージと、不登校のお子さんがいる親御さんからお寄せいただいた質問へのご回答を、全3回に分けてご紹介します(一部の表現は、不登校オンライン編集部が編集を行っております)。
※学校休んだほうがいいよチェックリストとは
子どもが「学校休みたい」「学校行きたくない」と言っているけど、休ませていいのかな?と心配になっている保護者の方に向けたチェックリストです。簡単な質問に答えるだけで、精神科医からの回答結果が届きます。運営は、不登校ジャーナリスト・石井しこう、好きでつながる居場所「Branch」、不登校の子のための完全個別指導塾「キズキ共育塾」の3団体が行っています。
目次
はじめに:学校休んだほうがいいよチェックリストについて
こど看:
「学校休んだほうがいいよチェックリスト」は、情報を集めていく中で、「あれ?これ、いいサービスじゃないか」と、自分でチェックしていました。誠実な内容ですし、監修も松本俊彦先生ですし。自分でも登録して実際にやって、本当に短時間でできました。
朝、お子さんから「行きたくない」って初めて言われたら、親御さんはやっぱりすごくビックリすると思います。自分では抱えきれない思いを、専門家の人はどう判断するんだろう?って、ちょっと紹介させてもらったんですよね。
しかも、単独の団体じゃなくて3つの団体で、1つに偏った考えで進んでいないですよっていうところもちゃんと誠実ですし、フォローもしっかりして、データも集めているっていうのは、本当にすごくいいんじゃないかなと思いました。
質問1:児童精神科に繋がる親子に共通して持ち帰ってもらいたいことは?
中里:
中学3年生のお母さんからの質問です。
小さい頃から集団適応が難しい女の子だったのですが、発達障害の診断で処方された薬を飲ませてきました。自分の気持ちを表現することが苦手で、人前でカモフラージュすることを続けてきた結果、小学校高学年でリストカットを覚えたり、希死念慮が強くなってきました。
目が離せなくなり、小児精神科病棟のあるところに保護入院になる予定でしたが、本人が医療で良くなるという良いイメージが持てず、断固拒否。家庭で抱えることになりました。
結果、複雑性トラウマがあることが分かり、トラウマに特化した治療を受けていくことで改善していきましたが、このように希死念慮があるような状態にまで悪化してしまった子どもが精神科病棟に入院して心の傷が癒えたり、希死念慮が消えたり、いわゆる根本治療が行われることはあるのでしょうか?
医療に繋がったとしても、ただレスパイト(在宅介護を一時的に中断して、医療保険を利用して短期入院すること)するだけで、薬で対症療法するだけの要素しかないような気がして、私も娘もすっかりアンチ精神科です。
こど看さんのもとに質問ですが、繋がってくるお子さんたちに共通して言えること、共通して持ち帰ってもらおうと思ってやっていること、共通している親の特徴など、ズバリ教えていただきたいです。
藁をも掴む思いで、不安定になった子どもをなんとかしようと思って一生懸命に奮闘している親の立場からですが、まだまだ見えていない一面があると思うので、よろしくお願いいたします。
こど看:
ご質問ありがとうございます。このケースの場合、症状などを見ていると、アンチ精神科になっちゃいますよね。
「繋がってくるお子さんたちに共通して言えること」は、答えになっていないかもしれないですけど、「本当にそれぞれ」です。
また、親御さんに共通する特徴も、「ズバリこうです」とはやはり言えません。親御さんを責める形にもなるというのもありますし、それぞれのケースに誠実に対応していますよということでもあります。
YouTubeを見ていると、「ズバリこの特徴を持っている」みたいなサムネがあったりしますけれど。
「入院を適用するかどうか」は、診察の場面で決まることではあると思うんですよね。
生活に支障をきたすくらいのこと――自分で自分を傷つけて止められないとか、希死念慮が強くなっていて自殺企図をするなど――があったら、入院にはなります。
児童精神科や児童思春期の病棟って、外から見ても全然イメージできないじゃないですか。「実際にどんなことをやっているのか?」「子どもたちは、中で安全なのかな?」というご質問は、保護者の方からよくいただきます。
児童思春期の精神科病棟の特徴としては、「日常や家庭にかなり近い」とイメージしてもらったらいいかなと思います。
精神科の急性期病棟やICU(集中治療室)のような救急医療みたいなところは、日常からかなりかけ離れているじゃないですか。
日常生活、学校、お家で子どもたちが困難を感じる場面があって、苦しんで入院されてきている。ということは、その中で何に困っているかを、日常生活を提供している中で私たちが評価していくという環境が必要なんです。
そして、困っていることが浮かび上がってきたときに、その子に対してリアルタイムで介入していくっていうのが大事かなと思います。
日常的な治療環境の中で子どもたちを守って、癒して、その子が育っていく。この3つの要素が、児童思春期の精神科病棟だと思っていただければいいかなと思いますね。
なので、本当に傷が癒えるのか?って言ったら、もちろん癒えるように私たちも対応させていただきます。
トラウマに関して言えば、トラウマインフォームドケアという考え方があります。トラウマをよく知ったスタッフが、患者さん――子どもたちだったり、保護者の皆様――に関わることによって、トラウマ体験を防ぎ、トラウマを体験してきた今までの経緯を知って、トラウマへの向き合い方や対処法を一緒に考えていくのが、児童思春期の病棟の特徴です。
トラウマに対するケアは、トラウマがメインの症状の子だから行うというわけではありません。全ての子に対して、「この子はもしかしたら目には見えていないトラウマを抱えているかもしれない」という視点で関わっています。EMDR(※)などの、トラウマ治療の専門医もいたりします。
※EMDR:Eye Movement Desensitization and Reprocessing(眼球運動による脱感作と再処理法)の略。特にPTSD(心的外傷後ストレス障害)やトラウマによる心の傷を癒すために開発された心理療法。
また、お子さんが良くなる「だけ」では、退院にはなりません。ご家族の体調や気持ち的な焦りなどが、もしかしたらお子さんに影響しているのかもしれません。ですので、お子さんとご家族のその両方がある程度バランスが取れてきたら、退院となります。
最後に「共通して持ち帰ってもらおうと思っていること」にお答えします。
親御さんもお子さんも、入院したことによって、「私の人生は、もうダメなんだ。入院も経験しちゃったし、将来ダメなんだ」みたいな気持ちを抱える方は、たくさんいらっしゃるんですね。
ただ私たちからすれば、「入院してきたこれまでのあなたが悪かったわけではないし、どんなあなたでも大切に思う大人はいるんだよ。実際に私たち治療で関わっていて、どうだった?あなたはそこにいるっていうだけで価値がしっかりあるんだよ」ということを、持ち帰ってもらいたいなとは思っていますね。
中里:
「どういう点を見たら、いい病院が見つかる」というヒントはありますか?
こど看:
まずは、「話を最後までしっかり聞いてくれるか?その上で、聞くだけで終わらないか?」は大事かなとは思いますね。
「相談に行ったけど、傾聴で終わりました」だと、「いま困っているんだよ」ということが何も変わっていないので。
相談した上で、「じゃあ、こうしましょう。こういう選択肢がありますよ」と選択肢をたくさん提示してもらえる場所がいいんじゃないかなと思いますね。
診療には時間制限もあるので、ある程度で区切らせてもらうことはあるんですけれど。
質問2:予期不安が強くて不登校に。本人は「学校に行きたい」と言っているのですが…
中里:
通信制高校の2年生の方の親御さんからです。
学校での出来事に不安を感じ、また同じことが起きるのではないか?と予期不安が強く、外出困難になり不登校になっています。行けそうなところから距離を延ばすことから挑戦していますが、なかなか上手くいかず時間だけが過ぎていきます。
今現在、学校に行けていないストレスもあり、昼夜逆転生活です。この状態を抜け出したい。車にも乗れないから心療内科にも行かれません。本人は、学校へ行きたいと言っています。何か良いアドバイスはありませんか?よろしくお願いします。
こど看:
疑り深くて申し訳ないんですけど、「学校へ行きたい」が、お子さんの気持ちなのか、保護者さんの気持ちなのかっていうのは、しっかり分けて考えたほうがいいかなと思います。
お子さんは「行きたい」と言っているんだけれども、もしかしたらその「行きたい」の裏には、例えば、「親を心配させたくないから行きたいと言わなきゃって思っている」のかもしれません。
もちろん、心の底から、「この日だけは行きたい」「友達に会えるから」などと言っているかもしれません。
お子さんが本当に「行きたい」と思っているんだったら、「何でこんなに行きたいんだろう?」「何で行きたいと思っているのか」「どういうふうにして行きたいのか。全部行きたいのかとか、1時間目だけ、給食だけ行きたいのか」といったところを確かめたり、一緒に話したりすることも大事です。
このお子さんは、車に乗れないけれど、完全に外に出られないわけではないのかな?
だとしたら、この状況で苦しいとは思うんですけど、ちょっとずつでいいかなと思うんですよね。本人ができているところに、視点・焦点を当てましょう。
「なぜ学校に行きたいか?」も、根掘り葉掘りじゃなくて、ちょっとずつ聞いていくイメージですね。本人も「学校に行けない自分」に、すごく苦しんでいるかもしれないので。
高校生だし、周りと比較して「自分は行けていないな。ダメだな」と自分を責めているかもしれません。
なので、「どういうペースで行きたいのか?」「無理をして行きたいって言っていないのか」というところをいろんな角度で声を掛けていって、その上で、聞ききらないと言うことが大切かなと思いますね。
石井:
「何で行きたいのか?」っていうことですよね。行きたい中身をすごくよく聞けば、また話が変わることもあるなと思います。
行きたい理由として、「お母さんに認めてほしい」と言う人もいますからね。行きたいんじゃなくて、認めてほしい。分かってほしい。あるいは、行きたくても行けない気持ちを理解してほしいってところがあるので。
「行きたい」という言葉にとらわれないっていうことは、すごく難しいけど、大事ですよね。
■関連記事
関連記事