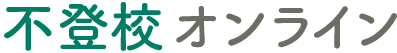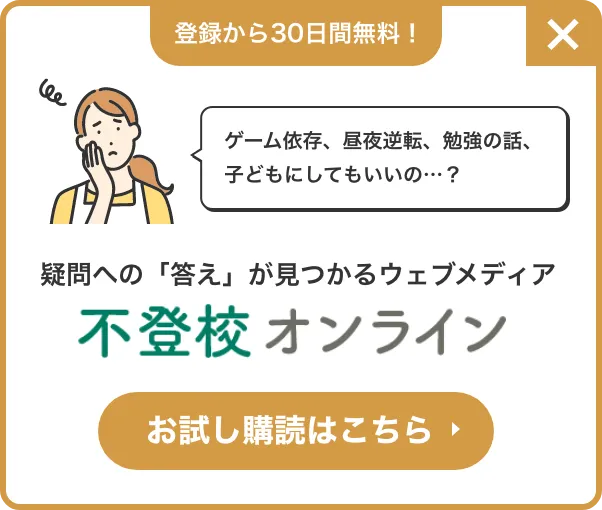「学校は無理に行くところじゃない」と現役教員が思う理由【全文公開】
私は学校教員を約20年間勤めている。学校教育とは、子どもたちが学ぶことによって「自由」を獲得するためのものであると考えている。ここでいう「自由」とは、子どもたちが自分の力で考えながら進む道を選択し、人生を切りひらいていける力のことだ。では、「学校へ行くか、行かないか」を選択する「自由」は、子どもたちにはないのだろうか。教員は担任するクラスに不登校の生徒がいると、「どうすれば学校へ来られるようになるだろうか」と考えがちである。
しかし、そもそも学校は「来なければならない」場所なのだろうか。憲法上、保護者には「教育を受けさせる義務」はあるが、児童・生徒には「教育を受ける権利」しかなく、「教育を受けなければならない義務」はない。それにも関わらず、学校に「来させたい」という発想が働くのは、学校現場に「~せねばならない、~するべき」という社会の風潮が強く反映されてしまっていることが原因なのではないだろうか。
とくに昨今、社会が以前にもまして抑圧的になっているように感じる。そして、学校という社会基盤は、多くの人たちにとって人生の一時期をすごした共通のプラットフォームであるため、学校に対する社会の目は必然、厳しいものになる。
「わいせつ教員」や「あだ名禁止校則」など、ごく一部の事例をことさら大きく取りあげる近年の報道には、もちろんそのような教員や学校に問題はあるが、いち教員としては、社会からの学校に対する悪意すら感じることがある。
社会へのアンチテーゼ
そのようななかで不登校になる生徒は、現在の社会の抑圧的な雰囲気を敏感に感じ取り、生きづらさを感じ、「あるべき姿を他人に強制する社会」に対するアンチテーゼを、「学校へ行かない」という態度で示しているのではないだろうか。
このように考えると、不登校の児童・生徒は「学校へ行かない」という「選択」をしたのだから、それで十分に教育の成果は出ているのだ。自分の進む道を「選択」し生きていく力を育てることが、学校教育の意義であるからだ。したがって、彼らの不登校は肯定されてもよいのではないか、と私は考える。
私は、大人も子どもも、自身の人生を「選択」できる社会を構築していきたい。仕事は辞めたければ辞めればいいし、学び直しをしたくなったら学び直せばよい。同様に、学校で学ぶかどうかも、各自が決めればよい。そのような社会の雰囲気をつくるために、まずは大人が児童・生徒への関わり方を見直さなければならないと思う。大人は「子どもを変えよう」としてはならない。あくまで、子どもたちが成長する伴走者であるべきだ。(学校教員・松井祐介(仮名))
■筆者略歴/松井祐介(まつい・ゆうすけ)
私立中高一貫校教員。学校の「あたりまえ」に疑問を感じながら、教員仲間・生徒とともに改善に取り組んでいる。
(初出:不登校新聞552号(2021年4月15日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)
記事一覧