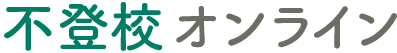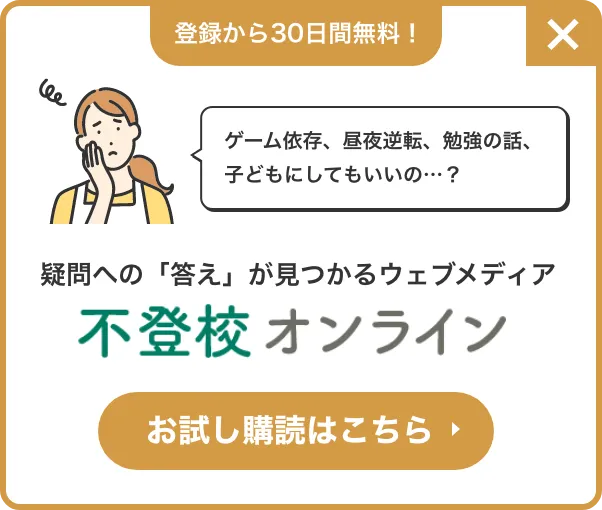【全文公開】あなたの眠れぬ夜に一冊の本を ひきこもり読書のすすめ 第1回『愛が嫌い』(町屋良平)
何をしていても悲しい。誰とも話したくない。そんなときでも、本を開けば、これまで出逢ったことのない世界、まったく見たことのない景色が広がっているかもしれません。新連載「ひきこもり読書のススメ」では、不登校経験者である書籍編集者・ライターの藤森優香が、いま学校に行っていない人・学校が苦手な人におすすめしたい本を紹介していきます。よければ、お子さんに薦めてみてください。第1回は町屋良平さんの『愛が嫌い』です。

藤森優香(ふじもり・ゆか)
ライター・編集者。ひきこもり期間中、読書で現実逃避をする術を身につける。現在は不登校オンラインでの執筆のほか、教育・ビジネス・実用関連の媒体で執筆している。趣味は、恋愛リアリティ番組を見ることと、村上春樹の登場人物のマネをして過ごすこと。
* * *
町屋良平さんは、1983年生まれの小説家です。2019年に『1R1分34秒』(新潮社)で芥川賞を受賞しています。複雑な親子関係や身体の感覚をテーマにした作品が多く、読んでいて登場人物の思考の流れにスルスルと入り込めるようなおもしろさがあります。
単行本『愛が嫌い』には、「しずけさ」「愛が嫌い」「生きるからだ」の3作が収録されています。「しずけさ」「愛が嫌い」を中心に、それぞれの魅力に迫ります。
「しずけさ」 起きているのか寝ているのかーー昼夜逆転の感覚
「しずけさ」は、「なんとなくのゆううつと不眠」によって、「クビのようなかたちで」会社をやめた25歳の青年と、両親が深夜に薬物パーティを開くために毎晩家を追い出される小学生の交流が描かれます。
……このように書くと、親の支配下で生きるしかない小学生の被害者性や、仕事がしたくてもできない若者の社会的な弱さを描いた話、と思われるかもしれませんが、ちょっと違います。
この話のおもしろさは、主人公の思考や感覚がひどくあいまいなことにあります。特に冒頭の青年の語りは、精神の不安定さを顕著にあらわしています。
真夜なかでは、何年も前のことが昨日だ。それは明日のことである感覚とすごく似ている。夜のしたでは記憶と日常がそこらじゅうに散らばっていて、塊になって一挙に襲いかかられるような、特異な時間感覚がある。(p. 6)
みえているものをみえているということも、じぶんではよくわからない。
みえていないということはとうぜんわからない。(p. 7)
この青年は精神に不調をきたしていますが、引きこもりの経験があれば既視感を覚える方も多いのではないでしょうか。夜中じゅう、起きているのか寝ているのか自分でもよくわからない。自分の感じていることが、夢なのか現実なのかよくわからないまま思考が流れている。こうした感覚は、私自身、不登校だった高校時代や、昼夜逆転の生活をしていた大学時代に味わったことがあります。
青年は、自分の体も自分の言葉も壊れているからこそ、小学生の前にいると、
「ただ大人がそこにいる状況そのものを求められている」(p. 40)
と思えて気楽さを感じます。
一方、真夜中に家を追い出される小学生のいつきくんは、「いつきくんをやめたがって」います。両親はいつも優しいのに、なぜ夜中に自分を追い出すのかわからない。大人の行動が理解できないのは自分の幼さが原因だと思っており、幼い自分のことが嫌いです。そして、両親が夜中によくないことをしているのを知っていながら、それが社会に明るみになれば自分が「被害者」になることに恐怖を感じています。
だからこそ、いつきくんは、自分のことを「椚(くぬぎ)くん」と別人の名前で呼ぶ精神的に不安定な青年といると安堵し、
「おまえがいると、じぶんが子どもだっていう罪悪感みたいのが、なくてたすかるよ」(p. 37)
と言います。
いつきくんは、ろくに会話が成立しない25歳の青年に自分の思いを語るなかで、ひとりでどんどん話を展開し、さっきまでは思いもよらなかった認識に出会っていきます。
ちなみに、著者の最新作『生きる演技』には、本作で小学生だった笹岡樹(ささおか・いつき)くんと同姓同名の高校生が登場します。高校生は「両親が家で麻薬を栽培し、夜中にドラッグパーティをして逮捕された」という過去を持つことから、本作の小学生・いつきくんが成長した姿、とみることもできるので、ぜひ読んでほしいです。
「愛が嫌い」 自分にはいったいなにが「ない」のか
2作目に収録されている「愛が嫌い」の29歳の主人公も、自分が何をしたいのかわからないという「自我のなさ」を抱えています。
自分には先ゆきというものがまるでない。生きがいもなければ野心もない。夢もなければ愛もない。ないないづくしの自分のほんとうの「なさ」がなんなのか、それこそがぼく自身にもわからないコアな性質だった。どうも気力に欠けている。親や友だちに叱られても、それを自分の問題として正確に捉えられていない。(p. 109)
「何がしたいの?」と言われても自分が何を希望しているのかわからない、という感覚は、私も子どものころに何度も味わったことがあります。大人になるにつれて、「あのとき求められていたのは、私が何をしたいのかではなく、周りを納得させる言葉だったのだ」と気づいて、周りが求めているであろう言葉を発することができるようになりました。しかしいまも、「ほんとうは何を思っているのか?」と問われると、全然わかりません。それにもかかわらず、あるいはだからこそ、周りの希望に沿って発言をしたあとは、どっと疲れます。
主人公の気持ちを代弁するかのように登場するのが、主人公と同じ名前を持つ2歳児のひろくんです。主人公の友人の子どもであるひろくんは、多くの2歳児が話す簡単な言葉すら発することがありません。主人公の発言に対して、
「まったく返答がかえってこないからこそ、孤独とも切り離せぬ解放感がある」(p. 94)
と語り、穏やかな時間を過ごします。
言葉を話せないひろくんと接することで、主人公は自分自身の欲望に向き合うことができます。2歳のひろくんや、ひろくんと向き合う主人公の視点を借りて、読者もまた、自分自身のありのままの感情・欲望と向き合っていくことができます。
3作目の「生きるからだ」も1作目、2作目と同様に、自我や感覚を失っている主人公が登場します。そして主人公は物語のなかで、新たな自分を発見していくことになります。
単行本『愛が嫌い』には、私が不登校していたころに感じていた虚無感や不安定な感覚がびっくりするほど出てきます。自分がわからない、何をして生きていったらいいかわからない、という方がいたら、これらの物語に触れてみてはいかがでしょうか。(つづく)
記事一覧