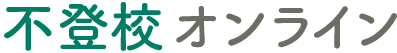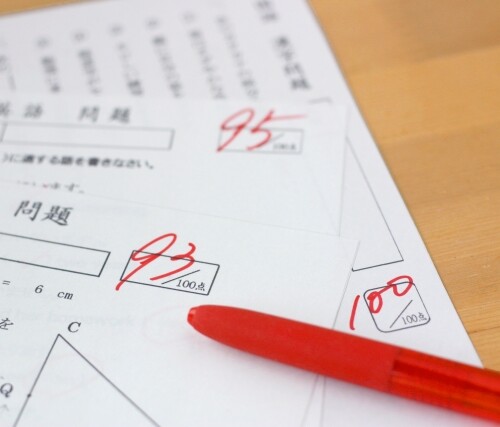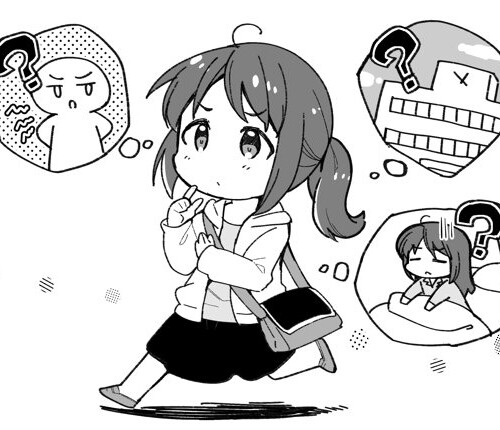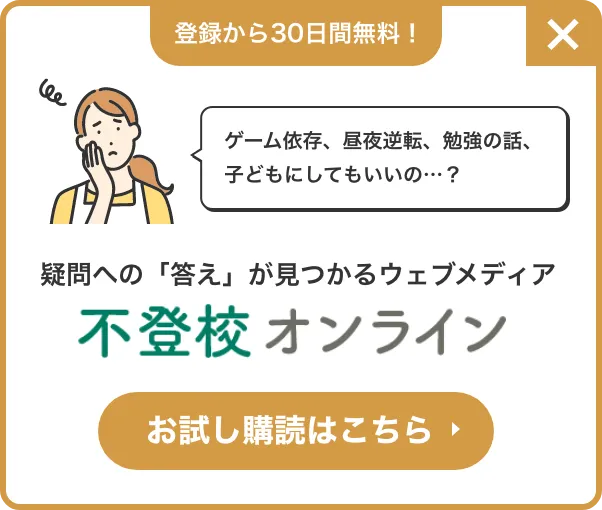いじめにより中2で不登校、今も残る私を傷つけた一言と支えた一言【全文公開】
中2で不登校を経験した星川葉さんは、両親からの言葉に傷つき、また支えられたという。両親の言葉とはどんなものだったのか、ご自身の経験を執筆いただいた(※写真は星川葉さん)。
* * *
中学2年生の秋ごろ、私は転校を経験した。地元の中学や友だちが大好きだったので「転校したくない」と私は両親に訴えた。でも、家の事情や学区の縛りでどうすることもできず、田舎の中学への転校が決まってしまった。
そして転校を機に私の地獄の日々は始まった。新しい学校での生活は、とまどいの連続だった。学年のクラス数は倍以上に増え、制服もリボンの結び方さえわからないセーラー服になった。なかでも1番つらかったのは友人関係だった。まわりの子に声をかけ、私は必死にクラスになじむ努力をしたけれど、うまくいかなかったのだ。クラスメイトからの誘いを1度断っただけで、あからさまにイヤな顔をされ次の日からは声をかけても無視をされた。 ほかの子に話しかけてみても、一応仲間には入れてはくれるものの部外者の私は空気のように居ない存在として扱われるだけだった。
グループ意識が強く輪にも入れてくれないクラスに私はしだいに疑問を感じるようになった。そして、私はクラスから孤立した。1日中誰とも話さなくなり、学校ではただ時間がすぎるのを待つだけ。息苦しい毎日をこなすたびに「転校さえしなければ」という後悔だけが、私のなかで膨らんでいった。
それでも、私は自分の心のうちを親に話すことはしなかった。それは、両親から「人に迷惑をかけるな。正しいことをして、胸を張って生きなさい」とつねに言われていたからだ。厳格な両親に学校のつらさと不満を話すなんてできなかった。
しかし状況は変わらず、私は限界を迎えた。毎朝お腹が痛くなり、どうしても学校へ行けなくなったのだ。しかたなく両親に話して、しばらく学校を休ませてもらったけれど、やはり両親は休むことを認めてくれなかった。「世間体があるから学校へ行け」と父は言い、母も「学校は行っておいたほうがよいのよ」と私に言った。
ぶちまけた本音
でも私の心と身体は、とっくに限界だった。そして私はある日ついに本音をぶちまけた。「私は学校へなんか行きたくない。こんな地獄をあなたたちは味わったことがあるのか。私がこんなにつらいって言っているのに世間体のほうが気になるの? 私と世間と、どっちのほうが大事なのよ!」と両親の前で泣き叫んだ。5人兄弟の真ん中で育ち、小さいころから親の顔色をうかがってばかりだった私にとって、両親に心の底から抗ったのはこの日が初めてだったかもしれない。
すると両親は私が泣き叫んだ日から何も言わず学校を休ませてくれるようになった。初めて不登校についても勉強してくれたようだった。
私にはその後の母からの言葉で今でも忘れられない言葉がある。それは、学校へ行かなくなってから1カ月ほどが経ち、担任が家に来たときのこと。学校へ来るよう私を説得する担任に「先生。義務教育は子どもが学校へ行きたいと言ったとき親が行かせる法律なので、子どもが行きたくないというなら行かせなくていいんです」と母は言ったのだ。
初めて母が私の気持ちを理解し寄り添ってくれた気がして、担任が居るにも関わらず私はその場でわんわん泣いた。今までとはちがう、うれし泣きだった。そのあと母は「あなたのことを考えられなくて、私たちの意見を押しつけて今までごめんね」と私に言ってくれた。
「こんなつらい思いをしているのは、転校させられたからだ」と親を憎んだこともあったし「世間体が」と言った父の言葉は今でも心の傷になっている。しかし、その後の両親の対応があったからこそ学校へ行かなければというプレッシャーから解放され、私はここまで生きてくることができた。親が変われば子どもの世界も変わるのだ。両親の対応と母のあの日の言葉に、私は今も感謝している。(不登校経験者・星川 葉さん・40歳)
(初出:不登校新聞567号(2021年12月1日発行)。掲載内容は初出当時のものであり、法律・制度・データなどは最新ではない場合があります)