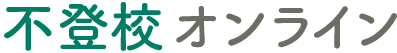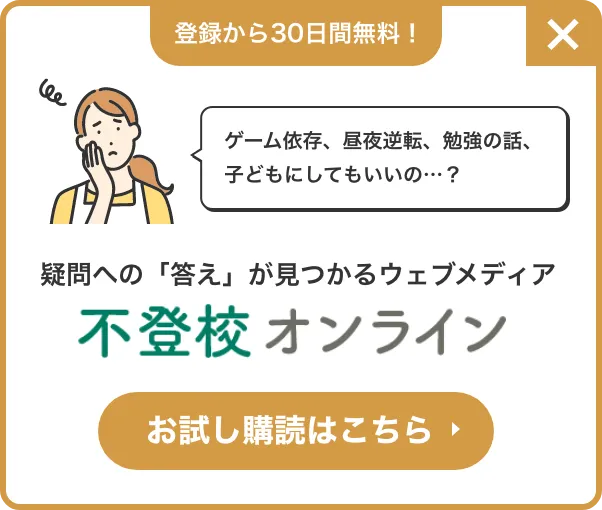ゲイアクティビスト砂川秀樹さんに聞く
同性愛の当事者とその親や教師との合計19通にもおよぶ往復書簡が収められた著書『カミングアウトレターズ』。今回はその共同編集者である砂川秀樹さんに、本書に込めた思い、同性愛問題の現状、また不登校との関係についてうかがった。
――本を出版するきっかけは?
私はゲイであることを公言して活動していますが、カミングアウトをするときに渡せる本がほしいとつねづね考えていました。
というのも、自分がゲイやレズビアンなどの同性愛者であるとうち明けるとき、直接的な会話だけではなかなか説明しきれない部分があるんです。相手に心の準備ができたときに、相手の意志で読めるものとしては本がもっとも適切だと考え出版にいたりました。
私が初めてカミングアウトしたのは、中学2年生のとき。親友に「好きな子がいて、男なんだ」と話したんですね。泰然とした子で、淡々と私の話を聞いてくれ、受けいれられたと感じました。最初にカミングアウトする相手の反応というのは重要です。その反応が、その後自分を受けいれられるかどうかに大きな影響を与えるからです。
――反応の多くが、不登校の子どもを持つ母親の場合と似ていますね。
本書では母親と子、教師と生徒の合計7組のカミングアウトしたときのことをふり返る手紙とそれに対する返事が収められています。カミングアウトを受けたときのことを多くの人が「頭が真っ白になった」と語っています。なかには、「私の育て方がいけなかったのではないか」と、みずからを責める母親もいます。
なぜなら、親の多くは学校に行って、結婚して、子どもをもうけて家庭を築いてきました。それが「社会の規範」であり、自然なことだと信じてきました。当然、自分の子どももそういった道を歩むものだと思い込んでいたにもかかわらず、「私は同性愛者である」という一言で、その土台はすべて崩れてしまうわけです。
そうした「社会の規範」とは非常に画一的なイメージを刷り込み、それから逸脱するということは、世間一般では「ふつうではない」ということになります。
異性愛を当然視する社会のなかで、同性愛であるということは「ふつうではない」人間としてつねに問われ続けることになります。
同性愛の当事者が抱える生きづらさや苦しみの起点はそうした「社会の規範」にあるわけで、「不登校」についても同様なのだと思います。そうしたなかでカミングアウトをすることは、家族など親密な関係のなかで、「社会の規範」を問い直すことであり、あらたな関係性を再構築する第一歩につながるものだと思います。

同性愛者は見えない存在